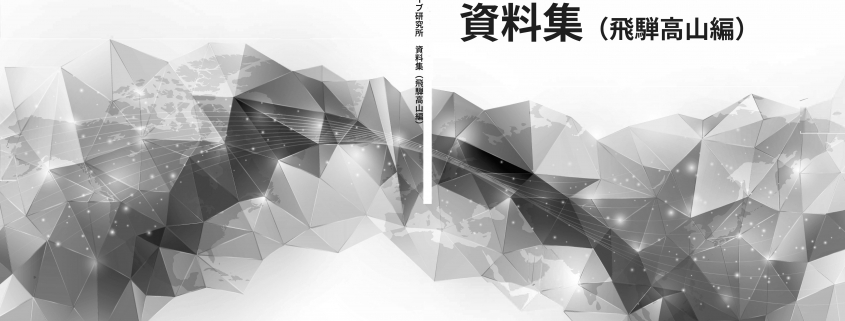アーカイブ年: 2023
座喜味城跡
西海岸を見渡せる標高127mの丘の上に築かれています。築城年代は15世紀前半で、座喜味の北東4kmに位置する山田城の城主・護佐丸(ごさまる)が北山監守の時、山田城を取り壊してその石材を運ばせてつくらせたと伝えられています。城は主郭と二の郭からなり、外周365m、総面積7,386㎡で、沖縄の城としては中規模のものです。城壁は琉球石灰岩によるあいかた積みを基調とし、アーチ門とその両脇は整然とした布積みとなっています。
座喜味城(ざきみぐすく・ざきみじょう)は、沖縄県中頭郡読谷村にあったグスク(御城)の城趾。日本軍が高射砲陣地を構築していたため、十・十空襲と沖縄戦で壊滅的な被害をうけ、瓦礫の丘陵地となり、また1974年まで米軍基地ボーローポイント内のナイキミサイル通信基地となっていた。沖縄返還を機に返還の機運が高まり、1974年に米軍から返還された。調査と復旧が進められ、通信基地に駐屯していた退役軍人も驚嘆するほどの美しいグスクとしてよみがえった。2000年、世界遺産に登録された。
概要
築城家として名高い読谷山按司、護佐丸によって築かれたといわれる15世紀初頭の城。城郭の外周は365m、城郭内面積は7,385㎡。なだらかで優雅な曲線を描く城壁は続日本100名城にも選ばれている。
城の上からは中頭地方周囲を広く見渡せる高台にある。海域や周辺離島まで見え、軍事上の要衝に存在した。城門のアーチに楔石を用いており、アーチ門では古い形態とされる。また、城郭の突出部は琉球の城郭に特徴的であり、防衛上の工夫と見られる。瓦が出土しない事からかつてあった建物は板葺きと考えられている。
2018年には南側に世界遺産座喜味城跡ユンタンザミュージアムもオープンした。
歴史
1416年から1422年に読谷山の護佐丸(ごさまる)が築城したとされている。
護佐丸は中北山の争いから逃れた今帰仁王子が伊波城に勢力を持った伊覇按司の三世の次男と言われる。先代山田城主読谷山按司(山田按司)も伊覇按司の一族係累であったが嗣子がなかったため、城主の兄弟の伊覇按司の三世の次男護佐丸が養子となって読谷山按司を継いだと伝えられる。1430年に中城城に移封されるまで読谷山按司を名乗った。
出土品に16世紀のものも見られる事から、護佐丸の移封後もしばらく利用されていたと推定されている。座喜味城の貿易遺物は15世紀中期以後であり、護佐丸が座喜味城を離れた後の年代であるため、近年いしゐのぞむは以下の新説により座喜味觀に大きく轉換を試みてゐる。「おもろさうし」78番(卷二)の越来按司の子「(ま)たちよもい」が尚泰久であることは定説だが、別途卷十五の「宇座のたちよもい」を泰期とする舊説は誤りであり、兩者はともに同一の尚泰久=懷機=國公道球である。尚泰久が護佐丸を中城に移した後、自ら懐機の名(越來の福建字音)で座喜味城下の長濱で南海貿易を行なひ、國公(越來及び懷機の同音)の道球(泰久の同音)として『琉球國由來記』卷十に記録されたのである。なお、この新説は発表間もなく、定説となってゐない。
久高島
久高島は沖縄本島の知念岬の東の海上5.3kmにある、周囲約8.0kmの小さな島。沖縄では琉球王国の時代から特別な島で、島自体が沖縄最高峰の聖地です。
琉球開びゃく始祖・アマミキヨが降り立った島として、琉球の神話や神事が今も息づく島で、島民はその歴史や神事を大切に守り継いでいます。
久高島(くだかじま)は、沖縄本島東南端に位置する知念岬の東海上5.3kmにある、周囲8.0km[1]の細長い島である。全域が沖縄県南城市知念に属する。人口は238人、世帯数は153世帯(2020年4月末現在)
地理
北東から南西方向にかけて細長く、最高地点でも標高17m[3]と平坦な島である。将来懸念される津波襲来に備えて、300人を収容できる避難施設(上部は海抜21.35m)が設けられている[4]。土質は島尻マージと呼ばれる赤土で保水力には乏しい。河沼はなく、水源は雨水と湧き水を貯める井泉(カー)に依存している。海岸沿いには珊瑚礁で出来た礁湖(イノー)が広がっている。
北東約2.1km沖にウガン岩がある。
歴史
琉球王国時代には国王が聞得大君を伴って久高島に渡り、礼拝を行っていた。後に本島の斎場御嶽(せいふぁうたき)から久高島を遙拝する形に変わり、1673年(延宝元年)からは、国王代理の役人が遙拝を務めるようになった。
近世・近代には鰹節の産地として知られ、徐葆光の『中山伝信録』でも「鰹節は久高島産のものが良質」と述べられている。
1945年1月7日に日本軍から強制立ち退き命令がだされ、金武町屋嘉の集落に身を寄せた[6] (久高島住民強制疎開の碑)。そのためやんばるでの避難生活や収容所での栄養失調やマラリアで亡くなった住民が多いといわれ、沖縄戦での犠牲者は男性が13名、女性が24名、子どもが27名の計64名である。1946年5月に帰島が許された。
行政区域上は1908年(明治41年)の島嶼町村制施行時に島尻郡知念村久高となり、2006年(平成18年)に知念村が佐敷町、玉城村、大里村と合併したため、南城市知念字久高となった。
2021年(令和3年)11月、福徳岡の場の噴火から生じた大量の軽石が沖縄の海域に移動。安座真港と久高島をつなぐフェリーが欠航するなどの影響が出た。
社会
公有地や電力会社所有地などを除き、土地を自治会である字(あざ)名義で登記して「総有」する、琉球王朝時代の地割制度が唯一残っている。家を建てる時は字総会の許可を得て、普段は土地を自宅や畑として使うものの、島を出る際には字へ返す。島の約3分の2を占めるリゾート開発の計画が持ち上がったことをきっかけに、1988年、「久高島土地憲章」として明文化された[9]。
リゾート計画は立ち消えとなり、 島内は観光開発がほとんどされず、集落は昔ながらの静かな雰囲気を残している。後述する各聖地を回るにも標識がないため、詳細な地図をあたるか、地元の人に聞かないと探すのは難しい。
抱石庵
抱石庵(ほうせきあん)は岐阜県岐阜市にある大正時代の民家。哲学者・仏教学者である久松真一の自宅である。
久松真一、及び父である大野定吉が1913年(大正2年)に建てた住宅である[1]。抱石庵は久松真一の号であり、晩年(1974年から1980年)に暮らした岐阜の自宅の呼称である。久松真一の書幅、関係資料を展示する施設として改修。2007年(平成19年)に久松真一記念館として開館している。2017年(平成29年)10月27日に国の登録有形文化財に登録されている。登録有形文化財としての登録名称は抱石庵(久松真一記念館)である。
哲学者・久松真一は明治22年岐阜市に生まれ、後に京都大学教授として禅哲学を展開した、西田幾多や鈴木大拙と並ぶ近代日本の代表的な思想家です。その生家である久松邸の改修を依頼されたのは私が岐阜県立森林文化アカデミー教員時代の2005年でした。
2002年ころから、改修設計の研究をはじめていたものの模索状態であった2005年に「建築病理学」を知り翌年には「木造建築病理学」講座をアカデミーでスタートさせる準備段階で幸運にもご依頼のあった仕事でした。
調査は以下の通り進みました。尚「抱石庵」の命名は、久松真一の師匠である西田幾多郎の命名だそうです。
曹洞院
下田市街地より県道下田南伊豆線で西に3km程行くと、山合いに第25番札所の曹洞院はある。周りを自然林に囲まれ、静かなたたずまい。シンプルな造りの山門は左甚五郎作と伝えられている。本尊は十一面観音。
幾度かの火災のため記録が焼失してしまっていて、詳細な沿革は不明となっています。かつては弘法大師修行の霊蹟で大師山とも言われる真言宗の大刹でした。戦乱で焼失した後、1525年(大永5)に七堂伽藍を再建、その際に曹洞宗へと改宗しました。1593年(文禄2)に山火事で類焼しましたが、1596年(慶長元)に再建されています。
23.伝説「左甚五郎の山門」
大賀茂の林山、少林山曹洞院の山門は江戸初期の名匠、日光陽明門にある「眠り猫」の作者、左甚五郎の作と伝えられている。
此の山門は別名「響門」と呼ばれ、寺内にある「金剛水」は弘洪大師ゆかりの井水と共に有名である。
曹洞院は元禄年間に火災のため大部分の建物が焼失したが、響門(山門)は本堂から大部離れた森の中にあったので、幸い火災を免れた。
響門はクギ一本も使わない完全なクサビ門で、中ほどの敷居の上で拍手を打つと前方の山に響きが伝わって、鴬の声に聞えたり小鳥の声に聞えたりして響が伝わってゆくので、響門と呼ばれるようになったと云う。
四脚門の切妻造りで、現在は桟瓦葺であるが、昔は茅葺であったと云う。
斗供は出三斗、中央及び前後の梁の上に蟇股があり、蟇股の中に浮彫が施されている。両側の外部には椿及びぼたん。その裏側にはそれぞれ花菱と桐、中央の蟇股にはおもだかの紋様が刻まれている。おもだかは此の門を寄進した武士の家紋であろうと云われる。蟇股の浮彫をはじめ、虹梁・懸魚・こぶし鼻等
の紋様は、素朴であるが気品を持っている。棟札の銘によると「延宝九年(1681)此門新造」と記されている。
左甚五郎は「一生に同じものを二度と作らなかった」と伝えられるが、「ここの門と曹洞院の門とは同じものだ。嫁があったら尋ねてゆけ。」と誰かに云い残したという事だが、「こゝの門」がどこにあるのかはっきりしない。
先年、曹洞院住職伊藤仁重老師(昭53.8亡)を尋ねて、「響門」の話を伺った時、先代の臼井祖猛師が片瀬の竜渕院の山門が「こゝの門」を指しているのではないか、というのを聞いたことがあると話された。
響門は名工の作として、今日でも柏手を打てば妙なる響を伝えてくる。
下田市の民話と伝説 第2集より
【研究論文】地域資源デジタルアーカイブにおけるオープンデータの有用性の研究 ~ 沖縄の地域文化遺産を例にして ~
1.はじめに
官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことが義務付けられた。しかし、2022年9月の時点で、沖縄県内市町村の取り組み率は、1位である岐阜県の100%に対し、26.8%と全国最下位だ。結果から、DXに対する意識の格差やデジタル技術不足の現状を知った。また、沖縄には特有の地域文化遺産が存在する。それらを地域活性化に活かしたいと考えた。
そこで、本研究では沖縄の地域文化遺産を中心にデジタルアーカイブを行うとともに、データを活用してWebページ制作を行う。そのWebページを地域文化遺産の保存、地域活性化を目的としたオープンデータ化を行い、どのような有用性があるのか明らかにする。
2.研究の方法
①オープンデータの定義、意義・目的などの基本となる情報やオープンデータ化における課題など、その活用推進の社会的背景について調査を行う。
②国及び地方公共団体が取り組んでいるオープンデータの利活用事例を調査する。事例を参考に、沖縄がオープンデータに取り組む際の課題や改善点について考察する。
③デジタルアーカイブの対象を、沖縄の地域文化遺産を情報収集、文献調査して決定する。現地で対象の地域文化遺産の撮影を行い、実際の情報、資料を収集・記録する。
④撮影データをもとに、地域文化遺産の保存、及び地域活性化を目的としたWebページ制作を行い、オープンデータとして公開する。
3.研究の結果
オープンデータの定義とは、機械判読に適し、二次利用可能なルールが適用され、無償で利用できるように公開されたデータである。その意義・目的は、諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化、透明化・信頼の向上だ。日本でオープンデータの活用が推進されるきっかけとなったのは、東日本大震災や急速なインターネット普及による情報社会化が挙げられる。オープンデータの懸念点は、誰でも容易に利用できるため、個人情報漏えいのリスクがあることだ。他にも、オープンデータ化に取り組むことでの具体的なメリットがイメージできない、そもそも方法が分からないという知識・技術者不足も課題である。
利活用事例の調査を行い、大阪市立図書館では、平成28年度より市立図書館の蔵書統計・利用統計や、デジタルアーカイブの著作権が消滅したデジタル画像情報等のオープンデータ化を進めていることが分かった。ブックカバーや書籍、スウェット・Tシャツ等にオープンデータ画像が活用され、日本経済新聞電子版の記事にも活用されるなどその有用性は高いと考える。
4.おわりに
オープンデータの社会的背景、利活用事例の文献調査が終了し、そこから課題や有用性の有無を考察した。今後は現地で地域文化遺産の撮影を行い、Webページ制作も行う。
参考文献
1)琉球新報.今日のニュース.琉球新報.
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1587009.html
論文
地域資源デジタルアーカイブにおけるオープンデータの有用性の研究
~沖縄の地域文化遺産を例にして~
第1章 緒 言
官庁と民間が保有するデータを流通・活用することで、自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化などを目指す官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)において、国及び地方公共団体はオープンデータに取り組むことを義務付けられている。しかし、デジタル庁の「都道府県別の市区町村オープンデータ取組率」についての調査では、令和4年6月28日時点で沖縄県内市町村の取り組み率は、1位である岐阜県100%に対し26.8%と全国最下位になっている。その調査結果から、沖縄ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)に対する意識の格差やデジタル技術不足の現状があるのではないかと考察した。また、沖縄には琉球王国時代の名残をとどめている特有の地域文化遺産があり、それらを地域活性化に活かしたいと考えた。そこで、本研究では沖縄の地域文化遺産を撮影してデジタルアーカイブを行うとともに、データを活用してWebページ制作を行う。そのWebページを地域文化遺産の保存、地域文化理解、地域活性化を目的としたオープンデータにどのような有用性があるのかを考察する。
第2章 オープンデータとは
1.オープンデータの定義
オープンデータの定義とは、オープンデータを効果的に利用しやすくし、利用者がデータを有効に活用できるようにするために設けられており、平成29年5月30日IT総合戦略本部の官民データ活用推進戦略会議にて決定され、令和3年6月15日に改正されたものである。
その内容はオープンデータの基本事項を示している「オープンデータ基本指針」に、以下のように定義されている。
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと定義する。
① 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
② 機械判読に適したもの
③ 無償で利用できるもの
引用:「オープンデータ基本指針」より抜粋
2.オープンデータの意義・目的
オープンデータは、様々な分野で重要な意義を持っており、公共データの二次利用可能な形での公開、またその活用を促進する意義、いくつかの重要な目的については、以下のように規定されている。
(1)国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化
広範な主体による公共データの活用が進展することで、創意工夫を活かした多様なサービスの迅速かつ効率的な提供、官民の協働による公共サービスの提供や改善が実現し、ニーズや価値観の多様化、技術革新等の環境変化への適切な対応とともに、厳しい財政状況、急速な少子高齢化の進展等の我が国が直面する諸課題の解決に貢献することができる。
(2)行政の高度化・効率化
国や地方公共団体においてデータ活用により得られた情報を根拠として政策や施策の企画及び立案が行われることで(EBPM:Evidence Based Policy Making)、効果的かつ効率的な行政の推進につながる。
(3)透明性・信頼の向上
政策立案等に用いられた公共データが公開されることで、国民は政策等に関して十分な分析、判断を行うことが可能になり、行政の透明性、行政に対する国民の信頼が高まる。
引用:「オープンデータ基本指針」より抜粋
3.オープンデータの必要性
オープンデータの提供と活用は、現代社会において多岐にわたる利点と必要性を有している。
その重要な側面の1つは、オープンデータの意義・目的にもある通り透明性と信頼性の向上だ。政府や組織が行動や決定をデータとして公開することで、市民はこれらのプロセスを理解し、監視することが可能となる。透明性の向上は、行政の公正性や誠実性に対する信頼感を高め、民主主義の基盤を強化することに繋がる。
第2に、オープンデータは市民参加を促進し、民主的な社会の形成に寄与する。市民がデータを利用して政策や提案に参加できる環境が整うことで、より効果的な意思決定が可能となる。これにより、行政が市民のニーズや懸念を正確に把握し、それに応じた施策を打つことが期待できる。
第3に、オープンデータはイノベーションの推進に役立っている。データの自由なアクセスは、新しいアプリケーションやサービス、ビジネスモデルの創造を助長する。研究者や企業が異なるデータセットを組み合わせ、新たな洞察を得ることで、社会に新しい価値をもたらすことが可能となるのだ。
第4に、オープンデータは社会的課題に対する効果的な解決策を見つけ出す手段を提供している。例えば、環境データを活用して持続可能な開発戦略を策定したり、医療データを分析して効果的な治療法を見つけたりすることが可能になる。
以上の、透明性の向上、市民参加の促進、イノベーションの推進、社会的課題への対応といった側面から見ても、オープンデータは社会全体に広がる利益と必要性を有しているといえるだろう。現代社会においてオープンデータの役割はますます不可欠となるのだ。
第3章 地域のオープンデータ
1.大阪市立図書館のオープンデータ
地方自治体が取り組んでいるオープンデータの事例として大阪市立図書館を紹介する。
平成28年度より、大阪市立図書館では「大阪市オープンデータの取り組みに関する指針」や「大阪市ICT戦略」に基づき、活力と魅力ある大阪の実現に資することを目的に、オープンデータ化を進めている。また他機関とも連携し、ビジネスの活性化や学校における教科学習での活用をも視野に入れた利活用推進に取り組むとともに、提供するオープンデータの拡大を図っている。
大阪市立図書館Webサイトでは、公開しているデータのうち、CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0の表示があるデータをオープンデータとして取り扱っている。また、CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスの「CC-BYコンテンツ」「CC-BY-SAコンテンツ」「CC0コンテンツ」について、例文とともにわかりやすく利用条件が記載されている。大阪市立図書館Webサイトで公開されている不正確な情報の混在等による利用者の損害等、一切の行為について大阪市立図書館はいかなる責任も負わないという表記があり、利用者は注意する必要がある。
オープンデータの活動事例を募集し、それらを一覧にまとめて記事として紹介している。大阪市立図書館のオープンデータは、一般の利用者からテレビ局、YouTubeなど幅広い分野で利活用されており、大阪市立図書館オープンデータの有用性は高いと考えられる。
オープンデータ活用事例の募集も同ページで行っている。使用したオープンデータの種類や何に活用したかを入力してフォームを送り、それを大阪市立図書館が記事にして紹介している。
2.地域におけるオープンデータの現状
地方自治体におけるオープンデータに関する取組の実施状況は、平成29年総務省にて行われた「地域におけるICT利活用の現状に関する調査研究」において、2012年度の調査から2016年度調査まで、「取組を推進している団体数」「取組を行っている団体数の比率」ともに増加している。
また、オープンデータに関する取組を推進している自治体では、6割程度が一定以上の成果が上がっているが、約4割では成果が上がっていない。そのため地方自治体にとってオープンデータは、なかなか成果が見えにくい取組であると考えられる。
3.地域におけるオープンデータの課題
オープンデータに関する取組を進める上での課題として、2016年度の調査では「具体的な利用イメージやニーズの明確化」(69.2%)、「提供側の効果・メリットの具体化」(61.5%)が2013年度に比べて増加した。一方、「個人情報等の機微情報の扱いに関する制度的な整備」、「政府におけるオープンデータの具体的な全体方針の整備」は2013年度に比べて10%程度減少している。
この結果から地方公共団体等がオープンデータに関する取組を推進していく上での大きな課題は、具体的にどうオープンデータを利用したらよいのか、オープンデータに取り組む目的や取り組むことで得る提供側のメリットが分からない等、オープンデータに対する知識・理解不足が挙げられる。反対に、権利処理の整備や政府における全体方針の整備、利用者と提供者間の責任分担の整理については、2013年度の調査からオープンデータに取り組む中でそれらの理解が広まり適応されたといえるだろう。
また、このアンケート調査の項目以外にもオープンデータの普及と利用にはさまざまな課題が存在する。これらの課題は、データの公開や利用を妨げる可能性があり、慎重な対応が求められる。
1つに、プライバシーとセキュリティの懸念だ。オープンデータは一般に匿名化や個人情報の削除が行われているが、これが十分に行われない場合、個人のプライバシーが侵害される可能性がある。また、データが悪意ある者の手に渡ることでセキュリティリスクが生じる可能性もある。こういったことから、機密情報やセンシティブなデータの公開には慎重な対応が求められる。
2つめに、データの品質と信頼性だ。オープンデータが利用価値を有するためには、データの品質と信頼性が確保されている必要がある。大阪市立図書館Webサイトにも「公開するオープンデータは、正確な情報となるよう努めていますが、不正確な情報の混在等による利用者の損害等、一切の行為について大阪市立図書館はいかなる責任も負いません。」と記載されている。誤った情報や不正確なデータが公開されると、これを基にした意思決定や研究が誤った方向に進む可能性があるため注意しなければならない。
3つめは、アクセスとデジタル格差だ。オープンデータを利用するためにはアクセスが必要だが、一部の地域や社会階層ではデジタル格差が依然として存在する。データへの平等なアクセスを確保するためには、デジタルリテラシーの向上やアクセス可能なインフラの整備が重要となる。
4つめは、文化的・倫理的な課題だ。特定の文化やコミュニティに関連するデータを公開する際には、文化的な課題や倫理的な配慮が必要となる。特に先住民族に関するデータなど、敏感なトピックに対する配慮が求められる。
これらの課題に対処するためには、データプロバイダや利用者、政府などが協力して適切なガイドラインや標準を策定し、透明性と公正性を確保する取組が求められる。オープンデータの利活用を進める上で、これらの課題に対する適切な対応は必要不可欠といえるだろう。
第4章 沖縄の地域文化遺産デジタルアーカイブ
1.沖縄の地域文化遺産撮影
地域文化遺産は、その地域の歴史・伝統・文化を集約した象徴的な存在であり、そこに属する人々にとって何ものにも代え難い誇りであると同時に、世界の多くの国の人々をも感動させる価値を持っている。実際に文化遺産へ訪れた際には、多国籍の外国人観光客が多いような印象があった。そのような文化遺産を人類共通の貴重な遺産として国際的に手を携えて次世代へ伝えていくことは、お互いの文化を認め、尊重する姿勢にもつながり、安定した国際社会の基礎を成すものといえるだろう。
沖縄の地域文化遺産は、琉球王国時代の名残をとどめているものが多く存在する。その中から世界遺産の城跡に着目し、座喜味城跡、中城城跡、勝連城跡、首里城跡の撮影を行うことにした。撮影に使用したカメラはDJI Osmo Pocketである。撮影は静止画撮影と動画撮影を行った。(首里城跡は、雨天で動画撮影が困難だったため動画撮影を行っていない。)
⑴.座喜味城跡(ざきみじょうあと)
座喜味城跡は、沖縄県中頭郡読谷村にある史跡名勝天然記念物だ。読谷村按司護佐丸によって築かれたと伝えられる座喜味城は、昭和47年5月15日、沖縄の本土復帰と同時に史跡に指定した。しかし、アメリカ軍の基地として使用されていた部分は指定し得なかったので、返還されたのを機に追加指定することになる。
沖縄本島西海岸の南部と中部の境、城原の山の上にあり、沖縄史上第一の築城家として名高い護佐丸(ごさまる)の居城である。中山王(尚巴志)の北山討伐に従った護佐丸が、一時今帰仁城で戦後処理にあたるが、やがてこの城を築き、読谷山一帯の広大な地域を確保し、北方の長浜港での貿易の利を掌握した。
城郭は丘陵の先端部に位置し、本丸の南側二の丸には第1・第2のアーチ型の城門があり、石垣がめぐらされている。どのようにしてアーチ型の城門を石垣で造ったのか気になった。本丸は二の丸より高く、もと5段の石の階段があったが現在はない。護佐丸は数年後に中城城に移ったので、この城はまもなく廃城となった。だが、築城の技術、護佐丸の歴史上の役割からもこの城は重要だといえる。
座喜味城は、戦乱の世だった「三山時代」に活躍し、琉球王国統一後の国の安定に尽力した名将護佐丸(ごさまる)によって築かれた城です。
国王に対抗する勢力を監視する目的でつくられ、1420年頃に完成しています。
規模は小さいですが、城壁や城門の石積みの精巧さや美しさは沖縄の城の中で随一といわれ、当時の石造建築技術の高さを示す貴重な史跡となっています。
⑵.中城城跡(なかぐすくじょうあと)
中城城跡は、沖縄県中頭郡北中城村・中城村にある史跡名勝天然記念物だ。1972年5月15日(日本復帰)の日に、国の史跡に指定された。指定面積は、110,473㎡(約33,440坪)で、その内14,473㎡(約4,300坪)が城壁面積だ。2000年12月2日には、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の1つとして世界遺産にも登録された。
中城城跡は、かつて貿易が行われていた屋宜の港から2㎞離れた標高約160mの高台上
にある。300余もあるとされる沖縄のグスクの中で最も遺構がよく残っていることで知られている城跡だ。東北から西南に一直線に連郭式に築かれた城で、6つの郭で構成されている。城壁は、主に琉球石灰岩の切石で積まれており、自然の岩石と地形的条件を活かした美しい曲線で構成されている。その構築技術の高さは、芸術的といわれ、歴史的にも高い評価を受けている。裏門からはいって、次第に高く、かつ広くなる三の丸・二の丸・本丸は、それぞれ堅牢優美な石塁で囲まれ、石の階段と門で各郭に通じている。とくに三の丸の城壁のように外側から目立つ石組は五角形の石を積みあげ、またアーチ門の回りは特に大きな切石を用い、石塁の角が丸味を帯びているのも特徴であるが、全体としてきわめて堂々たる外観を呈している。城の規模は必ずしも大きくはないが、東南側は自然の絶壁をなし、西北側は10mほど低い位置で外郭の石塁が走り、城の繩張りは日本中世の城に似たものがある。築城は護佐丸といわれるが、護佐丸が座喜味城から中城城に居城を移したのは、尚泰久の妻となった自分の娘の住む首里に近いということのほかに、王権を勝連按司阿麻和利から守るためであった。後に紹介する勝連城は、この城から直線で8キロ、中城湾をはさんで東北方指呼の間にある堅固な城である。つまり、護佐丸と阿麻和利が、それぞれ相手の居所のよく見える位置に築城して対峙したわけである。
しかし1458年、護佐丸は阿麻和利に滅ぼされ、中城城は王の直轄となり、第2尚氏の時代には王子の居城となった。中城城は、近年琉球政府文化財保護委員会の手で一部修理が加えられたが、当初の遺構をほとんどそのまま残し、その技法や構造において沖縄城郭史上いっそうの完成度を見ることのできる城である。とくに丸には門が1つ、二の丸には三の丸からはいる門と本丸に通じる門が2つ設けられ、殿舎の遺構、「いべ」と、三のいうように、あらゆる条件を備えている。しかも、この城こそが、沖縄における第1尚氏による中央集権の確立に重要な役割を果たし、沖縄のいわば中世的な戦乱の最後の築城であったことはきわめて注目すべきところだろう。
1853年に来島したペリー探検隊一行が現地調査を行い、「要塞の資材は、石灰岩であり、その石造建築は、賞賛すべきものであった。石は・・・非常に注意深く刻まれてつなぎ合わされているので、漆喰もセメントも何も用いてないが、この工事の耐久性を損なうようにも思わなかった。」と記し、中城城跡のすばらしさを讃えている。
また、中城城跡から14世紀後半から15世紀前半のものと思われる中国製青磁器が発掘されている。
中城城は、勝連城の勢力を牽制するために、国王の命令によって武将・護佐丸(ごさまる)が移り住んだ城として知られています。
標高167メートルの丘陵地に築かれ、城壁の上からは海を見渡すことができます。
名築城家でもあった護佐丸が増築した城壁と、それ以前の古い城壁が共存していて、築城文化を知る上でも貴重な城です。
⑶.勝連城跡(かつれんじょうあと)
勝連城跡は、沖縄県うるま市勝連南風原にある史跡名勝天然記念物だ。沖縄本島南部の東海岸に突出した与勝半島の付け根に近い台地上に、自然の地形を利用して築かれた一種の山城形式の城である。東南から北西にかけて、現在米軍基地になっている東郭から一段下がって鞍部のような部分の郭、それから珊瑚性石灰岩で石垣をめぐらす三の丸・二の丸・本丸、その先は深い谷となる。昭和40年から3年間、琉球政府文化財保護委員会によって発掘調査され、各郭の構造および他の郭に通ずる門や石段などがかなり明確になったほか、宋・元の青磁や南蛮手の陶器など、中国・南海との貿易資料も発見できた。
この城は、もと一平民であった阿麻和利が茂知附(もちづき)按司に代わって城主となり、勢力が増大して尚泰久の王女をめとった。護佐丸と対決してこれを滅ぼすが、1458年中山王と争い、敗死するまでの居城である。また城下町の形成など、政治史的、社会史的にも重要な城跡だ。
勝連城(かつれんぐすく・かつれんじょう)は、沖縄県うるま市にあったグスク(御城)の城趾である。阿麻和利の城として有名。
概要
城は勝連半島の南の付け根部にある標高60mから100mの丘陵に位置する[1]。南城(ヘーグシク)、中間の内、北城(ニシグシク)で構成されている。北城は石垣で仕切られた一の曲輪、二の曲輪、三の曲輪を備える(曲輪は郭とも言う)。一から三までの曲輪が階段状に連なり、一の曲輪が最も高い。
城の南側に南風原集落(南風原古島遺跡)が広がり、交易のための港を備えていた。城の北側は田地として穀倉地帯であった[1]。
城内の「浜川ガー」(はんがーがー)は、7代目城主濱川按司の女(むすめ)、真鍋樽が身の丈の1つ半の長さもある長髪を洗髪したと伝わる[2]。
構造
二の曲輪には正面約17m、奥行き約14.5mほどの比較的大きな舎殿跡が発見された。等間隔に柱が並び礎石もある社殿であったと推定されている。また城が構築された時代の屋根は板葺きが主流であったが、大和系の瓦も付近から発見されている[3]。
歴史
勝連城は、14世紀初頭に英祖王統2代・大成の五男、勝連按司によって築城されたと考えられているが、いっぽうで12世紀から13世紀頃には既に築城が始まっていたとする説もある。
そして、この城の最後の城主・阿麻和利(10代目勝連按司)は、圧政を敷き酒に溺れていた9代目勝連按司の茂知附按司に対してクーデターを起こし殺害、この地方の按司として成り代わり海外貿易などを推し進めますます力を付けた。阿麻和利は護佐丸・阿麻和利の乱で護佐丸を討ち取ったのち、尚泰久王をも倒そうと琉球の統一を目論んだが、1458年に王府によって滅ぼされた。[4]
城内からは中国、元代の陶磁器(染付)が出土しており、『おもろさうし』からも当時の繁栄をみることができる。民俗学者の柳田国男は、勝連が当時の文化の中心であったことは大和(やまと)の鎌倉のごとしと『おもろさうし』にあるように、浦添・首里・那覇を中心とした浦添文化に対して、系統上異なる勝連文化と言うべきものがあったのではないか、と推測した[5]。
現代
城壁の石は道路工事の石材などとして持ち去られてきたが、現在は復元工事により往時の姿を取り戻しつつある。
1972年(昭和47年)5月15日、沖縄の本土復帰にともない即日、日本国の史跡に指定された。2000年(平成12年)11月首里城跡などとともに、琉球王国のグスク及び関連遺産群としてユネスコの世界遺産(文化遺産)にも登録されている(登録名称は勝連城跡)。登録されたグスク(城)の中では最も築城年代が古いグスクとされている。
2010年(平成22年)、沖縄本島近海地震で城壁の一部が崩落する被害を受けた[6]。
2016年、2013年の遺構調査で発掘された10枚の金属製品の中に14世紀から15世紀の地層から3世紀から4世紀頃に製造されたローマ帝国のコインが4点、17世紀の地層から17世紀頃に製造されたオスマン帝国の貨幣が1点が確認された[7]。14世紀から15世紀にかけての海上交易を通じて東アジア経由で流入したと考えられ[8]、また、日本国内でローマ、オスマン帝国の貨幣が発見されたのは初めてのこと[9]。
2017年(平成29年)4月6日、続日本100名城(200番)に選定された。
歴代城主
勝連城は、14世紀始め頃に英祖王統の第二代国王・大成の五男、勝連按司によって築城され、阿麻和利に到るまで十代の城主により統治されたと考えられている。
勝連按司二世の娘は察度に嫁ぎ、察度が西威を倒して中山王国を建てると勝連も中山との結びつきを強め、中興し栄えたと伝わる。
初代 勝連按司一世(英祖王統・第二代王大成の五男)
二代 勝連按司二世(一世の世子、娘・眞鍋樽は察度王の妃)
三代 勝連按司三世(二世の世子)
四代 勝連按司四世(三世の世子)
五代 勝連按司五世(勝連の伊波按司に敗れ戦死)
六代 勝連の伊覇按司(伊覇按司一世の六男、姉妹の眞鍋金は尚巴志の妃。勝連按司五世の家臣・浜川按司に敗れ戦死)
七代 浜川按司一世(前領主・勝連按司五世の家臣)
八代 浜川按司二世(一世の世子)
九代 茂知附按司(家臣の阿麻和利に敗れ戦死)
十代 阿麻和利(越来賢雄率いる尚泰久王の王府軍に敗れ戦死、廃城)
観光
この城跡は山を利用して造られている天険の要害であり、城跡入口から急勾配がつづくため、軽装でも良いが足回りには注意が必要。
真鍋樽伝説
前述7代目城主濱川按司の女(むすめ)真鍋樽(マナンダルー、マランラルー)は絶世の美女だったと言う伝承が琉球各地にあり、例として具志頭間切(八重瀬町具志頭)の若者、白川桃樽金(シラカワトゥバルタルガニー)が真鍋樽に恋をし結婚を申し込むが結ばれず、二人は恋焦がれるうちに病死してしまい、葬送の行列が北中城で会合したので一緒に埋葬されたと言う伝承がある(「熱田マーシリー」)[10]。また、南山他魯毎の子、樽真佐(タルマサ)の孫に四郎樽金(シルタルガニー)がいて、彼の親はもてなかったが彼は真鍋樽と結婚したと言う。先述の白川桃樽金は謎かけをして解けない内に死んでしまい、四郎樽金は謎かけを解いて結ばれたと言う伝承である。
⑷.首里城跡(しゅりじょうあと)
首里城跡は、沖縄県那覇市首里にある史跡にある名勝天然記念物だ。首里城跡は、琉球王国の栄華を物語る世界遺産であり、沖縄の歴史・文化を象徴する城跡である。1429年から1879年までの450年間にわたり存在した王政の国である琉球王国では、中国や日本、東南アジア諸国との盛んな交易により琉球独自の文化が育まれていた。その王国の政治・外交・文化の中心として栄華を誇ったのが首里城なのである。
首里城は14世紀頃に創建されたといわれ、中国や日本の文化も混合する琉球独特の城で、随所に中国や日本の建築文化の影響を受けている琉球王国最大の木造建築物だった。小高い丘の上に立地し、曲線を描く城壁で取り囲まれ、その中に多くの施設が建てられている。いくつもの広場を持ち、また信仰上の聖地も存在する。これらの特徴は、首里城に限られたものではなく、グスクと呼ばれる沖縄の城に共通する特徴である。首里城は内郭(内側城郭)と外郭(外側城郭)に大きく分けられ、内郭は15世紀初期に、外郭は16世紀中期に完成している。正殿をはじめとする城内の各施設は東西の軸線に沿って配置されており、西を正面としている。西を正面とする点は首里城の持つ特徴の一つである。
首里城は国王とその家族が居住する「王宮」であると同時に、王国統治の行政機関「首里王府」の本部でもあった。また、各地に配置された神女(しんじょ)たちを通じて、王国祭祀(さいし)を運営する宗教上のネットワークの拠点でもあった。さらに、首里城とその周辺では芸能・音楽が盛んに演じられ、美術・工芸の専門家が数多く活躍していた。首里城は文化芸術の中心でもあったのである。
1879年(明治12)の春、首里城から国王が追放され「沖縄県」となった後、首里城は日本軍の駐屯地、各種の学校等に使われた。1930年代には大規模な修理が行われたが、1945年にアメリカ軍の攻撃により全焼した。戦後、跡地は琉球大学のキャンパスとなったが、大学移転後に復元事業が推進され現在に及んでいる。
そして、2000年12月、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」が日本で11番目の世界遺産として文化遺産に登録された。世界遺産に登録されたグスクの中でもひときわ目立っているのが首里城跡だ。また、尚巴志が琉球を統一した頃には、すでに歴史の表舞台に登場していたという。
2019年10月31日の火災で、正殿を含む9つの施設が焼損した。現在は、国内外の多くの人々からの支援により、「見せる復興」をテーマに一歩ずつ着実に復興へ向け歩みを進めている首里城。復元工事は正殿から着手しており、正殿の建っていた御庭には、木材を加工する「木材倉庫」、原寸大の図面を描く「原寸場」、建設中の正殿を雨風や埃から守る「素屋根」が建てられ、併設された見学エリアからガラス越しに復元工事の様子を見ることができる。
今から400~500年前の首里城は、板葺き屋根だった。1660年に火事になり、それから
再建した首里城は、瓦葺きになった。しかし瓦の色は、発掘調査によると、赤ではなく灰色の瓦が出たそうだ。赤瓦になったのは、また火事で首里城が焼けた後、1715年に再建した首里城からだ。なぜ灰色から赤瓦に変わったかと言うと、その頃の琉球で起こった人口増加問題にあったようである。400年前の琉球の人口は約10万人。それから100年後、人口は20万人近くになり、今も昔も、生活に欠かせない火は、薪を燃料にしていたので、人が増えると薪が無くなる。灰色の瓦だと高い温度で焼かないといけないが、赤瓦だと低い温度でも焼けるので、薪を使う量を節約できるのだ。
首里城の瓦を赤くして資材を節約した後、琉球王国では、山原(やんばる)に植林して、各村の山を管理し、守ろうとした。当時の琉球の人々は、すでに自然の大切さに気付いていたのだ。その証拠の一つが、首里城の赤瓦とも言えるのではないだろうか。瓦屋根は士族の家の他、陶器を焼く窯(かま)元、酒屋等の火を使う職業の家屋などに制限されていた。このことから、赤瓦は省エネ対策のひとつだったと考えられる。
平成の復元で首里城の赤瓦が蘇り、さらに県内の公共建築物や住宅・ホテル等でも赤瓦が見かけられるようになってきている。首里城正殿の赤瓦は、浸水防止等のための低吸収や割れにくいことが求められる。なお、平成の復元で原料とした沖縄本島北部の粘土は、現在入手できない状況である。
平成の復元以降、県内に継承されている技術や材料をできるだけ活用するため、令和の復元では沖縄本島内での材料調査から取り組み、試作瓦の作成や瓦をプレス加工するための金型の検討を行っている。
また、沖縄県では、首里城復興を応援するため、首里城のデザインを取り入れた「首里城図柄入りナンバープレート」の普及推進に取り組んでいる。このプレートを付けることで首里城復興を応援することができる。
首里城正殿の唐破風正面と屋根瓦の両端に大きな龍の棟飾が取り付けられている。これは、「龍頭棟飾」といい、首里王府の史書である「球陽」によると1682年の正殿修理の際に平田典通(ひらたてんつう)という人物が五彩の釉薬を全島に探し求め、焼物で作り正殿に飾ったと記されている。この平田典通は、それまで琉球では焼くことが出来なかった釉薬を使用する方法を中国で学び次々と焼物の歴史に残る功績を上げた琉球の名工だった。この釉薬を使った焼物技法は、現在では「上焼」と呼ばれ、平田典通の弟子たちによって伝え受け継がれていったと考えられている。
首里城(しゅりじょう、沖縄方言: スイグシク[1])は、琉球王国中山首里(現在の沖縄県那覇市)にあり、かつて海外貿易の拠点だった那覇港を見下ろす丘陵地にあったグスク(御城)の城趾である。現在は国営沖縄記念公園の首里城地区(通称・首里城公園)として都市公園になっている。
第二次世界大戦中に焼失後、1992年に柱・壁・瓦など朱色を基調として再建された[2][3][4][5]。しかし、2019年10月31日に正殿など主要7棟が火災で焼失し[6]、その後復興作業が進められている[7]。
概要
首里城の空中写真(2010年)
国土交通省 国土地理院 地図・空中写真閲覧サービスの空中写真を基に作成。
城壁
城内より市街を望む
琉球王朝の王城で、沖縄県内最大規模の城であった。戦前は沖縄神社社殿としての正殿などが旧国宝に指定されていたが[8]、1945年(昭和20年)の沖縄戦と戦後の琉球大学建設によりほぼ完全に破壊され、わずかに城壁や建物の基礎などの一部が残っている状態だった。
1980年代前半の琉球大学の西原町への移転にともない、本格的な復元は1980年代末から行われ、1992年(平成4年)に、正殿などが朱色を基調とした形で完成した[2][3][4]。
1993年(平成5年)に放送されたNHK大河ドラマ「琉球の風」の舞台になった。1999年(平成11年)には都市景観100選を受賞。その後2000年(平成12年)12月、首里城跡(しゅりじょうあと)として「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の名称で世界遺産に登録されたが、復元された建物や城壁は世界遺産に含まれていない。
2019年10月31日未明の火災により、正殿を始めとする多くの復元建築と収蔵・展示されていた工芸品が焼失または焼損した。
周辺には同じく世界遺産に登録された玉陵(たまうどぅん)、園比屋武御嶽(そのひゃんうたき)石門のほか、第二尚氏の菩提寺である円覚寺(えんかくじ)跡、国学孔子廟跡、舟遊びの行われた池である龍潭、弁財天堂(べざいてんどう、天女橋)などの文化財がある。
2.Webページ制作
現地で撮影した映像データを、岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所の「地域資源デジタルアーカイブにおけるオープンデータの有用性の研究」ページに掲載した。
城跡の概要、歴史や建てられた目的等の情報、またGoogleマップでその所在地をわかりやすく記載した。座喜味城跡、中城城跡、勝連城跡の3つは動画も添付した。そして、このWebページをオープンデータとして公開した。
第5章 考 察
ここまで、オープンデータの必要性や地方自治体のオープンデータの現状と課題等について考えてきた。それをふまえて地域文化遺産の保存、地域文化理解、地域活性化を目的としたオープンデータにどのような有用性があるのかを考察する。
大阪市立図書館は、活力と魅力ある大阪の実現に資することを目的に、オープンデータの取組を進めている。結果、書籍やブックカバー、新聞の電子版の記事といった一般の利用者からテレビ局、YouTubeなど幅広い分野で利活用されており、オープンデータとしての高い有用性を持っていると考えられる。
沖縄の地域文化遺産については、その独自の文化、歴史から世界中から人々が訪れている観光スポットの一つになっている。しかし、2019年に起きた首里城の火災では、正殿を含む9つの施設が焼損してしまった。そのような事態で地域文化遺産が失われてしまうことがあったときに、復興のために重要なのは「記録」だろうと、実際に現地で撮影しWebページを作成したことで理解できた。地域文化遺産の保存の観点からみて、データとして記録・保管・管理することでより深く文化遺産について理解でき、復興のための情報も多く残すことができると考えられる。また、オープンデータとして公開することで、現地に行くことができない場合でも地域文化遺産への理解を深めることができることがわかった。
第6章 結 言
本研究を通して、地方公共団体のオープンデータ化の取組率は増加し、成果も上がっている一方で、取り組むことで見えてくる課題もあるとわかった。また、大阪市立図書館のように上手くオープンデータ化を進めている地域もあれば、沖縄の市町村のようにあまりオープンデータ化に取り組むことができていない地域もあるため、オープンデータ化の課題でもあるように適切なガイドラインや標準の策定、その普及が重要になる。
本研究では、沖縄の世界遺産の城跡のオープンデータ化を行った。このような地域文化遺産のオープンデータ化を進めていくことで、その地域文化遺産の保存や地域文化への理解、地域活性化につながり、社会全体に広がる。
このことはオープンデータ化が必要であるといえる1つの理由になるだろう。
参考文献
本論文の作成にあたり、終始適切な助言と丁寧な指導をして下さった久世均先生に深く感謝します。また、調査にあたり多くの方にご協力をいただきましたことに、感謝の念を示します。今回の卒業論文では多くのご支援・ご協力のおかげで自分の納得のいく結論を出すことができました。卒業論文制作にあたり関係して下さった全ての方々に、厚く御礼を申し上げ、感謝の意をしめします。
謝 辞
岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究室: 教育リソース
(2023年1月22日アクセス)
https://digitalarchiveproject.jp/category/text/
文化遺産オンライン:首里城跡(2023年1月22日アクセス)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/164241
大阪市立図書館ホームページ:オープンデータについて(2023年3月1日アクセス)
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=1633
総務省:平成29年版情報通信白書:オープンデータに関する取り組み状況と課題
(2023年3月2日アクセス)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc122210.html
首里城公園(2023年3月10日アクセス)
https://oki-park.jp/shurijo/
デジタル庁:オープンデータ(2023年5月30日アクセス)
https://www.digital.go.jp/resources/open_data
大阪市立図書館:オープンデータ利活用事例の紹介(2023年6月5日アクセス)
https://www.oml.city.osaka.lg.jp/?page_id=1636
文化遺産オンライン:座喜味城跡(2023年6月13日アクセス)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/173575
文化遺産オンライン:中城城跡(2023年6月28日アクセス)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/217969
文化遺産オンライン:勝連城跡(2023年10月3日アクセス)
https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/140047
沖縄地域文化資源デジタルアーカイブ(2023年12月10日アクセス)
https://digitalarchiveproject.jp/category/database/okinawa/
沖縄県オープンデータカタログサイト(2024年1月2日アクセス)
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/joho/kikaku/opendata/opendata.html
沖縄市オープンデータ(2023年12月19日アクセス)
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k010-004/shiseijouhou/opnedata/index.html
那覇市公式ホームページ:オープンデータ(2023年10月25日アクセス)
https://www.city.naha.okinawa.jp/online/opendata/
論文資料
デジタルアーカイブ研究所資料集(飛騨高山編)
はじめに
平成29年度に文部科学省の私立大学研究ブランディング事業の「地域資源デジタルアーカイブによる知の拠点形成のための基盤整備事業」で採択され、3年間にわたりこれまでに本学独自で育んできたデジタルアーカイブ研究を活用し、地域資源のデジタルアーカイブ化とその展開によって、伝統文化産業の活性化などの地域課題の実践的な解決や新しい文化を創造できる人材育成を行い、地域の知の拠点となる大学を目指し事業を展開してきた。
その中でも「飛騨高山の匠の技デジタルアーカイブ」は、以下の点に注力して研究を進めてきた。
①伝統文化産業(飛騨春慶・一位一刀彫等)を多視点でデジタルアーカイブし、歴史的な視点を総合的にまとめ、匠の “こころ”をオーラルヒストリー等により「知の増殖型サイクル」を構成し、これらの一部を海外へ発信することにより伝統文化産業の振興を図る。
②伝統文化産業における匠の技とその歴史的な背景をまとめてデジタルアーカイブ化することで、伝統文化産業の理解と継承が容易になる。さらに、継承の過程で生まれた新しい知見を「知的創造サイクル」で取り込み、その利活用によって地域社会の振興を支援できる。
③フィールドにおける効果検証をするためのデジタルアーカイブ研究として捉え、解の見えない地域課題の解決をするための地域資源デジタルアーカイブとそのメソッドを確立する。
これらにより、地域の知が適切に循環・増殖することで新たな価値の創造と、これらを実践できる高度な専門的な知識を持つ人材の養成による雇用の創出を促進し、その結果として「知的創造サイクル」としてデジタルアーカイブの効果が認められ、さらにデジタルアーカイブの新たな展開が期待できる。また、これにより大学は地域に開かれた「知の拠点」となりうる。
この「デジタルアーカイブ研究所資料集(飛騨高山匠の技編)」は、本学が展開しているデジタルアーカイブの最新成果であり、これらの研究の拠点となるデジタルアーカイブ研究所では、大学が大学としてのアイデンティティを確立するためにも、「知」の拠点としての地域資源デジタルアーカイブを含めた総合的な大学デジタルアーカイブを構築することを支援している。今後は継続してデジタルアーカイブ研究に取り組むとともに新たな養成カリキュラムを構築することが本学として社会的な責務と捉えている。
2023年10月 デジタルアーカイブ研究所長 久世 均
岐阜女子大学 デジタルアーカイブ研究所
資料集(飛騨高山匠の技編)
発行年月日 2023年10月
発 行 所 岐阜女子大学デジタルアーカイブ研究所
〒500-8813
岐阜県岐阜市明徳町10番地 杉山ビル4階
印 刷 所 有限会社 青山印刷
高山市長との協議
1.日程 11月15日(水)9:00~14:00
2.高山市長との協議
3.参加者
一般財団法人 飛騨高山大学連携センター
①六角センター長
②木岡副センター長
岐阜女子大学
③松川学長
④久世 4名
4.内容
1.岐阜県私立大学地方創生推進事業について
2.飛騨高山匠の技デジタルアーカイブ資料集
(上)(中)(下)(左甚五郎編)
3.資料の活用について(協議)
4.その他
資料