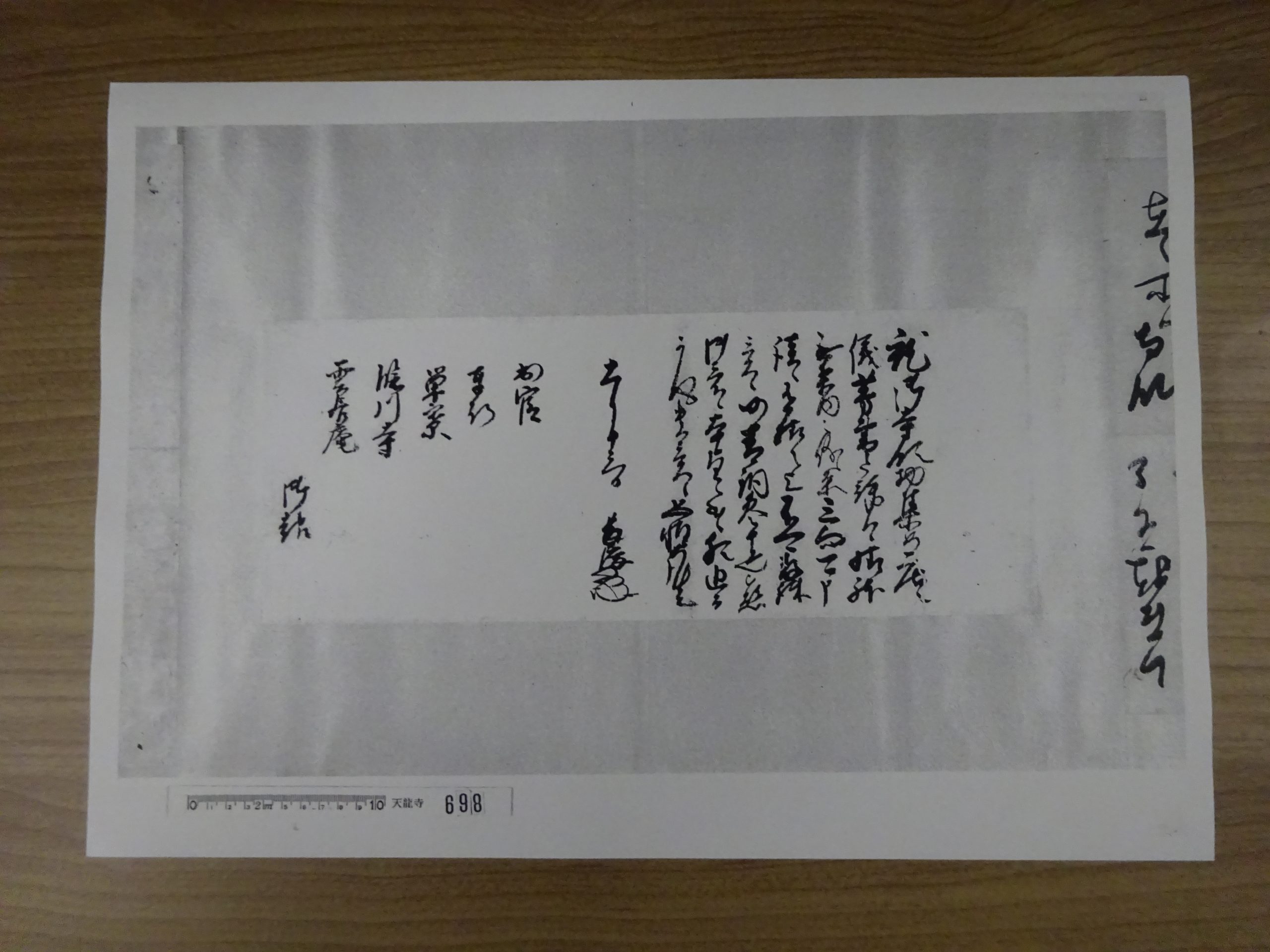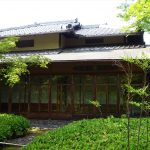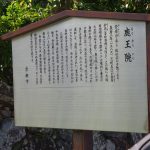【授業】人権教育
第1講 ドキュメント「青い目・茶色い目」を見て、差別の仕組みについて考える。
1.何を学ぶか
ドキュメント「青い目・茶色い目」を見て、差別の仕組みについて考える。
2.学習到達目標
① ドキュメント「青い目・茶色い目」を見て、差別の仕組みについて考え、このことが”いじめ”のシステムについて考察する。
② ”いじめ”が周りの大人によって生じていることについて説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
人権教育:レポート(第1回)
人権教育:レポート(第1回) (PDF)
5.資料
第2講 創造性を高めるためについて考える。
1.何を学ぶか
いじめをなくすためには、創造性を高めることが必要と考え、創造性を高めることといじめの関係性について考察する。
2.学習到達目標
① 創造性を高めるためには、内発的動機付けとの関係を説明できる。
② いじめと創造性に関することについて説明できる。
③ ダニエル・ピンクの「やる気に関する驚きの科学」を見て、創造性を高めるためには、何が必要かについて説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
人権教育:レポート(第2回)
人権教育:レポート(第2回)(PDF)
5.参考文献
第3講 いじめのメカニズムといじめ対策のポイントは何か考える?
1.何を学ぶか
いじめのメカニズムといじめ対策のポイントは何か考える?
2.学習到達目標
① いじめのメカニズムについて説明できる。
② いじめ対策のポイントについて説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
人権教育:レポート(第3回)
人権教育:レポート(第3回) (PDF)
5.参考文献
第4講 ネット社会の人権とモラルについて考える。
1.何を学ぶか
ネット社会の人権とモラルについて考える。
2.学習到達目標
① ネット社会の人権とモラル啓発ビデオを見て、ネット社会における人権問題について説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
人権教育:レポート(第4回)
人権教育:レポート(第4回) (PDF)
第5講 著作権法の目的について深く考える。
1.何を学ぶか
著作権について理解し、著作権法の目的について深く考える。
2.学習到達目標
① 著作権法についての説明を聞いたうえで、著作権法の目的について説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
人権教育:レポート(第5回)
人権教育:レポート(第5回) (PDF)
5.プレゼン資料
5.参考文献
第6講 能力主義は正義かについて考える。
1.何を学ぶか
能力主義は正義かについて考える。
2.学習到達目標
① 能力主義は正義かについて自分の考えを説明できる。
3.動画資料
VIDEO
4.課題
能力主義は正義か?という議論について考えたことを記述しなさい。
5.参考文献
実力も運のうち 能力主義は正義か? マイケル・サンデル (著), 本田 由紀 (その他), 鬼澤 忍 (翻訳)
第7講 防災と人権
1.何を学ぶか
防災と人権は、それぞれ重要な要素であり、密接に関連しています。防災は、災害に対する備えや対応を意味します。これには、災害が発生した際の人々の安全と健康を守るための施策や計画が含まれます。地震、洪水、台風などの自然災害や、人為的な災害に対する対策が含まれます。防災活動は、早期警戒システムの設置、避難計画の策定、救助活動の実施など、様々な段階で行われます。1.アクセスと公平性: 防災施策や支援は、全ての人々が平等にアクセスできるように設計されるべきです。差別や排除を防ぎ、すべての人々が適切な支援を受けられるようにすることが重要です。2.情報と参加: 防災計画や対策において、情報の透明性と参加の機会を提供することが、人権を尊重する重要な要素です。地域の人々が情報を得て、意見を述べることができるようにすることが必要です。3.保護と支援: 災害発生時には、特に脆弱な立場にある人々の保護と支援が重要です。人権を尊重した対応が求められます。
2.講座の内容 ① 過去の風水害(地域で発生した風水害・伊勢湾台風など)
3.学習到達目標
① 防災と人権について説明できる。
4.課題
① 防災と人権について関係性を説明しなさい。
人権教育:レポート(第7回)
人権教育:レポート(第7回) (PDF)