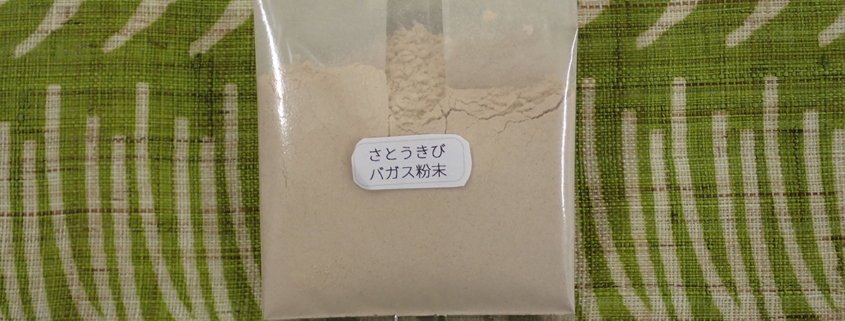沖縄のサトウキビ 黒糖
黒糖の定義について、消費者庁が発信している「食品表示に関するQ&A(食品表示基準に関する解釈通知)」には、「サトウキビのしぼり汁に中和・沈殿などの方法で不純物を除去し、煮沸によって濃縮した後、糖蜜分の分離などの加工を行わずに冷却して製造した砂糖で、固形または粉末状のもの」と記載されている(『加工黒糖等に関するガイドライン-第二条-(1)』より)。
サトウキビは沖縄方言で「ウージ」と呼ばれ、沖縄を代表する特産品の一つである黒糖は、郷土料理や菓子、土産品など幅広く用いられ、古くから沖縄の慣習や生活文化に深く根付いている。味わいはカラメルのようなコクと甘みが特徴で、場合によっては渋みや苦味も感じられる複雑な味わいを持つ。菓子や料理の甘味料として使われるだけでなく、コーヒーや紅茶の砂糖として、あるいはそのまま食べて楽しむこともできる。
近年では、部活の休憩時間に黒糖が配られ、ミネラル補給として活用されることもあり、子どもたちにも身近な存在として親しまれていることから、沖縄の文化や生活に深く根付いた食品であることがうかがえる。
現在は、個包装のものもあり、シークヮーサー味やショウガ味などのバリエーションが豊富になってきている。
資料(メタデータ)
メタデータ_黒糖
沖縄のサトウキビ サーター車
サーター車(砂糖車)とはサトウキビを搾るための圧搾装置のことで、沖縄では約400年前から活用されており、沖縄の製糖業の歴史を語るうえではなくてはならない存在である。
その構造は、3本のローラーを歯車で回転させ、回転するローラーの間にサトウキビの茎を差し込んで圧迫粉砕し、サトウキビ汁を絞り出す。回転させる動力は牛や馬などで心棒をまわして歯車を動かしていた。
この製糖法は1623年、首里王府の役人である儀間真常(1557-1644)が中国から学び伝えられたものといわれている。自家で砂糖製造を始めたことから黒糖製造が広がった。当時、使用されたのは木製の二本式砂糖車だったが、時代と共に石製、鉄製と改良された。
現在では使われておらず、琉球村などで昔の生活を伝える展示として展示されている。
資料(メタデータ)
メタデータ_サーター車
沖縄の施設 東南植物楽園
沖縄県沖縄市知花に所在する日本の植物園、博物館相当施設。1968年に開園し、2013年7月にリニューアルオープンした。
世界中から集められた亜熱帯や熱帯の植物が沖縄の環境を活かし、自然に近い姿で一年中見ることができ、約1300種類もの植物が楽しめる。また、沖縄特有の薬草や有用植物、サトウキビなども栽培・展示されており、その実際を間近で観察することができ、地域の植物資源の保護・学習・研究の場としての役割も担っている。
そのほか、釣りや雑貨創作、動物とのふれあい等ができる体験イベント、音声ガイドで園内を案内する周遊バス、地元食材を使用したメニューを提供するレストラン・カフェ、冬季限定イベントのイルミネーションなど、展示以外の行事にも力が入れており、観光客から地元民まで毎年多くの方が訪れている。
また、2025年11月11日(火)にて開催された(一社)夜景観光コンベンション・ビューローが主催する「International Illumination Award2025(インターナショナルイルミネーションアワード)」イルミネーションイベント部門優秀SDGs賞において、全国第1位を受賞した。
資料(メタデータ)
メタデータ_東南植物楽園
沖縄のサトウキビ 製糖記念小公園
製糖記念小公園は、平成23年9月13日、新中糖産業㈱(旧 中部製糖㈱)の創立50周年記念事業として西原町のサンエー西原シティ前の歩道に設置された。
サンエー西原シティは1993年に中部製糖社(現・新中糖産業)が製糖事業から撤退後、1998年まで翔南製糖が製糖操業を行っていた工場跡地である。製糖記念小公園は、西原町は糖業とゆかりの深い町であるという歴史的足跡を現在に伝える施設であり、設置されている複数の説明板から糖業やその移り変わりについて知ることができる。
資料(メタデータ)
メタデータ_製糖記念小公園
沖縄のサトウキビ 有用植物としてのサトウキビ
有用植物とは、私たち人間の生活とさまざまな面で深く関わっている植物のことである。サトウキビもその一つで、琉球王朝時代から現在に至るまで、沖縄の人々の生活と密接な関係をもってきた農作物である。
サトウキビは、琉球王朝時代に儀間真常(1557~1644)によって中国・福建省から栽培方法と製糖技術が伝えられた。これにより沖縄では砂糖生産が広まり、サトウキビは重要な作物として定着していった。
現在では、沖縄県の全耕地面積の約5割がサトウキビの栽培に使われており、県内農家の約7割がその栽培に従事している(令和4年度 沖縄県農林水産部調査)。サトウキビは強風や日照りに強く、高温多湿を好むため、台風の多い沖縄の気候にも適している。栽培から製糖、加工、販売に至るまで多くの雇用を生み出し、地域経済を支える主要な農産物となっている。
サトウキビは沖縄方言で「ウージ」と呼ばれ、沖縄の特産品である黒糖の原料としても知られている。黒糖は郷土料理や菓子、土産品など幅広く利用され、古くから沖縄の慣習や生活文化に深く根付いている。
資料(メタデータ)
メタデータ_サトウキビ
沖縄のサトウキビ バガス
バガスとは、サトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすのことで、サトウキビ全体の約25%がバガスとして得られる。主な成分はセルロース、ヘミセルロース、リグニンであり、水分を約45%含んでいる。見た目は茶色がかった繊維質で、木材パルプに近い性質を持つ。
バガスは食物繊維を豊富に含んでいるものの、繊維構造が非常に強固で食感が悪いため、食品としての利用はこれまでほとんど行われてこなかった。しかし近年では、廃棄物として処理されてきたバガスの資源価値が見直され、環境に配慮した素材として注目されている。
主な用途として、製糖工場ではバガスがボイラー燃料として利用され、製糖工程に必要なエネルギーをまかなう役割を果たしている。また、紙製品の原料としても活用が進んでおり、無印良品ではバガスと竹パルプを混ぜて作った紙皿が販売されるなど、環境負荷の低減を意識した製品開発が行われている。
さらに、沖縄県南部ではバガスを活用したクッキーやカップケーキが製造・販売されており、これまで活用されにくかった資源を新たな形で生かす取り組みも見られる。そのほか、建材や断熱材、堆肥、飼料原料として生産者に提供されるなど、バガスは多様な分野で再利用されている。
資料(メタデータ)
メタデータ_バガス
沖縄のサトウキビ ウージ染め
ウージ染めとは、サトウキビを利用した染め物、織物のこと。「うーじ」とは、沖縄の方言でサトウキビを指す。
染色にはサトウキビの葉と穂の部分を用い、刈り取ったサトウキビの葉を細かく切り、2~3時間かけて煮出し、こす作業を2回繰り返して染液を取り出す。その後の染め方には2通りの方法があり、先に糸を染めた後に織り上げる「先染め」と、布を絞り等で後から染めていく「後染め」がある。
染液につける時間や、 葉を刈り取る季節によっても少しずつ色が変化し、若草色や萌葱色などのグリーン系から、黄金色などの落ち着いたイエロー系など、葉の青々とした夏の時期には黄色が強くなり冬には渋みがかった色に染まるほか、12月中旬から2月頃にかけて咲くさとうきびの花を使った、「花穂染め」と言われるピンク色のウージ染めもあり、様々な色を楽しむことができる。
資料(メタデータ)
メタデータ_ウージ染め
与那原の施設 与那原大綱曳資料館
与那原大綱曳は、那覇・糸満の大綱引きとあわせて「沖縄三大綱曳」といわれており、与那原大綱曳資料館は与那原町の教育・学術および文化の継承・発展に寄与するために設置された。現在の施設は2022年4月にリニューアルした資料館である。
「綱曳」は沖縄県内各地で広範に分布している習俗の1つで、地域的特色があり、地域の人々を結集するうえで大切な役割を果たしている。しかし、近年の生活様式等の変化とともに人々の価値観も多様化し、地域の綱曳もそれぞれ変容してきている。また地域によっては継続が困難となり途絶えたものも少なくない。そのような中、若い世代の住民が増えてきている与那原町ではあるが、与那原大綱曳は時代にともに変容しながらも現代へと受け継がれてきている。与那原大綱曳資料館は「ツナカン」ともよばれ、町民に親しまれている。
資料(メタデータ)
与那原の施設_与那原大綱曳資料館
与那原の文化財 与那原町の石獅子
与那原町の石獅子は7つとも異なる姿・形をしている。特に火の獅子(上与那原区)と中島の石獅子②はユニークである。
火の石獅子は大里村の石獅子に対抗して設置された石獅子という話が残っている。昔、火事が良く起きていた大里村では、火事を返すために与那原町に頭を向けた石獅子を設置していた。そのことが原因で与那原での火事が頻発するようになったと考えた与那原の村人は、大里村に頭を向けた石獅子を設置することで村を火事から守ろうとした。
中島の石獅子は材木ストリートの先、住宅街にひっそりと存在している。が、この石獅子の顔の右半分は木がめり込んでいるというほかに石獅子にはないような唯一無二の個性がある。そういった特異さも含めて地域の人々から愛されているからこそ、今もなお残されているのかもしれない。
国道331号線沿いに鎮座している新島の石獅子①は、拝所として崇められているわけでも木がめり込んでいるわけでもないが、その胸元には大きなリボンがかけられており、かわいらしさを感じさせると同時に地元住民に愛されているという他ならない証拠のようなものであると思わせられる。
このように、石獅子は先人がかつて与那原町を守ろうとしてきた証拠であり、村人の地域に対する誇りを感じるような歴史を持っている。その歴史に触れることは現代の与那原町民のシティプライドにもつながると考えられる。また、これまで7体もの石獅子が大事に守られてきたという事実がシビックプライドであり、その石獅子の存在が広まることがより強いシビックプライドにつながる。
資料(メタデータ)
与那原の文化財_石獅子/与那原の文化材_中島区の石獅子
与那原の歴史 御殿山
御殿(ウドゥン)とは、王子・按司の家、またはその人を指す名称のことで、一般に王族の家屋建物を意味する語である。
御殿山(ウドゥンヤマ)は、山原(金武)から首里の御殿に納めるための木材を一時的に置いておくための場所であったことから由来する地名である。沖縄では昔、山原(金武)から木材や薪炭を運び、南部からは米・麦・豆といった日用雑貨を運んで貿易を行っていた。与那原はその物資を受け取る港として栄えていた。山原から運ばれてきた木材のうち、御殿に差し出す木はここに置くようにさだめられたため、実際には山はないが「御殿山」と称したというのがいい伝えである。
なお、御殿山は1999(平成11)年4月21日に町指定文化財として登録されている。
資料(メタデータ)
与那原町の歴史_御殿山
与那原の産業 AGARIHAMA BREWERY
与那原町にあるクラフトビール製造所のアガリハマブルワリー(クラフトビール専門店)は、株式会社YUKAZEの新規事業で2023年にオープンさせた場所である。創業約3年と始めたばかりで、「ないものは、創ればいい」というYUKAZEの理念のもと、一からビールについて勉強し、工場長とその仲間たちで作り上げたクラフトビールである。
与那原町の新たな県産品として発信中である。試行錯誤しながら作っており、ジャパン・グレートビア・アワーズ(JGBA)という日本地ビール協会(クラフトビア・アソシエーション)が主催する、日本国内で製造されたビールに特化した日本最大級の品評会・審査会では、2024年に金賞と銀賞、2025年にも銅賞を受賞している、成長中のクラフトビール専門店である。
クラフトビールは普通のビールと違い、苦手に思う方もいるが、AGARIHAMABREWERYのクラフトビールは、すっきりした味わいで、初心者の方でも飲みやすいように作られている。
この味わいを生み出すために、工場長の方は日々努力されている。主な原料は4つだけだが、その4つにも種類がありその組み合わせで味が異なっていたり、製造中の温度を1℃ずつ変えて味を確認しながら絶妙な調整をしながら作っている。試行錯誤に日々で年々美味しくなっていっているし、自身を持って提供している商品である。