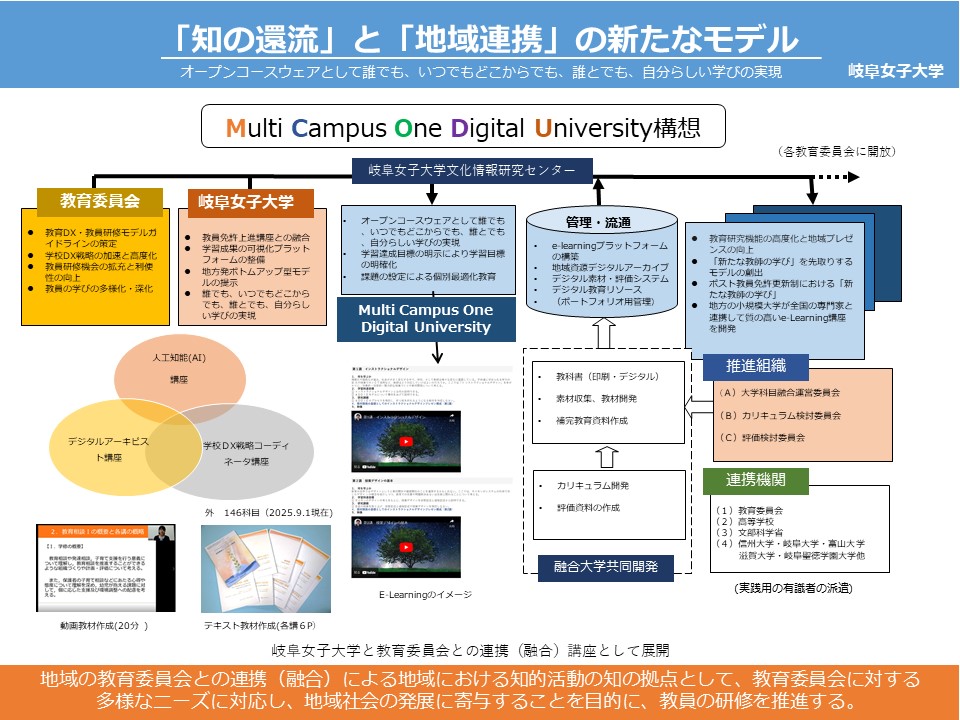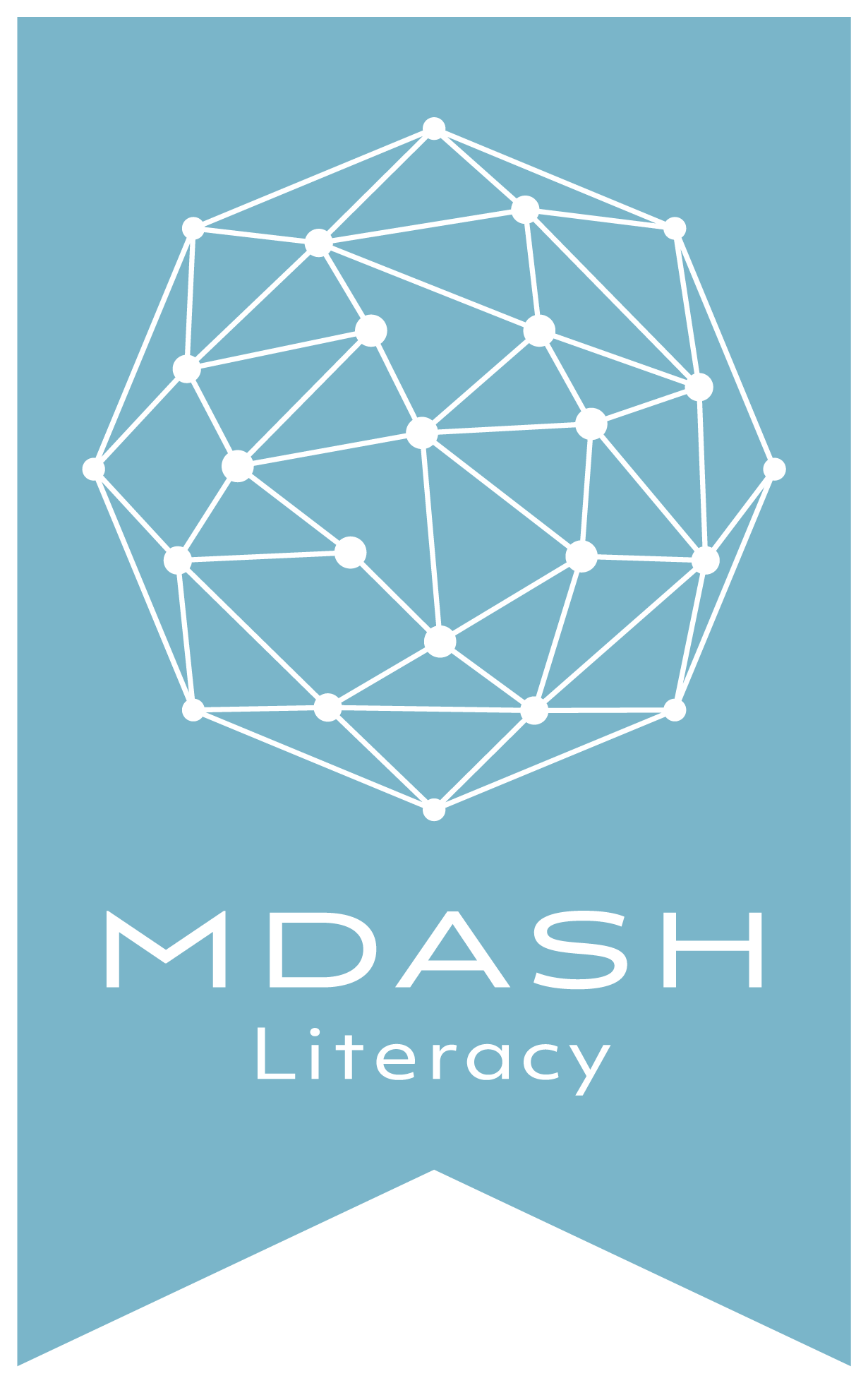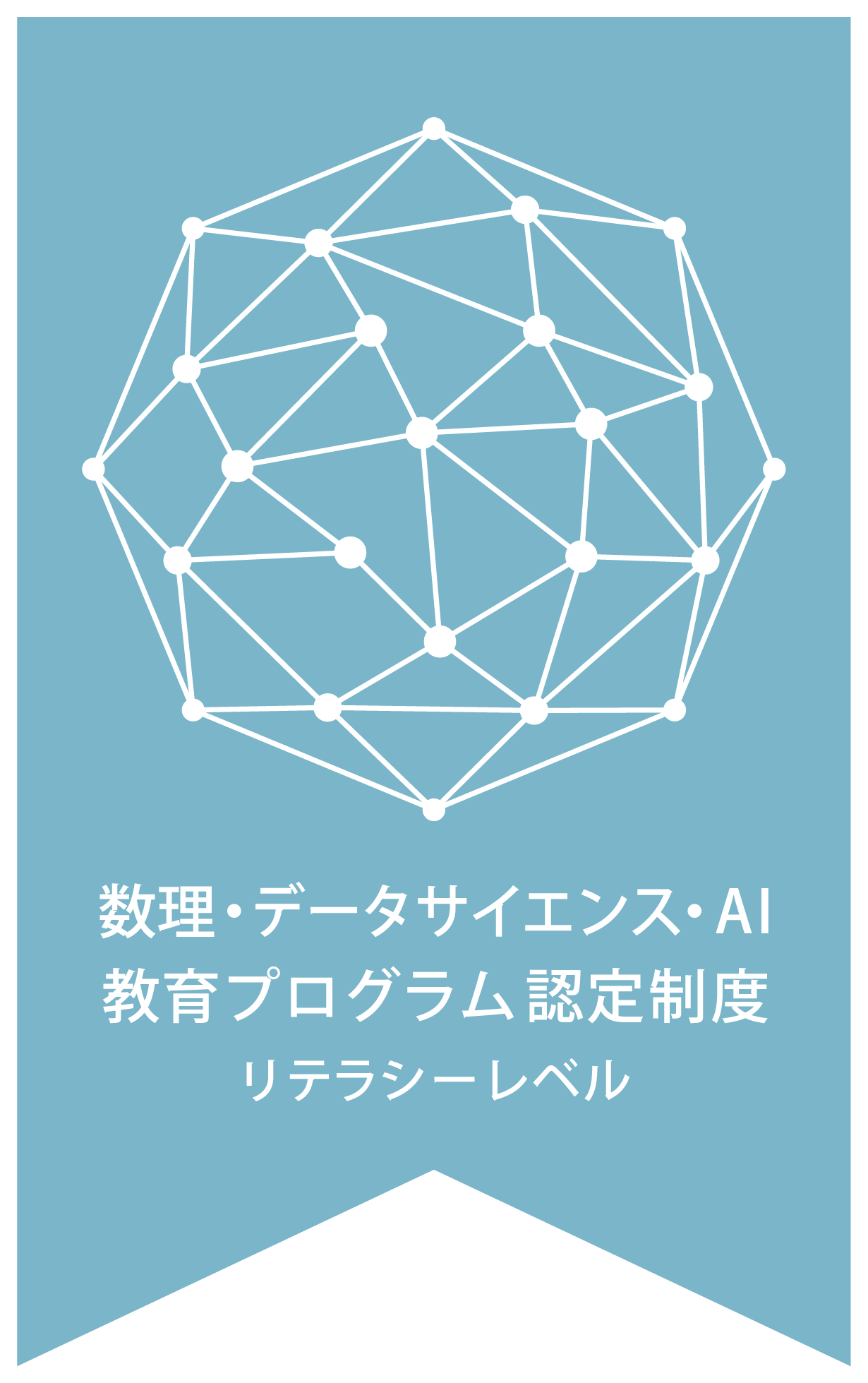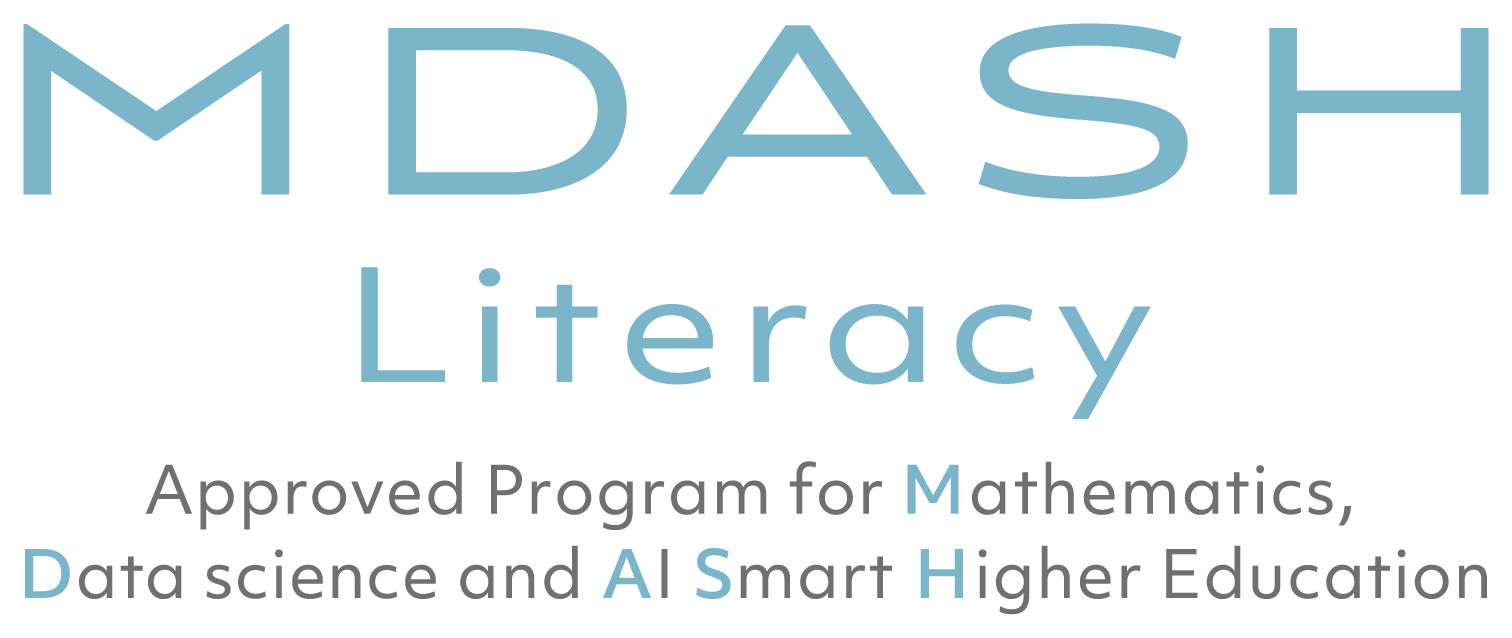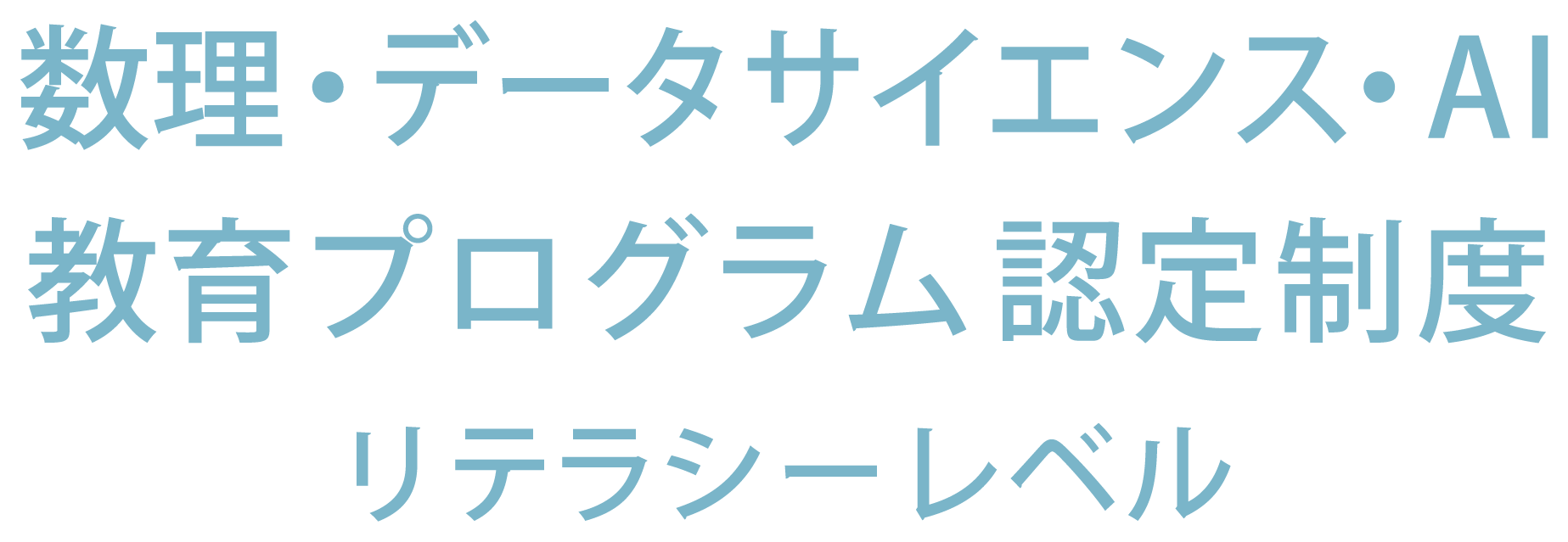【研究論文】市田柿デジタルアーカイブによる地域活性化の研究
1.諸 言
(1)研究の動機
祖父が市田柿を生産しており、市田柿を地域活性化に繋げることができると思い。市田柿をデジタルアーカイブすることにより、発祥地である下伊那郡高森町の地域の活性化に繋げるための研究を進めたいと考えた。
(2)研究の目的
「市田柿」は平成 28 年度に長野県で初めて地理的表示(GI)保護制度に登録された、飯伊地区を代表する特産品である。特に年末年始の国内における人気が高く、近年では海外での GI登録を進めており、中華圏等を対象とした輸出拡大により海外での人気も高くなっている。
「市田柿」を取り扱う団体の活動により、市田柿の消費拡大、販売価格向上に繋がってきた。しかし、「市田柿」を食べたことのない若年層の増加、生産者の高齢化と後継者不足が課題となっている。このような中で、令和3年度に「市田柿」販売開始 100周年を迎えるにあたり、この地域の伝統的食文化として「市田柿」を守り、次の 100 年に伝えていきたいという思いから、「市田柿」を食べて知ってもらうこと、将来的に「市田柿」を食べる習慣を身につけてもらうこと、「市田柿」を中心とした就農者の確保に繋げていくことを目的に研究を実施した。
(3)研究の背景
① 下伊那郡の地域の課題
下伊那郡は長野県の南端に位置し、豊かな自然と伝統文化に恵まれた地域ですが、多くの地方と同様に地域活性化において複数の課題を抱えています。主な課題を以下に詳述します。
(1)人口減少と高齢化
下伊那郡の最大の課題の一つは、深刻な人口減少と高齢化です。若年層の都市部への流出が続き、出生率の低下も相まって、地域全体の活力が失われつつあります。高齢化の進展は、地域コミュニティの担い手不足、医療・介護インフラへの負担増、さらには耕作放棄地の増加といった問題を引き起こしています。地域経済を支える労働力人口の減少は、産業の衰退にも直結し、悪循環を生み出しています。
(2)産業の衰退と担い手不足
下伊那郡の基幹産業は農業が中心ですが、高齢化と後継者不足により、農業生産力の低下が懸念されています。特に、地域の特産品である果樹栽培や畜産業において、新たな担い手の確保が急務です。また、伝統的な製造業も存在しますが、国内外の競争激化や技術革新への対応の遅れから、経営が厳しさを増している企業も少なくありません。新たな産業の創出や既存産業の活性化に向けた戦略が求められています。
(3)交通インフラの不便さ
下伊那郡は山間部に位置するため、広域交通網へのアクセスが比較的限られています。主要都市からの距離があり、公共交通機関も十分とは言えません。この交通の不便さは、観光客誘致の足かせとなるだけでなく、企業の誘致や物流コストにも影響を与え、経済活動の活性化を阻害する要因となっています。リニア中央新幹線の開通が期待されていますが、その恩恵を地域全体で享受するための二次交通の整備も不可欠です。
(4)地域資源の有効活用と情報発信不足
下伊那郡には、天竜峡に代表される美しい自然景観、飯田市人形劇フェスタなどの文化イベント、そして伝統的な食文化など、魅力的な地域資源が豊富に存在します。しかし、これらの資源が十分に活用されていない、あるいはその魅力が外部に十分に伝わっていないという課題があります。地域ブランドの確立やプロモーション戦略の強化を通じて、これらの資源を観光客誘致や地域産品の販路拡大に結びつける必要があります。
(5)行政と住民、事業者間の連携不足
地域活性化には、行政、住民、そして事業者間の緊密な連携が不可欠です。しかし、下伊那郡においても、それぞれの主体が個別に活動し、情報共有や連携が不足しているケースが見られます。地域課題の解決や新たな取り組みの推進には、共通の目標設定と、それを実現するための協働体制の構築が喫緊の課題となっています。特に、若者の視点やIターン・Uターン者の知見を地域づくりに活かすための仕組みづくりが重要です。
下伊那郡の地域活性化は、人口減少・高齢化という構造的な問題に加えて、産業の担い手不足、交通の不便さ、地域資源の有効活用と情報発信不足、そして多様な主体間の連携不足といった多岐にわたる課題が複合的に絡み合っています。これらの課題に対し、地域の実情に即したきめ細やかな戦略を策定し、多様な関係者が連携して持続可能な地域づくりを進めることが、下伊那郡の未来にとって不可欠と言えるでしょう。
② 市田柿の生産の現状と推移
長野県下伊那郡を主産地とする「市田柿」は、美しい飴色の果肉ときめ細やかな白い粉、もっちりとした上品な甘みが特徴の高級干し柿として知られ、地域団体商標や地理的表示(GI)にも登録されているブランド品です。その生産は地域の基幹産業であり、伝統的な技術と手間ひまをかけて作り上げられていますが、近年、その現状と将来に向けていくつかの課題を抱えながら推移しています。
(1)生産量の現状と推移
市田柿の正確な生産量全体の統計は探しにくいものの、JAみなみ信州の販売額は2022年度に26億円を突破するなど、ブランド価値の向上とともに一定の生産量は維持されています。しかし、その内訳を見ると、生産を支える農家の高齢化と後継者不足が深刻化しており、これが生産量維持への大きな懸念材料となっています。
(2)高齢化と担い手不足: 市田柿の生産農家の半数以上が70歳代以上であり、後継者がいない農家も少なくありません。市田柿の生産は、収穫から皮むき、乾燥、もみ込みといった工程に集中的な労力と熟練の技術が必要とされるため、高齢化が進むにつれて生産を断念する農家が増加する傾向にあります。耕作放棄地の増加も指摘されており、生産基盤の維持が課題となっています。
(3)生産規模の二極化: 中小規模の生産者で産地が維持されている一方で、生産規模の縮小を考える農家も約3割に上ります。JAや地域は、産地を牽引する中核的農家の生産量拡大を支援するとともに、中小規模生産者の生産工程の効率化や労力補完のための体制整備、新規就農者の呼び込みを強化することで、需要に応える生産基盤の強化を目指しています。
生産技術と品質維持への取り組み
市田柿の生産には、独自の技術と品質基準があります。高品質な市田柿を生産するためには、収穫後の施肥から剪定、病害虫対策、摘果作業など年間を通じた細やかな管理が必要です。また、独特の飴色の果肉に仕上げるための硫黄くん蒸や、もっちりとした食感を生み出すための天竜川から発生する「川霧」の恩恵、そして熟練の職人による手もみといった伝統的な工程が欠かせません。
(4)品質管理の徹底: 市田柿ブランド推進協議会が設立され、市田柿の定義を定め、品質基準の維持向上、衛生意識向上のための研修会などを積極的に行っています。
スマート農業の導入: 生産者の負担軽減と品質向上のため、乾燥工程の重量や温湿度を遠隔で監視できる「スマート農業アイテム」の導入が進められています。これにより、乾燥管理の失敗によるカビなどの品質不良を減らし、生産ロスを抑える効果が期待されています。
賞味期限延長の取り組み: 海外輸出の拡大に伴い、賞味期限の延長が課題とされていましたが、包装資材の改善等で対応が可能となり、輸出先国の拡大に寄与しています。
流通と海外展開
市田柿は、国内では年末の贈答用としての需要が高く、年明けには市場価格が低迷する傾向にありました。この国内需要の偏りを解消し、価格の安定化を図るため、海外輸出が積極的に推進されています。
(5)海外輸出の強化: 2016年から特許庁の地域団体商標海外事業に参画し、戦略的な輸出を開始しました。台湾、香港、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、カナダ、米国などへの輸出実績があり、特に中華圏の旧正月「春節」の贈答需要を見据えたアジア市場への輸出を強化しています。
GI登録とブランド力向上: 国内外でのGI登録(地理的表示保護制度)を通じて、市田柿のブランド価値向上と模倣品対策に取り組んでいます。これにより、高品質な日本産の商品として海外での認知度も向上しています。
(6)販路拡大と多様化: 伝統的な青果市場経由の販売に加え、現地のインポーターや販売業者との連携、試食販売などを通じたプロモーション活動も行われ、販路の多様化が進んでいます。
・今後の展望と課題
市田柿の生産は、ブランド力向上と海外輸出の拡大により、一定の成果を上げています。しかし、高齢化と後継者不足は依然として深刻な課題であり、生産基盤の維持・強化が喫緊の課題です。
(1)新規就農者支援と生産者の確保: 地域内外の中堅・若手農業者や新規就農者への支援策を強化し、市田柿の生産に意欲のある担い手を継続的に確保していく必要があります。
生産工程の効率化と省力化: 高齢の生産者でも無理なく生産を続けられるよう、スマート農業技術のさらなる導入や、皮むきなどの作業を共同で行う施設の活用など、生産工程の効率化と省力化が求められます。
(2)気候変動への適応: 近年の温暖化による気候条件の変化も課題となっています。市田柿の生産に適した昼夜の寒暖差や川霧の発生に影響が出る可能性もあり、気候変動に適応するための栽培技術や生産管理方法の検討も必要とされています。
市田柿は、地域に根差した伝統的な産品として、その生産維持と発展のために多角的な取り組みが続けられています。国内外での需要拡大と安定供給に向け、生産者の確保、技術革新、そして関係者間の連携が今後も重要な鍵となるでしょう。
③ 市田柿デジタルアーカイブによる市田柿のプランド戦略
市田柿は、長野県下伊那郡に伝わる伝統的な干し柿であり、その歴史と文化、そして高品質な製品としての価値が地域団体商標やGI(地理的表示)登録によって確立されています。しかし、生産者の高齢化や後継者不足、さらには気候変動といった課題に直面する中で、持続的なブランド力を維持・向上させるためには、デジタル技術を活用した新たな戦略が不可欠です。その具体的な方法として、「市田柿デジタルアーカイブ」の構築と活用が非常に有効と考えられます。
市田柿デジタルアーカイブとは、市田柿に関するあらゆる情報をデジタルデータとして収集、整理、保存し、多様な目的で活用するためのプラットフォームを指します。単なる情報の保管庫ではなく、積極的にブランド戦略に組み込むことで、市田柿の価値を多角的に高め、国内外への発信力を強化することができます。
以下に、市田柿デジタルアーカイブをブランド戦略として活用するための具体的な方法を詳述します。
(1)歴史と文化の継承と発信
市田柿は単なる農産物ではなく、地域の歴史と文化に深く根ざした存在です。デジタルアーカイブは、その歴史と文化を永続的に継承し、次世代に伝える強力なツールとなります。
具体的な方法:
歴史的資料のデジタル化: 市田柿の起源、栽培方法の変遷、干し柿文化の歴史を示す古文書、写真、絵画などを高精細でデジタル化し、ウェブサイト上で公開します。例えば、昔の栽培風景や作業風景を収めた写真や、市田柿が地域経済に果たしてきた役割を伝える文献などを公開することで、その歴史的背景を深く理解させることができます。
伝統技術の記録と公開: 市田柿作りには、皮むき、縄かけ、硫黄くん蒸、手もみといった熟練の技が不可欠です。これらの伝統的な製造工程を、高画質の動画や写真、詳細な解説テキストで記録し、アーカイブに収めます。例えば、ベテラン農家の手もみの技術をスローモーションで撮影し、その繊細な指先の動きを解説することで、製品に込められた手間と情熱を視覚的に伝えることができます。これは、国内外の消費者に対し、市田柿が単なる食品ではなく「匠の技」によって生み出される芸術品であることをアピールする上で非常に有効です。
地域文化との関連性: 市田柿が地域のお祭りや年中行事、食文化の中でどのように位置づけられてきたかを記録します。例えば、市田柿を使った郷土料理のレシピ動画や、地域に伝わる市田柿にまつわる民話や歌などをアーカイブすることで、市田柿が地域社会と密接に関わってきたことを示し、地域のアイデンティティとしての価値を高めます。
(2)生産者と産地の「顔」が見える化
消費者が食品を選ぶ際に、生産者の顔やストーリー、産地の情報が重要視される傾向にあります。デジタルアーカイブは、これらの情報を網羅的に提供し、消費者と生産者の信頼関係を構築する上で貢献します。
具体的な方法:
生産者データベースの構築: 各生産者のプロフィール(名前、顔写真、年齢、生産歴、市田柿への思いなど)を詳細に記録し、公開します。例えば、「〇〇さんの市田柿」として、栽培へのこだわりや苦労話、未来への展望などをインタビュー動画や文章で紹介することで、消費者はより深い共感を得ることができます。
畑の様子や作業風景の公開: 生産者の畑の四季折々の様子、収穫作業、干し柿作業風景などをリアルタイムに近い形で動画や写真で発信します。例えば、InstagramやYouTubeと連携し、日々の作業風景をライブ配信したり、短時間の動画で「今日の市田柿」として更新したりすることで、生産現場の臨場感を伝え、安心感を与えます。これは、特に食の安全や透明性を重視する消費者に響く戦略となります。
トレーサビリティの確保: 各生産者の生産ロットと製品を紐付け、消費者がQRコードなどを読み込むことで、どの生産者が、いつ、どこで生産した市田柿であるかを確認できるシステムを構築します。これにより、信頼性と安心感を大幅に向上させることができます。
(3) 品質と安全性の「見える化」と保証
GI登録されている市田柿ですが、その品質の高さと安全性を消費者に具体的に示すことは、ブランド価値の維持・向上に不可欠です。
具体的な方法:
品質基準の明示と説明: 市田柿のGI基準、JAの品質基準、選果基準などを分かりやすくデジタル化し、公開します。例えば、写真や図を使って「特秀」「秀」「優」といった等級の違いを視覚的に説明し、それぞれの基準がどのように設定されているかを解説することで、消費者は市田柿の品質管理の厳しさを理解することができます。
検査データや認証情報の公開: 残留農薬検査の結果、衛生管理体制の認証(HACCPなど)、GI登録証など、市田柿の安全性と品質を証明するデータをアーカイブします。消費者からの信頼を獲得するために、これらの情報を透明性高く公開することが重要です。
気候データとの連携: 栽培期間中の気温、降水量、日照時間などの気象データを記録し、公開します。これにより、その年の天候が市田柿の生育にどのように影響したかを消費者が理解でき、製品の特性をより深く知ることができます。例えば、特に日照時間が長かった年の市田柿は甘みが強い、といった情報を付加価値として提供できます。
(4)教育と研究への活用
市田柿デジタルアーカイブは、単なる情報発信だけでなく、教育や研究の素材としても活用できます。
具体的な方法:
教育コンテンツの提供: 小学校や中学校の社会科見学用教材、農業高校の教材として、市田柿の栽培から加工までのプロセス、地域の歴史、伝統文化などを学べるデジタルコンテンツを提供します。ゲーム要素を取り入れたり、VR/AR技術を活用したりすることで、よりインタラクティブな学習体験を提供できます。
学術研究への貢献: 市田柿の品種改良、栽培技術の改善、加工技術の最適化に関する研究データや文献をアーカイブし、研究者がアクセスできるようにすることで、学術研究の促進に貢献します。
伝統技術の伝承: 熟練農家の技術を詳細に記録することで、新規就農者や若手農家が学習するための教材として活用できます。例えば、動画で実際の作業工程を繰り返し確認できるようにすることで、技術習得の効率を高めます。
(5)グローバル展開と多言語対応
市田柿の海外輸出を強化するためには、デジタルアーカイブの多言語対応が不可欠です。
具体的な方法:
多言語対応ウェブサイト: アーカイブのコンテンツを、英語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語、フランス語など、主要な輸出先国の言語に翻訳し、ウェブサイト上で公開します。
海外向けプロモーション: 海外の食品見本市やイベントで、デジタルアーカイブを活用したプロモーションを行います。例えば、タブレット端末で市田柿の歴史や生産者のストーリー、製造工程の動画などを紹介することで、海外のバイヤーや消費者に対して強力にアピールできます。
SNSを活用した情報発信: 海外向けのSNSアカウント(WeChat, Facebook, Instagramなど)を開設し、デジタルアーカイブのコンテンツを効果的に活用して情報発信を行います。現地のインフルエンサーとのコラボレーションも有効です。
(6)地域コミュニティの活性化
デジタルアーカイブは、地域住民が市田柿に関する情報を共有し、地域への愛着を深めるためのプラットフォームとしても機能します。
具体的な方法:
住民参加型コンテンツの創出: 地域住民から市田柿にまつわる思い出の写真やエピソードを募集し、アーカイブに掲載します。例えば、昔の市田柿作りの写真や、家族で干し柿を作った思い出話などを集めることで、地域住民の参加意識を高め、アーカイブをより豊かなものにします。
イベント情報の発信: 市田柿に関連するイベント(収穫体験、干し柿作り体験、販売イベントなど)の情報をアーカイブで発信し、地域内外からの参加を促します。
地域活性化への貢献: デジタルアーカイブを観光資源としても活用し、下伊那郡への来訪を促します。例えば、アーカイブ情報と連携した「市田柿巡りスタンプラリー」などを企画し、地域の観光ルートを設定することも可能です。
市田柿デジタルアーカイブは、単なる情報のデジタル化に留まらず、市田柿のブランド価値を多角的に高め、国内外への発信力を強化し、さらには地域の持続的な発展に貢献する強力なツールとなり得ます。歴史と文化の継承、生産者と産地の「顔」の見える化、品質と安全性の保証、教育と研究への活用、グローバル展開、そして地域コミュニティの活性化といった具体的な戦略を組み合わせることで、市田柿は未来へと続く強力なブランドとしてその地位を確固たるものにできるでしょう。
市田柿は、長野県下伊那郡に伝わる伝統的な干し柿であり、その歴史と文化、そして高品質な製品としての価値が地域団体商標やGI(地理的表示)登録によって確立されています。しかし、生産者の高齢化や後継者不足、さらには気候変動といった課題に直面する中で、持続的なブランド力を維持・向上させるためには、デジタル技術を活用した新たな戦略が不可欠です。その具体的な方法として、「市田柿デジタルアーカイブ」の構築と活用が非常に有効と考えられます。
④ 課題
「市田柿」とは、もともとは長野県下伊那郡高森町市田地域で生産されていたことからついた柿の品種名だ。その栽培の歴史は500年以上とされる。現在は、飯田市および下伊那郡の各地域で生産されており、2006年に地域ブランドとして登録されてからは、干し柿にされた状態のものも「市田柿」と呼ぶようになった。
かつては、晴れ渡った秋空のもと農家の軒先に“柿のれん”がオレンジ色に輝く風景が南信州一帯に拡がっていた。現在では、衛生上の観点から屋内の乾燥室に幾重にも吊るされるのが一般的だが、所どころ、窓から“柿のれん”が垣間見られる風景は、南信州の秋の訪れを感じる風物詩だ。
現在は海外へも輸出されるほどの生産規模となり、干し柿の代名詞のようにその名は語られる。販売高は年間40~45億円。南信州の農業を支える、重要な産業のひとつでもある。
しかし、年を追うごとに生産農家の高齢化に伴う労働力不足が加速。生産力の低下が懸念されている。木に成った柿が収穫されることなく、鳥のエサとなってしまっている場所も少なくない。
また、温暖化による気候条件の変化も大きな課題だ。市田柿に必要なのは、昼間と朝晩の気温差。しかし現在はかつてほどの厳しい冷え込みは少ない。気温差が小さくなると、水分の抜けが悪くなり、乾燥時間が長くなったり、カビなどの発生も増加。安定生産を脅かすようになった。
2.研究の方法
(1)市田柿とは
市田柿(いちだがき)は、長野県南部で栽培される柿の品種。果実から干し柿(ドライフルーツ)が作られる。
14世紀頃、現在の長野県下伊那郡高森町に当たる旧市田村で盛んに栽培されていた事が由来である。
市田柿の誕生まで
柿は奈良時代に中国から渡ってきたと言われています。江戸時代には飯田下伊那地方でも柿が作られていました。
当時の飯田下伊那を代表する柿は「立石柿」。江戸でも大変有名でした。伊勢信仰が盛んだった下市田村(現高森町下市田)に立てられた伊勢社の境内にあった柿の古木は「焼いて食べても美味しい」と評判で「焼柿」と呼ばれていました。
この伊勢屋敷に住んでいた寺子屋の師匠 児島礼順が、柿を育て食べることを奨励し、この柿は接木によって村中に、そして村外へと広がりました。
明治時代末期には、市田柿の商品化が進められ、また数々の偉大な先人によって戦後には「市田柿」として東京や名古屋の市場進出を果たすまでになりました。
そして、平成18年に特許庁より「地域商標登録」として認定され、今日の市田柿があります。
書籍『市田柿のふるさと』
2006年(平成18)年10月27日、特許庁により全国52件の一つとして当町の特産品『市田柿』が「地域ブランド(地域団体商標)」に認定されたのを受け、2006年12月20日に郷土歴史家、柿生産者、町議会議員、地元役員、役場職員等14名からなる「市田柿の由来研究委員会」が発足しました。この方々の手によって、当町の特産品「市田柿」の由来についてまとめた書籍『市田柿のふるさと』が作られました。
(2)市田柿の歴史
市田郷地域で柿の栽培が始まったのは、江戸時代の伊勢神宮参拝(伊勢講)により、当時既に柿栽培が盛んであった美濃(現在の岐阜県南部)よりもたらされたとの説が有力とされる。地元の萩山神社にはその社が残っている。
この頃は焼柿とよばれ、囲炉裏端で焼いて渋を抜き食べられることが主であったとされるが、しだいに吊るされ「ころ柿」として加工されるようになり、1922年(大正11年)に市田村青年団により、焼柿から「市田柿」と改称し、中央市場に共同出荷が行われる。この時は失敗に終わるが、その後戦争を経て、戦後、出荷量は増加していく。
戦後になり、病害虫駆除、施肥、整枝・剪定の技術の普及、長野県立農業試験場によって硫黄燻蒸法などが確立され、更に優良系統選抜などを経て品質を均質化。かつての主要産業であった養蚕が世界恐慌などを経て衰退していたこともあって栽培面積が増加した、それに違って栽培地域も旧市田村地方から、伊那谷に広まっていく。
近年では火力乾燥法や消毒法、あるいは柿加工乾燥に適した乾燥設備(通称「柿ハウス」)の普及、パッケージの工夫などによる販路の拡大などにより急成長した。 2006年(平成18年)には地域団体商標登録制度がスタートし、長野県で最初の地域ブランドとして認定を受けた。
(3)市田柿の製造過程
① 特徴
果実は小ぶりであり、生柿・干し柿共に紡錘形をしている。同じ干し柿でも、あんぽ柿に比べると固めであり、串柿などにくらべると柔らかめなのが特徴である。市田柿の干し柿は、表面がいわゆる「粉(こう)が吹いている」、すなわちブドウ糖が表面に染み出て白い粉に覆われるのが上等品とされる。栄養価はポリフェノールが特筆して高い。100グラム中の含有量が250ミリグラムであり、干しぶどう(赤)に比べて3倍近い。
② ブランド
地域団体商標「市田柿」を管理する市田柿ブランド推進協議会では「原料柿、製造地域共に飯田市・下伊那地方に限る」としている[3]。他の干し柿ブランドとの違いとして、原料柿の品種まで指定されていることが挙げられる。
かつては焼き柿として食され、1922年(大正11年)頃から「市田柿」の商標を名乗り、当時の市田村壮年団が販売を試みている[4]。市田柿活性化推進協議会は2021年から市田柿を紹介した冊子を作成するなど100周年事業を展開している。
本格的に1950年(昭和25年)頃から優良系統を選び、市田柿に適した栽培法、燻蒸法などが普及、第二次世界大戦後に干し柿として商品化が進められた。現在では飯田市や下伊那など南信州地域を中心に栽培され、2001年(平成13年)の栽培面積は495ヘクタール、生産者数は約5000戸、2005年から2012年までの平均生産量は、原料柿で推定8577トン、加工済みの干し柿で2143トンに及ぶ。干し柿生産量では日本最大である。
③ 生育
市田柿は頂部優勢が強く直立した形状になりやすい。樹高が高いと作業効率や安全性に支障が生じるため、栽培においては定植10年ほどで心抜きを行ない、主枝の発生位置を低くして樹高を3.5メートル以下程度に保つことが多い。次郎柿などの甘柿とは違い、生で食すると口の中に収められないほどのタンニンが感じられる渋柿。果実は10月下旬から11月上旬にかけて熟し、一個あたりの重量は100グラムと小ぶりである。
人工的に手を加えて交配したものではなく、品種の中から優良な母木を選び広めたもののため、樹としては原種に近く、比較的病気に強いとされる。
④ 製法
伝統的な従来製法から、機械化などが行われているが基本的には同じ製法が守られている。市田柿の商標がついて販売されている柿は、基本的に2004年(平成16年)に市田柿の商標を管理する生産販売団体が中心となって作成された衛生マニュアルに基づき管理が行われている。
⑤ 収穫
果樹園にて黄色から橙色に実った所で収穫される。身は橙色になってもまだ固く渋い。収穫は果樹の「萼」の部分、ほぞとも言われる部分を残すように、また樹を傷めぬよう、実っている方向と逆向きに転がすように回すとぽろりと取れる。収穫した果実は、2,3日のうちにすぐに加工されるか、あるいは0~2℃、湿度90%程度に保たれた予冷庫に保管され加工される。
なお、収穫時期を逃すと赤く柔らかくなった「熟し」と呼ばれる状態になる。この状態になると干し柿にはならずまた日持ちもしないが、渋がなくなり非常に甘くなる。一般に流通することは殆ど無いが、古くからはきな粉をまぶすなどし、あるいは冷凍してシャーベット状などにするなどしても食べられることがある。
⑥ 皮むき
ヘタの部分を残し、完全に皮をむく。現在は専用の全自動・半自動と呼ばれる機械を用いて加工されるが、戦後直後までは千重(せんかさ)と呼ばれる独特の刃物が用いられ、1980年代までは手回しの機械を用いて皮むきがなされていた。この時用いる刃物は、水滴型の柿の形に沿うように大型で刃が沿うになっており、一般的な調理用の器具とは異なっていた。現在は市田柿本体に針を挿し込まず固定し、より高品質な加工ができる吸引式の装置の普及が始まっており[10]、市田柿の商標を管理する市田柿ブランド協議会では、2014年産から完全に針を使わない吸引式のみにする予定である。
地元の出荷を行なっているみなみ信州農業協同組合等では、近年中に全面的にこの衛生的に優れ歩留まりをよくする吸引式の装置への移行を目指している。
⑦ 吊るし
1.5mほどの紐に吊るし「連」とよばれるものにする。 古くは藁縄、戦中から戦後にかけてはタコ糸などが用いられてきたが、現在はナイロン製の専用の細い糸、あるいは、樹脂製のフックが付いた紐が使われる。
⑧ 燻蒸
硫黄により燻蒸を施す。硫黄を燃やして得る二酸化硫黄が用いられる。この二酸化硫黄燻蒸によって酸化を防止し、硬くなりすぎずまたタンニンの硬化を防ぐ。なお硫黄は燻蒸量も少なく、2週間にも及ぶ乾燥中に蒸発してしまうが、製法中の唯一の食品添加物として使用される。
一部では一切硫黄燻蒸を行わない柿も販売されている。 無燻蒸のものには二種類あり、単に初めからそのまま食べるのではなく加工用にするため手間をかけず、硬く色が黒くても構わないものとしたものと、そのまま食べられる干し柿として高級百貨店など特別な販路向けに限定で流通し高価であるものがある。
前者の場合は単純に手間を省いているため硬くなりそのまま食べるには適さない。一部の業者ではこれを逆手に取り「より自然に近い」等と宣伝しているが、単に製法の違いであり自然に近いわけではない。また本来は加工用であるにもかかわらず、これをそのまま食べるものとして販売している業者も存在する。
後者の場合でもタンニンの効果によって色は黒くなるが、厳密に水分量を管理し手揉みなどを行うなどで手間をかけることによって硬くなるのを防いでいる。しかし、一般にあまり食味は変わらないか少し悪い(品評会等では硫黄燻蒸品の評価のほうが高い)。しかしイメージを優先する自然派志向のニーズに応えるものとして試験的に一部流通している。
⑨ 乾燥
縄に柿がぶら下がった「連」の状態で風通しの良い場所に吊るし乾燥させる。 かつては「柿すだれ」と言われ、農家の軒下に紐で吊されたオレンジ色の柿を見ることができたが、現在では食品の衛生管理の観点から、出荷をする生産農家については管理がなされた農業用ハウスなどで干されている。そのため今でも軒下に見ることのできる柿のれんは、自家用のものか、もしくは観光客向けに見せるために吊された物である。
この工程を加温し短縮する製法もある。ここで自然に粉が出るまで吊るしたまま乾燥させることもあるが、多くは以下の粉だし工程が行われる。
⑨ 粉だし
10日~2週間程度、約半分ほどまでに干し上がり、渋が抜けた所で縄から外し(「柿を下ろす」と呼ばれる)、ほぞ(萼の部分)及びヘタの部分を切り落とし、一つ一つ柿を確認する。
その後、寝かせ込みと天日干しをし、柿もみ機と呼ばれる回転するドラムの中に柿を入れ、刺激を与えると、柿が白い粉(こ)を噴く。適正な干し上がりになるよう、また均一に粉が来るように寝かせ込み、天日干し、柿もみを繰り返して、精錬する。
全面に均一に粉が来た所で完成。その後選別・梱包などが行われる。現在では酸素を通さないフィルムを用いたパッケージに、脱酸素剤を用いて品質が落ちにくいパッケージが使われているが、市田柿は涼しいところに置き、またパッケージを開封したら出来るかぎり早く食べることが望ましい。温かいところに置くと過乾燥を招き硬くなったり、逆に水分を吸収し「もどり」あるいは「煮え」と呼ばれる現象を引き起こしたりして食味を損なう。なお短期であれば冷凍も可能である(解凍は自然解凍のこと)。
(4)市田柿の利用
飯田市や下伊那郡地域では「元旦に食べた干し柿から出てきた種の数が多いほど、その一年で多くの富を蓄えることができる」という言い伝えがあるため、新年を祝う席に縁起物として干し柿を食べる習慣がある。その他、和菓子などの加工用にも用いられる。加工には切り込んで混ぜたような菓子のほか、その白く柔らかく粉が来た見た目を生かした高級和菓子などもある。
3.市田柿のデジタルアーカイブ
(1)市田柿の製造過程
① 特徴
果実は小ぶりであり、生柿・干し柿共に紡錘形をしている。同じ干し柿でも、あんぽ柿に比べると固めであり、串柿などにくらべると柔らかめなのが特徴である。市田柿の干し柿は、表面がいわゆる「粉(こう)が吹いている」、すなわちブドウ糖が表面に染み出て白い粉に覆われるのが上等品とされる。栄養価はポリフェノールが特筆して高い。100グラム中の含有量が250ミリグラムであり、干しぶどう(赤)に比べて3倍近い。
② ブランド
地域団体商標「市田柿」を管理する市田柿ブランド推進協議会では「原料柿、製造地域共に飯田市・下伊那地方に限る」としている[3]。他の干し柿ブランドとの違いとして、原料柿の品種まで指定されていることが挙げられる。
かつては焼き柿として食され、1922年(大正11年)頃から「市田柿」の商標を名乗り、当時の市田村壮年団が販売を試みている[4]。市田柿活性化推進協議会は2021年から市田柿を紹介した冊子を作成するなど100周年事業を展開している。
本格的に1950年(昭和25年)頃から優良系統を選び、市田柿に適した栽培法、燻蒸法などが普及、第二次世界大戦後に干し柿として商品化が進められた。現在では飯田市や下伊那など南信州地域を中心に栽培され、2001年(平成13年)の栽培面積は495ヘクタール、生産者数は約5000戸、2005年から2012年までの平均生産量は、原料柿で推定8577トン、加工済みの干し柿で2143トンに及ぶ。干し柿生産量では日本最大である。
③ 生育
市田柿は頂部優勢が強く直立した形状になりやすい。樹高が高いと作業効率や安全性に支障が生じるため、栽培においては定植10年ほどで心抜きを行ない、主枝の発生位置を低くして樹高を3.5メートル以下程度に保つことが多い。次郎柿などの甘柿とは違い、生で食すると口の中に収められないほどのタンニンが感じられる渋柿。果実は10月下旬から11月上旬にかけて熟し、一個あたりの重量は100グラムと小ぶりである。
人工的に手を加えて交配したものではなく、品種の中から優良な母木を選び広めたもののため、樹としては原種に近く、比較的病気に強いとされる。






























④ 製法
伝統的な従来製法から、機械化などが行われているが基本的には同じ製法が守られている。市田柿の商標がついて販売されている柿は、基本的に2004年(平成16年)に市田柿の商標を管理する生産販売団体が中心となって作成された衛生マニュアルに基づき管理が行われている。
⑤ 収穫
果樹園にて黄色から橙色に実った所で収穫される。身は橙色になってもまだ固く渋い。収穫は果樹の「萼」の部分、ほぞとも言われる部分を残すように、また樹を傷めぬよう、実っている方向と逆向きに転がすように回すとぽろりと取れる。収穫した果実は、2,3日のうちにすぐに加工されるか、あるいは0~2℃、湿度90%程度に保たれた予冷庫に保管され加工される。
なお、収穫時期を逃すと赤く柔らかくなった「熟し」と呼ばれる状態になる。この状態になると干し柿にはならずまた日持ちもしないが、渋がなくなり非常に甘くなる。一般に流通することは殆ど無いが、古くからはきな粉をまぶすなどし、あるいは冷凍してシャーベット状などにするなどしても食べられることがある。
⑥ 皮むき
ヘタの部分を残し、完全に皮をむく。現在は専用の全自動・半自動と呼ばれる機械を用いて加工されるが、戦後直後までは千重(せんかさ)と呼ばれる独特の刃物が用いられ、1980年代までは手回しの機械を用いて皮むきがなされていた。この時用いる刃物は、水滴型の柿の形に沿うように大型で刃が沿うになっており、一般的な調理用の器具とは異なっていた。現在は市田柿本体に針を挿し込まず固定し、より高品質な加工ができる吸引式の装置の普及が始まっており[10]、市田柿の商標を管理する市田柿ブランド協議会では、2014年産から完全に針を使わない吸引式のみにする予定である。
地元の出荷を行なっているみなみ信州農業協同組合等では、近年中に全面的にこの衛生的に優れ歩留まりをよくする吸引式の装置への移行を目指している。































⑦ 吊るし
1.5mほどの紐に吊るし「連」とよばれるものにする。 古くは藁縄、戦中から戦後にかけてはタコ糸などが用いられてきたが、現在はナイロン製の専用の細い糸、あるいは、樹脂製のフックが付いた紐が使われる。










































⑧ 燻蒸
硫黄により燻蒸を施す。硫黄を燃やして得る二酸化硫黄が用いられる。この二酸化硫黄燻蒸によって酸化を防止し、硬くなりすぎずまたタンニンの硬化を防ぐ。なお硫黄は燻蒸量も少なく、2週間にも及ぶ乾燥中に蒸発してしまうが、製法中の唯一の食品添加物として使用される。
一部では一切硫黄燻蒸を行わない柿も販売されている。 無燻蒸のものには二種類あり、単に初めからそのまま食べるのではなく加工用にするため手間をかけず、硬く色が黒くても構わないものとしたものと、そのまま食べられる干し柿として高級百貨店など特別な販路向けに限定で流通し高価であるものがある。
前者の場合は単純に手間を省いているため硬くなりそのまま食べるには適さない。一部の業者ではこれを逆手に取り「より自然に近い」等と宣伝しているが、単に製法の違いであり自然に近いわけではない。また本来は加工用であるにもかかわらず、これをそのまま食べるものとして販売している業者も存在する。
後者の場合でもタンニンの効果によって色は黒くなるが、厳密に水分量を管理し手揉みなどを行うなどで手間をかけることによって硬くなるのを防いでいる。しかし、一般にあまり食味は変わらないか少し悪い(品評会等では硫黄燻蒸品の評価のほうが高い)。しかしイメージを優先する自然派志向のニーズに応えるものとして試験的に一部流通している。
⑨ 乾燥
縄に柿がぶら下がった「連」の状態で風通しの良い場所に吊るし乾燥させる。 かつては「柿すだれ」と言われ、農家の軒下に紐で吊されたオレンジ色の柿を見ることができたが、現在では食品の衛生管理の観点から、出荷をする生産農家については管理がなされた農業用ハウスなどで干されている。そのため今でも軒下に見ることのできる柿のれんは、自家用のものか、もしくは観光客向けに見せるために吊された物である。
この工程を加温し短縮する製法もある。ここで自然に粉が出るまで吊るしたまま乾燥させることもあるが、多くは以下の粉だし工程が行われる。
⑨ 粉だし
10日~2週間程度、約半分ほどまでに干し上がり、渋が抜けた所で縄から外し(「柿を下ろす」と呼ばれる)、ほぞ(萼の部分)及びヘタの部分を切り落とし、一つ一つ柿を確認する。
その後、寝かせ込みと天日干しをし、柿もみ機と呼ばれる回転するドラムの中に柿を入れ、刺激を与えると、柿が白い粉(こ)を噴く。適正な干し上がりになるよう、また均一に粉が来るように寝かせ込み、天日干し、柿もみを繰り返して、精錬する。
全面に均一に粉が来た所で完成。その後選別・梱包などが行われる。現在では酸素を通さないフィルムを用いたパッケージに、脱酸素剤を用いて品質が落ちにくいパッケージが使われているが、市田柿は涼しいところに置き、またパッケージを開封したら出来るかぎり早く食べることが望ましい。温かいところに置くと過乾燥を招き硬くなったり、逆に水分を吸収し「もどり」あるいは「煮え」と呼ばれる現象を引き起こしたりして食味を損なう。なお短期であれば冷凍も可能である(解凍は自然解凍のこと)。
(2)市田柿の歴史
市田郷地域で柿の栽培が始まったのは、江戸時代の伊勢神宮参拝(伊勢講)により、当時既に柿栽培が盛んであった美濃(現在の岐阜県南部)よりもたらされたとの説が有力とされる。地元の萩山神社にはその社が残っている。
この頃は焼柿とよばれ、囲炉裏端で焼いて渋を抜き食べられることが主であったとされるが、しだいに吊るされ「ころ柿」として加工されるようになり、1922年(大正11年)に市田村青年団により、焼柿から「市田柿」と改称し、中央市場に共同出荷が行われる。この時は失敗に終わるが、その後戦争を経て、戦後、出荷量は増加していく。
戦後になり、病害虫駆除、施肥、整枝・剪定の技術の普及、長野県立農業試験場によって硫黄燻蒸法などが確立され、更に優良系統選抜などを経て品質を均質化。かつての主要産業であった養蚕が世界恐慌などを経て衰退していたこともあって栽培面積が増加した、それに違って栽培地域も旧市田村地方から、伊那谷に広まっていく。
近年では火力乾燥法や消毒法、あるいは柿加工乾燥に適した乾燥設備(通称「柿ハウス」)の普及、パッケージの工夫などによる販路の拡大などにより急成長した。 2006年(平成18年)には地域団体商標登録制度がスタートし、長野県で最初の地域ブランドとして認定を受けた。
(3)萩山神社
萩山神社は、寿永年間(1182年頃)松岡氏四代帯刀が諏訪大明神を勧請して創建した。次いで鎌倉時代に鶴岡八幡宮の神霊を勧請して諏訪神社に合祀した。萩山神社は、弘安年中(1278~1287)と寛永20年(1643)の2回大火に逢い焼けたが、承応2年(1653)に再建した。荒神社は、最初安養寺の守護神として下市田字大庭に三宝荒神として祀られていたが、明治40年(1907)5月出された知事訓令により大正2年に(1913)神社を統合し、現在地に移され、祭神も三宝荒神から素戔鳴命に変わっている。
昭和58年2月高森町文化財に指定された。
長野県下伊那郡高森町に鎮座する萩山神社は、地域の信仰の中心であり、その歴史は市田柿の発祥と普及に間接的ではありますが深く関わっています。直接的に市田柿を生み出した場所ではないものの、市田柿の歴史を語る上で欠かせない「伊勢社」との強い結びつきから、萩山神社もまた市田柿のルーツを辿る重要な要素となっています。
・萩山神社の歴史と伊勢社
萩山神社は、寿永年間(1182年頃)にこの地の領主であった松岡氏が諏訪大明神を勧請して創建されたと伝えられる、非常に歴史のある神社です。その後、鎌倉時代には鶴岡八幡宮の神霊も合祀され、地域の守り神として篤く信仰されてきました。
市田柿の発祥において重要な役割を果たした「伊勢社」は、江戸時代に伊勢信仰が盛んだった旧市田村に、伊勢神宮の分霊を勧請して祀られたものです。この伊勢社には、伊勢参拝客のための「伊勢屋敷」が併設されており、そこに漢学者・児島礼順が住み込み、寺子屋を開いていました。そして、この伊勢社の境内にあった「焼柿の古木」が、現在の市田柿の原種となったとされています。
この伊勢社の祠は、後に近くの萩山神社へ移されたという記録が残されています。これにより、市田柿の原種である「焼柿」が育まれた伊勢社の歴史と、地域の中心的な信仰施設である萩山神社とが結びつけられています。現在の萩山神社の境内には伊勢社そのものや「焼柿の古木」は残っていませんが、その歴史的な繋がりは、市田柿の物語を構成する上で非常に重要です。
・萩山神社と地域農業・生活への影響
萩山神社は、地域の守り神として、古くから五穀豊穣や住民の安寧を祈る場所であり続けてきました。市田柿を含む地域の農業が発展する上で、神社の存在は精神的な支えであり、また共同体意識を育む場でもありました。
祈りの場としての役割: 萩山神社では、春祭りなどの例大祭を通じて、地域の繁栄や農作物の豊作を祈願する神事が行われてきました。市田柿の生産が盛んになるにつれて、柿の豊作もまた、これらの祭りで祈りの対象となっていったと考えられます。地域住民が一体となって祭りを行い、神に感謝し、豊作を願うことは、共同体としての連帯感を強め、過酷な農業労働を支える精神的な基盤となりました。
地域のコミュニティ形成: 神社は、人々が集い、交流する場でもありました。祭りの準備や執行を通じて、地域の情報交換や協力体制が自然と形成されていきました。市田柿の栽培が本格化し、共同出荷が行われるようになる過程においても、このような地域のコミュニティの力が下支えになったことは想像に難くありません。
伝統の継承: 萩山神社で行われる祭りや伝統行事は、世代を超えて受け継がれてきました。これらの行事を通じて、地域の子どもたちは地域の歴史や文化、そして農業の重要性を肌で感じ、市田柿に代表される地域の特産品への愛着を育んできました。
・現代における萩山神社と市田柿
現代において、萩山神社は市田柿の生産と直接的に関わることは少なくなっていますが、その歴史的な繋がりは、市田柿のブランド価値を語る上で重要な要素として認識されています。
歴史的背景の提供: 市田柿の歴史を紐解く際、伊勢社と「焼柿の古木」、そして児島礼順の存在は不可欠であり、その伊勢社が萩山神社に隣接していた、あるいは合祀されたという事実は、市田柿の物語に深みを与えます。高森町の歴史民俗資料館などでも、市田柿の歴史とともに萩山神社や伊勢社への言及があることからも、その重要性がうかがえます。
地域文化の象徴: 萩山神社は、市田柿が生まれた地域の歴史と文化を象徴する存在です。観光客や消費者が市田柿の産地を訪れる際、萩山神社のような歴史的な場所を訪れることで、製品の背景にある物語や地域の魅力をより深く理解することができます。
地域のアイデンティティ: 市田柿は高森町の、ひいては下伊那地域のアイデンティティの一部となっています。萩山神社が長年にわたり地域の守り神として存在し続けることは、この地域のアイデンティティを形成し、維持する上で重要な役割を担っています。
このように、萩山神社と市田柿は、直接的な生産関係というよりは、伊勢社という共通のルーツ、そして地域社会の信仰と共同体の形成という間接的ながらも深い歴史的・文化的な繋がりを持っています。萩山神社は、市田柿が地域に根ざした「伝統」として今日まで受け継がれてきた背景にある、精神的・文化的な基盤を象徴する存在と言えるでしょう。









(4)柿ハウス
市田柿は、長野県下伊那郡を主産地とする伝統的な干し柿であり、その独特の風味と品質は、天竜川から発生する「川霧」と、昼夜の寒暖差が大きい伊那谷の気候に大きく依存してきました。かつては、収穫された柿が農家の軒先に「柿すだれ」として吊るされ、自然の風と太陽によってゆっくりと乾燥していく風景が、伊田谷の冬の風物詩でした。しかし、近年、市田柿の生産において、この伝統的な天日乾燥から**「柿ハウス」での乾燥**へと移行する動きが顕著になっています。
・柿ハウスとは
柿ハウスとは、市田柿を乾燥させるために特別に設計されたビニールハウスや専用の乾燥施設を指します。昔ながらの軒先での天日乾燥に代わり、温度、湿度、通風といった乾燥条件をある程度制御できる環境で市田柿を吊るし、乾燥させるために利用されます。
・柿ハウス導入の背景と目的
柿ハウスの導入は、市田柿の生産が抱える複数の課題に対応し、品質の安定化、生産効率の向上、そして衛生管理の強化を図ることを目的としています。
・品質の安定化と気候変動への対応:
天候不順のリスク軽減: 天日乾燥は、天候に大きく左右されます。長雨や湿度の高い日が続くと、カビが発生しやすくなったり、乾燥が遅れて品質が低下したりするリスクがありました。柿ハウスでは、ビニールや屋根によって外部の天候の影響を軽減できるため、安定した乾燥環境を保ちやすくなります。
最適な乾燥条件の維持: 市田柿の美味しさを決定づける「白い粉(ブドウ糖の結晶)」の生成や、もっちりとした食感を得るには、適切な温度と湿度の管理が不可欠です。柿ハウスでは、窓の開閉や送風機の使用、暖房器具の導入などにより、外部の気候条件に左右されずに理想的な乾燥条件を維持しやすくなります。これにより、不良品の発生を抑え、高品質な市田柿を安定的に生産することが可能になります。
昼夜の寒暖差の活用: 市田柿の品質には伊那谷特有の昼夜の寒暖差が重要ですが、ハウス内でもこの温度差をある程度再現・活用することで、自然の恵みを最大限に引き出す工夫が凝らされています。
・衛生管理の徹底:
異物混入防止: 軒先での天日乾燥は、鳥や虫、小動物の侵入、埃の付着といった衛生面のリスクがありました。柿ハウスは外部と遮断された環境であるため、これらの異物混入を防ぎ、より衛生的で安全な市田柿を生産することができます。これは、特に食品安全に対する意識が高まる現代において、消費者の信頼を得る上で非常に重要な要素となります。
GI登録の要件: 市田柿は地理的表示(GI)保護制度に登録されており、製造場所や製造方法に関して一定の基準が定められています。衛生的な環境での乾燥は、その基準を満たす上でも重要な要素となります。
・生産効率の向上と省力化:
作業の効率化: 柿ハウスでは、柿を吊るすための専用の設備が整っているため、効率的に大量の柿を吊るし、乾燥させることができます。また、乾燥中の柿の管理(揉み込みや吊るし直しなど)も、計画的に行いやすくなります。
省力化の可能性: 一部の大規模な柿ハウスでは、温度や湿度を自動で管理するシステムや、柿を吊るしたまま移動できるレールシステムなどが導入されており、省力化にも貢献しています。これは、生産者の高齢化が進む中で、労働負担を軽減し、生産を継続していく上で重要な役割を果たします。
短期間での乾燥も可能に: 機械乾燥を併用するハウスでは、従来の天日乾燥が30〜40日かかるところを、最短4日で完了させることが可能になるなど、大幅な生産効率の向上が図られています。
・柿ハウス導入の課題
柿ハウスの導入には多くのメリットがある一方で、いくつかの課題も存在します。
初期投資と維持コスト: 柿ハウスの建設には多額の初期投資が必要です。また、暖房や送風のための電気代など、維持管理にもコストがかかります。小規模農家にとっては、これらのコスト負担が大きな課題となる場合があります。
伝統的な風景の喪失: 柿ハウスの普及により、伊那谷の冬の風物詩であった「柿すだれ」の風景が失われつつあります。これは、地域文化の観点から惜しまれる側面もあります。
「自然の恵み」とのバランス: 市田柿の品質は、伊那谷の自然条件に大きく依存しているため、ハウス内での人工的な環境制御と、自然の恵み(寒暖差、川霧など)をどのようにバランスさせるかが、高品質を維持する上で常に課題となります。
市田柿の生産における「柿ハウス」の導入は、気候変動への対応、衛生管理の強化、品質の安定化、そして生産効率の向上といった現代的な課題に応えるための必然的な流れと言えます。伝統的な天日乾燥の風景は失われつつありますが、柿ハウスは、市田柿というブランドの持続可能性を高め、次世代へとその味と文化を継承していく上で不可欠な存在となっています。今後も、技術革新と地域特性の融合を図りながら、最適な生産体制が模索されていくことでしょう。
(5)児島礼順
児島礼順(こじま れいじゅん)は、江戸時代後期の漢学者であり、現在の長野県下伊那郡高森町にあたる旧市田村における「市田柿」の成立と普及に深く関わった人物として知られています。彼の存在は、市田柿が単なる農産物ではなく、地域の歴史と文化に根ざした「伝統」として語られる上で非常に重要な位置を占めています。
・児島礼順の生い立ちと市田村での活動
児島礼順は、三河国田原藩(現在の愛知県田原市)の元藩士と伝えられる漢学者です。彼が市田村に定住した時期や経緯については諸説ありますが、文化年間(1804年~1817年)に、伊勢信仰が盛んだった市田村に勧請された伊勢社(現在の高森町下市田)の境内に設けられた「伊勢屋敷」に住み、そこで寺子屋を開いて子どもたちに学問を教えていたとされています。
当時の市田村では、すでに柿の栽培が行われていましたが、主流は「立石柿」と呼ばれる渋柿で、これを乾燥させた「串柿」が作られていました。しかし、伊田社には「焼柿の古木」と呼ばれる、焼いて食べても美味しいと評判の柿の木があったと伝えられています。
・児島礼順と「焼柿」の普及
児島礼順と市田柿の最も重要な関係は、この伊勢社の「焼柿の古木」を広めたことにあるとされています。彼は、この古木の柿を伊勢社に供えた後、寺子屋の生徒たちと一緒に囲炉裏で焼いて渋抜きをして食べることを奨励しました。この「焼いて食べる」という食べ方が、当時の村人にとって非常に珍しく、美味しいものとして広まりました。
さらに、児島礼順は、この「焼柿」の古木の優れた特性を見抜き、村人たちに接ぎ木によって増やしていくことを促したと言われています。当時、柿を種から育てると収穫までに長い年月がかかるため、すでに接ぎ木栽培の技術は存在していましたが、児島礼順がその普及を積極的に奨励したことで、「焼柿」は村中に、そして村外へと広がっていきました。
・「市田柿」の名称への繋がり
この「焼柿」が、後に「市田柿」と呼ばれるようになる原種とされています。明治時代末期になると、この柿の加工品が共同出荷されるようになり、大正11年(1922年)に市田村青年団によって「市田柿」と命名され、中央市場へ出荷されるようになりました。児島礼順が生涯をかけて広めた柿が、地域の特産品として確立されていく過程において、彼の果たした役割は非常に大きいと言えるでしょう。
・歴史的意義と後世への影響
児島礼順に関する史料は多く残されているわけではありませんが、高森町史や『市田柿のふるさと』などの郷土史研究によって、彼の功績が伝えられています。彼は単に学問を教えるだけでなく、地域の自然や農作物にも深い関心を持ち、その知識と教養を地域の人々の生活向上に役立てようとした、まさしく地域の「知のリーダー」であったと言えます。
児島礼順の存在は、市田柿が単なる美味しい干し柿であるだけでなく、地域に根差した歴史と文化を持つ「ブランド」であることを物語る重要な要素です。彼の功績が語り継がれることで、市田柿には、漢学者の知恵と、それを広めようと努めた人々の情熱、そして地域が一体となって育んできた歴史が凝縮されているという付加価値が生まれています。これは、現代の市田柿のブランド戦略においても、そのルーツを語る上で欠かせない物語となっています。
(6)伊勢神宮参拝(伊勢講)
長野県下伊那郡高森町を主産地とする「市田柿」の発祥には、江戸時代の盛んな伊勢神宮参拝、通称「伊勢講(いせこう)」が深く関わっているとされています。この伊勢講が、当時の地域社会に与えた文化的・経済的な影響が、市田柿の誕生と普及に大きく貢献したと考えられています。
・伊勢講とは
伊勢講とは、江戸時代に日本全国に普及した伊勢神宮への参拝を目的とした民間信仰団体です。当時の庶民にとって伊勢参りは一生に一度あるかないかの大旅行であり、個人での費用負担や旅の安全の確保が困難だったため、村や集落単位で人々が資金を積み立て、くじなどで選ばれた代表者が「代参者」として伊勢神宮へ参拝するという形式が一般的でした。
代参者は、伊勢参りを通じて各地の情報を持ち帰り、また土産物として地域の特産品を持ち帰る役割も担っていました。伊勢参拝は単なる信仰活動に留まらず、地域間の交流を促し、新たな文化や技術、産品が伝播する重要な機会でもあったのです。
・伊勢講と市田柿の発祥
下伊那郡高森町、旧市田村では、江戸時代後期に伊勢信仰が非常に盛んでした。文化年間(1804年~1817年)には、特に信仰の篤かった村人たちが、伊勢神宮の分霊を勧請して「伊勢社」と呼ばれる祠を祀ったと伝えられています。この伊勢社の境内には、伊勢神宮への参拝客(御師)が寝泊まりするための「伊勢屋敷」が設けられていました。
市田柿の発祥に関する説の一つとして有力視されているのが、この伊勢講を通じて、柿の栽培が盛んだった美濃国(現在の岐阜県南部)から、伊勢社境内に持ち込まれた柿の苗木があったというものです。伊勢詣での帰路に、美濃で評判の柿を持ち帰り、伊勢社の境内に植えられた可能性が指摘されています。
そして、この伊勢社の境内に生えていた柿の古木が、後に「焼柿(やきがき)」と呼ばれる、焼いて食べても美味しいと評判の柿であったとされています。この「焼柿」こそが、現在の市田柿の原種となった柿であると考えられています。
・児島礼順の役割と伊勢社の「焼柿」の普及
前述の児島礼順は、この伊勢屋敷に住み込み、寺子屋を開いていた漢学者です。彼は、伊勢社の「焼柿の古木」の優れた品質に注目し、寺子屋の生徒たちと共に囲炉裏で焼いて渋抜きをして食べることを奨励しました。この「焼柿」の美味しさが評判となり、児島礼順は村人たちに、この柿を接ぎ木によって増やしていくことを積極的に促しました。
これにより、「焼柿」は市田村中に広がり、地域の主要な作物として定着していきます。当時の市田村では、すでに「立石柿」という渋柿が栽培され、干し柿として加工されていましたが、「焼柿」はより優れた品質を持っていたため、次第にその存在感を増していきました。
・伊勢講と地域経済・文化の繋がり
伊勢講は、単に柿の苗木が持ち込まれるだけでなく、地域経済や文化にも大きな影響を与えました。
情報と技術の伝播: 伊勢講の代参者たちは、旅先で得た様々な情報や技術を故郷に持ち帰りました。柿の栽培や加工に関する新たな知識も、この交流を通じて地域に伝えられた可能性があります。
地域産品の交流: 伊勢参りの土産物として、各地の特産品が持ち帰られ、また地域の産品が持ち出されることで、広域な流通と評価の機会が生まれました。市田柿の加工品も、当初からこのような交流の中でその価値が認識され、広まっていったと考えられます。
地域共同体の強化: 伊勢講は、村や集落の結束を強める役割も果たしました。共同で費用を積み立て、代参者を送り出すという活動を通じて、地域の連帯感が高まり、それが後の市田柿の共同出荷やブランド化にも繋がっていったと推察されます。
伊勢神宮参拝(伊勢講)と市田柿の発祥は、単なる偶然ではなく、当時の地域社会の信仰、人々の交流、そして知恵が密接に結びついた結果と言えるでしょう。伊勢講を通じて美濃から柿が持ち込まれ、伊勢社の「焼柿の古木」がその原種となり、児島礼順の尽力によってその栽培が広まったという一連の歴史は、市田柿が持つ「地域性」「伝統」「文化」といったブランド価値の重要な根源となっています。
(7)下伊那の歴史
長野県下伊那郡(しもいなぐん)は、古代から現代に至るまで、交通の要衝として、また豊かな自然と文化に育まれた地域として、独特の歴史を歩んできました。特に天竜川の恵みと、甲斐・三河・遠江といった周辺諸国との関わりがその歴史を特徴づけています。
1.古代・中世:伊那郡の成立と動乱の時代
古代の伊那郡
下伊那郡は、元来は伊那郡の一部でした。郡名が記された最古の記録は、**天平10年(738年)の正倉院御物の庸布(ようふ)に記された「信濃国伊那郡」の墨書銘に見られます。古代の伊那郡では、金刺(かなさし)氏などが郡司として名を連ねていました。また、諏訪神氏が天竜川を下って北東部に勢力を拡大したことが、地域開発の一つの焦点であったと考えられています。 平安時代に入ると、現在の伊那市小黒川から下伊那郡松川町付近までの天竜川西岸の河岸段丘一帯は、宮中の御服に用いる麻布を調達する「伊那春近領(いなはるちかりょう)」**という国の領地とされていました。
2.中世の支配構造
鎌倉時代には、肥沃な伊那春近領は北条得宗家の領地となり、得宗家は諏訪大社を中心に上伊那地方までを支配しました。この時代、地域には諏訪氏の系統とされる豪族たちが存在し、得宗家に仕えていました。
室町時代前期には、後醍醐天皇の第八皇子である**宗良親王(むねながしんのう)が、地元の豪族である香坂高宗(こうさかたかむね)らに守られ、大鹿村の大河原(おおかわら)を拠点に30年余りにわたり各地を転戦しました。親王が建立したと推定される寺院も残されており、下伊那地方が南朝方の活動拠点の一つであったことが窺えます。 また、飯田市にある開善寺(かいぜんじ)は、鎌倉時代に江馬氏によって創建され、後に信濃守護となった小笠原貞宗(おがさわらさだむね)**が開基となり、南北朝時代には元(げん)の名僧を招いて開山とするなど、地域の有力な禅寺として栄えました。
3.戦国時代の争乱
戦国時代になると、信濃国は周辺の有力な戦国武将、すなわち甲斐の武田氏、越後の上杉氏、尾張の織田氏、三河の徳川氏といった大勢力に囲まれ、常に領地争いの渦中にありました。肥沃な伊那地方は特に重要な拠点と見なされ、その攻防の舞台となりました。 **天文23年(1554年)には、武田信玄による神之峰城(こうのみねじょう)**侵攻など、武田氏の勢力拡大に伴う戦火に見舞われ、寺院の焼失や寺領の没収などが起こりました。
4.近世:飯田藩と幕府領の時代
飯田藩の成立と変遷
戦国時代が終結し、江戸時代に入ると、下伊那地方は主に飯田藩領と幕府領(天領)に分かれて支配されました。 飯田藩は、関ヶ原の戦いの後に小笠原秀政が入封したことに始まります。その後、脇坂氏、堀氏、そして**享保10年(1725年)に堀親賢(ほりちかかた)**が入って以降は、堀氏が代々藩主を務め、明治維新まで飯田城を拠点としてこの地域を治めました。 一方で、領地の一部は幕府直轄領や旗本領(千村氏預地、知久氏預地など)、また他藩の領地として複雑に入り組んでいました。
交通・経済の発展
近世の下伊那地方は、三河街道(中馬街道)などが通る交通の要衝であり、特に飯田は南信濃の中心都市として発展しました。 主要な産業としては、養蚕や蚕糸業が盛んになり、地域の経済基盤を支えました。また、木材などの天竜川舟運も重要な役割を果たしました。
5.近代・現代:近代化と行政の変遷
廃藩置県と下伊那郡の発足
幕末、下伊那地方では、勤王の志士らが潜伏するなど、新政府への動きも見られました。特に、飯田藩士であり、後に勤王の志士を匿った**多勢子(たせこ)**などの活動は、島崎藤村の小説『夜明け前』にも描かれています。
慶応4年(1868年)、幕府領は伊那県の管轄となり、その後の廃藩置県(明治4年、1871年)により、飯田藩領などは飯田県や名古屋県の管轄となりました。同年11月の第1次府県統合により、全域が筑摩県(ちくまけん)の管轄となります。 明治8年(1875年)の町村統合を経て、明治12年(1879年)1月4日に郡区町村編制法の施行により、伊那郡が上伊那郡と下伊那郡に分割され、正式に下伊那郡が発足しました。郡役所は飯田町(現在の飯田市)に設置されました。
産業と災害
明治時代から昭和初期にかけて、下伊那地方の主要産業である蚕糸業は最盛期を迎え、地域の経済を牽引しました。 また、この時代には、満州移民や北米・南米への移民といった形で、地域住民の多くが新天地を求めて海を渡るという大きな歴史的流れも存在しました。
現代の下伊那郡は、飯田市を中心としながらも、町村合併を経験し、それぞれが独自の文化や産業を守りながら発展を続けています。
長野県下伊那郡は、古代から伊那郡の一部として、天竜川沿いの肥沃な土地と、東西南北を結ぶ交通の要衝として常に注目されてきました。中世には南朝方の拠点や有力寺院の建立、戦国時代には武田・織田・徳川などの勢力に巻き込まれるなど、動乱の歴史を歩みました。近世には飯田藩と幕府領に分かれ、近代以降は蚕糸業を主要産業として発展し、明治以降の行政区画の変遷を経て現在の形を成しています。豊かな自然と歴史的遺産が、下伊那郡の文化を深く形作っています。
(8)下伊那の伝統文化
野県下伊那(しもいな)地域は、古くから甲斐(山梨県)、三河・遠江(愛知県・静岡県)との交流が盛んであったこと、そして中央を貫流する天竜川の恵みと、峻厳な山々に囲まれた地理的環境から、独特で多様な伝統文化が育まれてきました。特に、神々への感謝や災厄を祓うための祭りや芸能、そして地域産業を支えた工芸技術にその特色が色濃く現れています。
1. 祭りと芸能:神々と共に生きる文化
下伊那地域の伝統文化の核をなすのが、神楽や獅子舞などの民俗芸能です。これらは、五穀豊穣、無病息災、家内安全を祈願するもので、長い歴史を通じて地域の人々の精神的な柱となってきました。
(1) 霜月祭り(しもつきまつり)
下伊那を代表する最も重要な伝統行事であり、国の重要無形民俗文化財に指定されています。
概要: 旧暦11月(霜月)に行われる神事であり、一年の収穫を神々に感謝し、来年の豊作を祈る祭りです。特に**湯立て神楽(ゆだてかぐら)**が中心となります。
湯立て神楽: 釜で沸かした熱湯に神々を招き入れ、その湯を浴びることで身を清め、神人一体となる儀式です。
開催地: 飯田市南信濃の和田、程野(ほどの)、**八坂(やさか)**の各神社などで特に有名で、各集落で独特な流れを持っています。これら三つの霜月祭りは、特に古い形を伝えているとされます。
特徴: 祭りのクライマックスでは、仮面をつけた**「面(おもて)」**が登場し、神々の世界を現します。神秘的で幻想的な雰囲気から、作家・**夢枕獏(ゆめまくらばく)**の小説『陰陽師』の着想の一つにもなったと言われています。
(2)飯田の獅子舞
飯田市を中心とした地域には、多種多様な獅子舞が伝承されており、その数は全国的にも有数です。
種類: 神楽獅子、太神楽(だいかぐら)獅子、**三番叟(さんばそう)**の流れを汲むものなど、様々な系統があります。特に、人形頭と呼ばれる独自の獅子頭を用いるものが多いのが特徴です。
用途: 祭礼の際に奉納されるほか、村々を回り家々を清める**門付け(かどづけ)**の役割も担います。力強い舞や、ユーモラスな仕草で人々を楽しませます。
(3)伊那谷の念仏踊り
下伊那地域では、祖霊供養や疫病退散を目的とした念仏踊りも多く見られます。
遠山の郷(とおやまのさと)に残る念仏踊りは、太鼓や鉦(かね)のリズムに合わせて独特の節で念仏を唱えながら踊るもので、地域の信仰生活と深く結びついています。
2.伝統工芸:暮らしに根差した技
下伊那地域では、古くから発達した産業や、地理的条件から生まれた独特な工芸品が現代に受け継がれています。
(1) 飯田水引(いいだみずひき)
飯田市が全国的な生産地として知られ、国の伝統的工芸品に指定されています。
歴史: 江戸時代、飯田藩主が和紙の生産を奨励したことに端を発します。元々は元結(もとゆい:髪を結うための紐)の技術から発展しました。
技術: 和紙を細長く裁断し、こよりを作り、それを水糊で固めて乾燥させたものに色をつけたり、金銀の箔を巻いたりして仕上げます。
用途: 祝儀袋や不祝儀袋の飾りに用いられるほか、近年ではアクセサリーやインテリアなど、現代の暮らしに合わせた新しい用途も開発されています。複雑で繊細な結びの技術は、水引の最大の魅力です。
(2)飯田の和紙と人形
飯田地方は和紙の生産が盛んであり、その和紙を素材とする工芸品も発達しました。
飯田和紙: 地域の伝統的な和紙製造技術は、水引の原料供給源として重要でした。
飯田人形: 和紙を素材とした飯田人形(いいだにんぎょう)は、素朴ながらも味わい深い人形であり、郷土玩具として親しまれています。また、現代に伝わる人形芝居の道具としても用いられています。
(3)和ろうそく
飯田市には、かつてろうそく製造を生業とする家が多くありました。
特徴: 植物性の油(ハゼの実など)を原料とし、手作業で丁寧に作られる和ろうそくは、すすが出にくく、炎が大きく美しいのが特徴です。現在も伝統的な技法を守る工房が残されています。
3.地域特有の食文化と信仰
下伊那の山間部は、厳しい自然環境を乗り越えるための知恵として、独特な食文化や信仰を育んできました。
(1)特産品と食文化
市田柿(いちだがき): 下伊那地域が発祥の地とされる干し柿で、地理的表示(GI)保護制度に登録されています。緻密な甘さと独特の食感が特徴で、飯田市市田地域がその名の由来です。
五平餅(ごへいもち): 木曽・伊那地方の郷土料理。ご飯を潰して串に巻き付け、胡桃や胡麻、醤油などをベースとした甘辛いタレをつけて焼いたものです。元々は、山仕事の際の携行食や神事の供物として用いられていたとも言われます。
ジビエ(野生鳥獣肉): 猪肉や鹿肉を利用する食文化は、山深いこの地域ならではの伝統的な食文化の一つです。
4.仏教文化と信仰
古刹(こさつ): 飯田市にある**開善寺(かいぜんじ)**は、室町時代に信濃守護・小笠原氏によって再興された禅寺であり、地域の文化、特に仏教美術において重要な役割を果たしてきました。
大平(おおだいら)宿: かつての三河街道の宿場町であり、山間部に位置しながらも重要な交通路として機能しました。宿場特有の文化や、信仰の道としての役割も担っていました。
長野県下伊那地域の伝統文化は、霜月祭りに代表されるように、神々を招き、共に過ごすという古代的な信仰形態を色濃く残しています。その上で、飯田水引のような高度な工芸技術を発展させ、厳しい自然の中での生活の知恵として五平餅や市田柿などの食文化を確立してきました。
地域を貫く天竜川と、周辺地域との文化交流が、下伊那の多様な伝統文化を形成してきたと言えるでしょう。これらの文化は、地域の人々の手によって大切に守り伝えられ、現在もなお生活に密着した形で息づいています。
(9)松岡城址
松岡城は南北朝時代争乱の頃築かれ、その後、戦国時代に大きな修復が加えられておよそ250年間松岡氏の本拠地となりました。松岡城は高森町の東南部、東方に天竜川を望む標高560メートルの段丘突端、西方は平地に連なる地に築かれた城です。城内は本丸を除く大部分が開墾されて田畑になっていますが、深く掘られた数条の堀跡は概ね現存しており、本丸・二の丸・三の丸・および惣構の各曲輪がはっきり残っています。松岡城の大きな特徴として、舌状の段丘先端から本曲輪。二の曲輪・三の曲輪・惣構と作られ、その間に第一~第五の堀を構えてこれが真直ぐに連なるという連郭式の典型的な城であることです。また、本城跡の残存状態は中世の段丘を利用した城跡としては県下で最も良いと言われています。































































































(10)市田柿発祥の里の石碑
長野県高森町の大丸山公園入口にある。この石碑は、市田柿のルーツが旧市田村(高森町)にあることを示しており、市田柿の歴史の長さを象徴している。
・場所:高森町大丸山公園入口(大丸山公園東交差点に面した場所)
・特徴:かなり大きな石碑
・意義:長野県南部で500年以上の歴史を持つ市田柿の発祥地であることを示している。












(11)市田柿の活用
1.柿渋染めの体験
岐阜県山県市にある柿BUSIさんにて柿渋染めの体験。
・達人の技が作る。旧伊自良村で130年受け継がれている伝統の干し柿。約1ヶ月天日干しした自然の甘みが感じられる。
・伊自良大実柿(いじらおおみがき)は世界で唯一、岐阜県旧伊自良村の北部にしか存在しない渋柿。この渋柿の皮をむき竹串に3つ挿したあと、わらで10段編むという方法でつくられる伊自良特有の干し柿を『伊自良大見連柿』という。
守り継がれる1000本の伝統。柿の木は500年伝わる。
・半世紀ぶりに復活した伊自良の柿渋
時代の変化と共に需要が減少し、半世紀前に途絶えてしまった『伊自良大見柿』の柿渋。人の情熱により復活した柿渋文化を継承していくため、柿BUSIは柿渋染めの魅力を伝えている。
・多くの手で未来へ繋ぐ
希少な柿を少しでも守っていくため使われなくなった柿畑を地域の方々から借りて管理。その畑の柿を柿渋の原料にしている。収穫の際は、各地から多くの方が力を合わせている。たくさんの人の手と心によって、伊自良の柿渋文化は未来へと守り続けられている。
・柿渋染め体験
自分が染めたいものを持ち込んで柿渋染めができる。日本で古来より伝わる染料を使って、オリジナルのものが作れる染色体験。
収斂作用
燻製剤 色とめ 鉄は青い
柿渋は固くなる
高森にも来た ドラマチック高森
市田柿はむいていなかった?
模様をつける
水に濡らす
柿渋に浸ける 3分
お湯に溶かした鉄に動かしながら浸す 10分
水で洗い、干す















































2.JA南信州 市田柿工房
住所:
長野県下伊那郡 高森町下市田2478-2
電話:0265-34-2010
最寄り駅:下市田駅[出口]徒歩19分









4.市田柿デジタルアーカイブの教材化
教材として、市田柿の栽培から加工までのプロセス、地域の歴史、伝統文化などを学べるデジタルコンテンツの作成
南信州を代表する特産品「市田柿」のデジタルアーカイブを、学校教育における教材として活用するための構想と具体的な実践方法について解説します。
市田柿デジタルアーカイブの教材化:地域と未来をつなぐ学びのデザイン
長野県南信州地域の冬の風物詩であり、地理的表示(GI)保護制度にも登録されている「市田柿」。その歴史、製造技術、景観、そして生産者の想いを記録した「デジタルアーカイブ」は、単なる資料の保存場所ではありません。これを学校教育の現場で「生きた教材」として活用することは、地域理解を深めるだけでなく、情報活用能力や課題解決能力を育む絶好の機会となります。
以下に、市田柿デジタルアーカイブを教材化するための視点と展開案を論じます。
1. 教材化の意義と目的
市田柿デジタルアーカイブを教材化する最大の意義は、**「暗黙知の形式知化」と「時空を超えた比較」**にあります。
かつては家族総出で行われていた柿作りも、分業化や農家の減少により、子供たちがその全容に触れる機会は減っています。デジタルアーカイブにある「古写真」「製造工程の動画」「生産者のインタビュー音声」は、子供たちが直接見ることのできない過去の風景や、熟練の技(例:柿の揉み込み加減や粉の吹かせ方)を可視化します。
教育的な目的は以下の3点に集約されます。
地域アイデンティティの醸成: 地域の誇りである産業を深く知る。
探究的な学びの深化: 一次資料(アーカイブデータ)に基づき、自ら問いを立てて解決する。
情報リテラシーの育成: デジタルデータの正しい取り扱いや著作権、発信の仕方を学ぶ。
2. 教科横断的なカリキュラム・マネジメント
デジタルアーカイブは、単一の教科にとどまらず、多角的なアプローチが可能です。
社会科・地理歴史(小学校・中学校)
景観の変遷と比較: アーカイブ内の昭和期の写真と現在の風景(Google Earthや実地調査)を比較させます。「なぜ天竜川沿いに柿の加工場が多いのか(川霧の影響)」、「土地利用がどう変化したか」を考察させることで、地形と産業の結びつきを理解させます。
農業と経済の歴史: 養蚕から市田柿へと地域の主力産業が移り変わった歴史的背景を、アーカイブ内の統計データや当時の文書から読み解きます。
家庭科・食育
保存食の知恵: 渋柿を甘くするメカニズムや、保存性を高めるための加工技術(硫黄燻蒸など)を学びます。アーカイブにある伝統的なレシピや食べ方の変遷を調べ、実際に調理実習に取り入れることも可能です。
情報科・総合的な学習の時間
デジタルアーカイブの構築体験: 既存のアーカイブを見るだけでなく、生徒自身が現在の市田柿の風景を撮影し、メタデータ(撮影場所、日時、説明)を付与して「未来のアーカイブ」を作る活動です。これにより、データベースの仕組みや情報の整理・分類の重要性を実践的に学びます。
3. 「探究学習」における具体的な活用事例
高校の「総合的な探究の時間」などを想定した、より高度な活用モデルです。
テーマA:ブランディングと地域創生
問い: 「市田柿を世界ブランドにするにはどうすればよいか?」 アーカイブに保存されている過去のポスターやパッケージデザインの変遷を分析させます。その上で、現代のトレンドや海外市場を意識した新しいPR動画やパンフレットを、アーカイブ素材(使用許諾の範囲内で)を二次利用して作成させます。これは、知的財産権の学習ともリンクします。
テーマB:担い手不足と技術継承
問い: 「熟練農家の『手触り』をどう継承するか?」 アーカイブにある「匠の技」の動画を細かく分析し、オノマトペ(擬音語・擬態語)や数値で言語化を試みる授業です。さらに、ICTを活用して農家の負担を減らす「スマート農業」の可能性について、過去の労働環境のデータと比較しながら提言をまとめます。
4. デジタルアーカイブ活用における課題と配慮
教材化にあたっては、以下の点に配慮が必要です。
著作権と肖像権の教育: アーカイブ内の写真を授業で使う場合や、生徒が加工して発表する場合のルール(クリエイティブ・コモンズ・ライセンスなど)を徹底して指導する必要があります。これは現代社会で必須のデジタル・シティズンシップ教育となります。
「実物」との往還: デジタルだけで完結させないことが重要です。アーカイブで事前学習をした上で、実際の農家を訪れたり、干し柿の匂いを嗅いだりする「リアルな体験」と組み合わせることで、学びの深度は何倍にもなります。デジタルはあくまで、リアルを深く理解するためのレンズとして機能させるべきです。
結論:アーカイブは「過去」ではなく「未来」の種
市田柿デジタルアーカイブを教材化することは、単に昔のことを懐かしむ活動ではありません。子供たちがアーカイブという膨大なデータの中から必要な情報を**「検索」し、歴史的背景を「分析」し、現代の課題解決に向けて「創造」**するプロセスそのものです。
地域固有の資源である「市田柿」を題材に、最先端の「デジタルアーカイブ」という手法を組み合わせることで、南信州の子供たちは「ローカルな視点」と「グローバルな技術(デジタル活用)」の両方を獲得することができます。この教材化の取り組みこそが、100年後の市田柿の風景を守り、次世代の担い手を育むための最も確実な投資となるでしょう。
「市田柿デジタルアーカイブ」を実際に授業で活用するための、**小学校高学年(5・6年生)〜中学生の「総合的な学習の時間」**を想定した学習指導案と、生徒用ワークシート案を作成しました。
この単元では、単に昔の写真を眺めるだけでなく、**「過去と現在を比較し、変化の理由を考察する(探究する)」**ことに主眼を置いています。
学習指導案:市田柿タイムトラベル 〜アーカイブから未来の地域を考えよう〜
対象: 小学校5・6年生 または 中学1年生 教科: 総合的な学習の時間(社会科とのクロスカリキュラムも可能) 単元時間数: 全6時間(本案は、中核となる第3時の展開案です)
1. 単元の構成(全6時間)
-
第1・2時:【現状把握】 市田柿の現在の製造工程を知る(見学や現職農家のお話)。
-
第3時:【調査・分析】 デジタルアーカイブを活用し、昔の市田柿作りを調査する(※本時)。
-
第4時:【考察】 昔と今の「変わったこと」「変わらないこと」を整理し、その理由を考える。
-
第5・6時:【発信・提案】 未来の市田柿を守るためのキャッチコピーやポスターを作成・発表する。
2. 第3時 学習指導案詳細
主題: デジタルアーカイブで「変化」の謎を解こう ねらい:
-
デジタルアーカイブから目的に応じた情報を検索・収集できる。(情報活用能力)
-
写真や動画から、当時の人々の工夫や苦労、地域の様子を読み取ることができる。(思考・判断)
生徒用ワークシート案
このワークシートは、アーカイブ探索(第3時)で使用するものです。
市田柿 探究学習ワークシート No.3
<u>年 組 番 氏名: </u>
テーマ:時空を超えて調査せよ!「昔の市田柿」報告書
デジタルアーカイブを使って、自分が気になった**「昔の様子(写真・動画)」**を1つ選び、現在と比べてみましょう。
1. 調査ターゲット(あなたが見つけた資料)
2. 「今」との比較(間違い探しレベルで細かく!)
3. 【重要】探偵の推理コーナー(なぜ、変わったのだろう?)
「2」で書いた変化には、必ず理由があります。想像力を働かせて推理してみよう。
4. 先生からのコメント(フィードバック欄)
(ここに先生が、生徒の「着眼点の良さ」や「推理の面白さ」を評価するコメントを記入します)
授業準備・運用のポイント
この教材化を成功させるための補足アドバイスです。
1. デジタル環境の確認
2. つまずく子への声かけ(スキャフォールディング)
3. 学びの深め方
このように、「アーカイブを見る」という受動的な行為を、「違いを見つけて推理する」という能動的なアクションに変えることで、教育効果は飛躍的に高まります。
タブレット端末(iPad、Chromebookなど)での使用に最適化した、横向き(ランドスケープ)レイアウトのワークシート構成案です。
タブレット学習では、縦長のA4プリントよりも、画面いっぱいに表示できる16:9の比率(PowerPointやGoogleスライドのサイズ)が最も操作しやすいため、その形式で設計しました。
【タブレット用】市田柿タイムトラベル調査票
この構成案は、PowerPoint、Keynote、Googleスライド、またはロイロノート等の授業支援アプリで作成する際の「設計図」としてご利用ください。
画面構成案(全体像)
推奨サイズ: 16:9(横向き) ターゲット: 小学校高学年〜中学生
■ スライド1枚目:調査と証拠の保全(検索・貼り付け)
このページは、アーカイブから見つけた画像を貼り付け、基本データを記録するページです。
■ スライド2枚目:比較分析(間違い探し)
このページは、左側の「昔」と右側の「今」を対比させ、気づきを書き込むページです。
■ スライド3枚目:考察(名探偵の推理)
このページは、思考を深めるための「まとめ」です。キーボード入力が苦手な生徒向けに、穴埋め形式を用意します。
教材作成・配布のヒント
この構成案を実際に授業で使うための具体的な手順です。
1. アプリ別の作成方法
2. デザインの工夫(ユニバーサルデザインの視点)
3. 次のステップ(すぐにご支援できること)
もし、PowerPoint (.pptx) 形式のテンプレートファイルとして、より詳細なレイアウト調整(枠線の配置や配色など)が必要であれば、具体的なスライドごとのテキスト配置案をコード(Markdown形式)で出力することも可能です。
5.結 言
参考資料