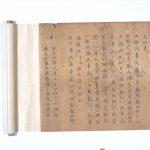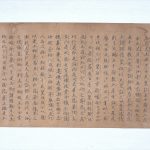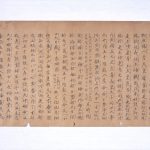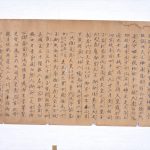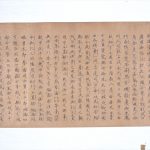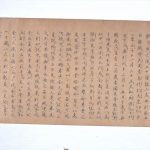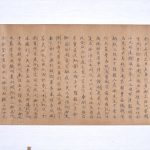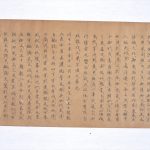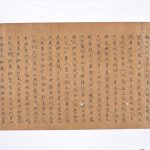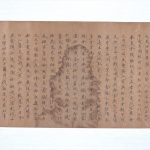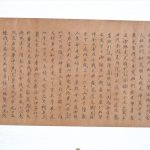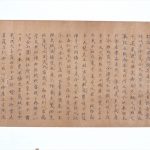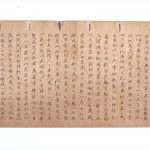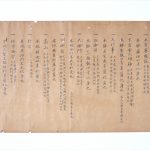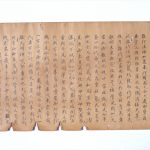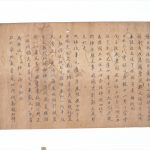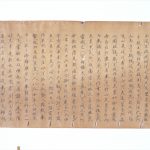龍峰寺
龍峰寺(りゅうぶじ、龍峯寺)は岐阜県岐阜市奥にある臨済宗妙心寺派の寺院で、山号は廣徳山。北方城主安藤守就の菩提寺である。
戦国時代に北方城主の安藤守就が、弟の湖淑を開山として一族の菩提寺として北方に建立した。正確な創建年は不明で、湖淑の法系も伝わっていない。その後、天正10年(1582年)に北方城が稲葉良通により攻められた際に城と共に兵火により焼亡した。湖淑は本巣郡の奥村まで逃れ、安藤守就の菩提を弔い寺院を再興した。湖淑和尚の没後は住持を欠くが、明暦年間に越前国報恩寺の別川和尚が住持となる。その法嗣、蜜外和尚は人里離れた山上から麓に寺を移した。天和3年(1683年)に乙津寺の鉄錐和尚を住持に招いたのちその法が受け継がれた。寺宝として湖淑和尚の肖像を所蔵し、安藤守就の墓が本堂裏手の山に建っている。
後背山栄昌院
栄昌院は、織田信長の妹であるお市の方と浅井長政との間に生まれた三姉妹のうち、次女の常高院(初)の菩提寺です。
初は、近江の名門で若狭国(福井県)小浜城主となった京極高次に嫁ぎました。寛永十年(1633年)に江戸で亡くなり、法名を常高寺殿松厳栄昌大姉といいます。常高院の没後、その側近く仕えた侍女七人が小浜にそれぞれ寺庵を結び、全体を栄昌院と号して、常高院の菩提をとむらいつづけました。
明治維新をむかえたとき、尼僧たちは小浜から京極家の領地であった丸亀(香川県)に移りましたが、明治初期に京極家が祭祀を仏式から神式に改めたため、常高院の位牌とともに尼僧が美濃国方県郡佐野村(岐阜市)へ来住し、栄昌院を復興したのです。
境内には常高院の供養塔とともに、寺を守ってきた歴代の尼僧たちの供養塔が建っています。
また、ドラマでも有名となった、三姉妹の三女の江から初にあてた手紙が見つかったことから栄昌院は一躍脚光を浴びました。
八幡神社・日吉神社
日吉神社社殿は、隣接する八幡神社とともに当初より数度の補修、屋根葺替えが施されており、日吉神社社殿は昭和38年(1963)に解体修理が行われた。現在、勾欄[こうらん]、縁束、板壁、浜床[はまゆか]、破風板の一部が取替えられているが、その他の部材は当初のもので解体修理に取替えられた部材の内、当初のものはすべて各社の小屋裏内に保存されている。この解体修理のほか、数度の補修においてもよく当初の形式、手法が踏襲されてきている。
部材は長年の風雪により著しく風化しているが、虫害は比較的僅少で桃山時代の技風を示す蟇股[かえるまた]の牡丹、鴛鳥等の彫刻も一部破損はしているが原形を保っており、また、時代の特色を表わす妻飾、組物[くみもの]の彫刻も優れたものが残存していることから、建築年代は桃山時代末と思われる。
護国之寺
護国之寺(ごこくしじ)は、岐阜県岐阜市にある高野山真言宗の寺院である。
山号は雄総山(ゆうそうさん)。
本尊は十一面千手観世音菩薩。
美濃三十三観音霊場第十七番札所。美濃四国札所八十八番。美濃七福神(布袋尊)。国宝の金銅獅子唐草文鉢をはじめ、数多くの岐阜県、岐阜市指定重要文化財がある。
伝承によれば、746年(天平18年)、聖武天皇の勅命により行基が開山したという。この寺の開山に関しては、奈良の大仏造立に関わった「日野金丸」(ひのきんまろ)の伝説がある(後述)。
1590年(天正18年)、兵火により焼失する。江戸時代、再建が順次行われた。現在の建物は元文 – 宝暦年間の建立である。
上記の鉢に関して次のような伝承がある。聖武天皇は東大寺の大仏を造立するため、優れた仏師を探すための使者を日本各地に派遣する。その中で、美濃国に派遣された使者が芥見(現在の岐阜市)の願成寺に滞在した時、夢の中で、「明日の朝、最初に出会った人物が探している人物である」とのお告げを聞く。翌朝、美濃国雄総(現在の岐阜市)で使者が出会ったのは、川で牛を洗っていた日野金丸(ひのかねまろ)という童子であった。使者の前で、金丸はその場で粘土で仏像を作る。その出来の良さから使者は金丸を奈良へ連れて行く。金丸は大仏建立の責任者として活躍する。
大仏落慶法要の最中、突然、紫雲が現れ、空から音楽が流れ出した。そして空中から鉢が現れた。空から「釈尊がこの大仏造立の功績をたたえ、釈尊由来の鉢を授けることとなった」という言葉が聞こえてきた。聖武天皇は功績のあった日野金丸にこの鉢を授けた。金丸はこの鉢を納めるために、故郷に護国之寺を建立したという。日野金丸は死後、十一面千手観世音菩薩像となり、護国之寺の本尊となったとも伝えられている。
金丸については、次のような言い伝えもある。1970年代、この辺り(岐阜市日野)の郷土史について研究していた教師(山田)の話によると、金丸(金王丸)は護国之寺と長良川をはさんだ南(左岸)側にある日野(昭和初期までは右岸側の一部も日野村であった)の童子(故に日野金丸)で、お坊様(使者)が来た時に作った仏像は田んぼの土で作ったということである。大仏建立に貢献し授かった鉢を、初めは地元に建てたお堂に納めていたが、長良川の出水時に流されそうになったことから、対岸の高台に移したという。また、お堂があったとされる地区は、今でもその時の名残から堂後(どううしろ)と呼ばれている。
【県】護国之寺宝篋印塔
雄総山護国之寺は、天平時代に創建されたと伝えている古刹である。
この塔は、自然石の上面を平らにした台石上に置かれ、基礎・台座・塔身・笠・相輪の五石からなる。銘文から、この塔が願主の近縁者供養のために建立されたことが伺える。台座や塔身の高さと幅との比率や笠の構造、また方立ての型式や外傾の度合などから、銘文の嘉元2年(1304)、14世紀初めごろの建立とみられる。
美濃地方に現存する在銘の宝篋印塔としては、最も古いもののひとつであり、また大型の塔として、その保存状態も比較的良好で、貴重なものである。
岐阜別院
本願寺岐阜別院(ほんがんじぎふべついん)は、岐阜県岐阜市にある浄土真宗本願寺派(西本願寺)の寺院(別院)である。開基は准如上人。
岐阜市には、東西両別院がある。真宗大谷派(東本願寺)の別院は、真宗大谷派岐阜別院。
1570年~1590年頃、本願寺11世顕如上人が美濃国に巡教の折に、美濃国厚見郡西野(現岐阜市西野町)の土豪、一柳直高(一柳直末、一柳直盛の父)が信徒となって帰依する。一柳直高の没後、その墳墓のそばに一寺が建立されたことが始まりと伝えられている。
1603年(慶長8年)、准如上人が当地を巡教した際に、一柳直盛が父の一柳直高の遺命により申し出、この寺は本願寺の坊舎とされ、岐阜御坊もしくは西野御坊と呼ばれる[1]。
1876年(明治9年)に名称を岐阜別院と改められる[1]。
本堂は、1645年(正保2年)には再建されるが、1713年(正徳3年)全焼、1720年(享保5年)に再建されるが、1945年(昭和20年)7月9日、岐阜大空襲により山門、鐘楼、経蔵等を除く本堂などが焼失する。現在の本堂は1951年(昭和26年)の再建である。
1975年(昭和50年)、岐阜市芥見南山3丁目に「岐阜別院芥見分院」が建立される。
【県】岐阜別院本門
宝暦6年(1756)の建立で、門の形式は4脚門に属し、様式はほぼ唐様[からよう]の様式を用い、屋根入母屋造[いりもやづくり]本瓦葺、規模はこの種の4脚門としてはまれにみる大型なものである。中心部の柱は円柱、その他は角柱を用い、柱下には唐様特有の石製礎盤をおき、虹梁[こうりょう]・頭貫[かしらぬき]の木鼻[きばな]には唐獅子・象鼻などの彫刻を施し、頭貫下の幕板には波形の彫刻を入れ、台輪[だいわ]には飾金具を打ち、門の中心柱両脇の腰羽目・欄間などにも菱組みの欄間、貫下には花狭間[はなざま]の彫刻を用いている。中央間両開き桟唐戸上部幕板にも桐その他の彫刻を入れるなど荘厳さをましている。組物は二手先[ふたてさき]詰組尾垂木[おたるき]入り・二軒扇垂木[ふたのきおうぎたるき]、両脇には左右対照にほぼ前記同様の脇門を設けるなど正に豪華なものである。なお、この門は総欅で、彫刻装飾の多彩なことなど、よくこの時代の特徴を表している。
【県】岐阜別院裏門
寺伝は北方陣屋の冠木門を移築したという。建立年代は明確ではないが、寺伝のいうように元禄頃とみるべきであろうか。構造的には棟門に属し北方陣屋にもこの種の門は数少なく、歴史的にみて、貴重な存在である。
阿弥陀寺
阿弥陀寺(あみだじ)は、京都市上京区にある浄土宗の寺院。山号は蓮台山。院号は総見院。本尊は阿弥陀如来。織田信長の墓があることで知られる。
天文24年(1555年)に浄土宗の玉誉清玉が、近江国坂本に創建したのが当寺の始まりである。その後、清玉は自身と縁のある織田信長からの帰依を得ると、上京の今出川大宮に寺基を移す。
天正10年(1582年)6月2日に信長が本能寺の変で自害すると、清玉は自ら合戦中の本能寺に赴いて信長の遺灰を持ち帰り、墓を築いたとされている。後に織田信忠の遺骨も二条新御所より拾い集め、信長の墓の横にその墓を作ったという。さらに本能寺の変によって討死した名の分からぬ多数の犠牲者も当寺に葬って供養したという。
天正13年(1585年)に豊臣秀吉の京都改造により現在地に移転した。
延宝3年(1675年)11月25日に火災にあい、信長の木像、武具・道具類などの遺物が焼失した。焼け残ったものは大雲院に移されたが、同院でも再び火災にあって今ではほとんど残っていない。
美作国津山藩の4代藩主森長成は毎年6月2日に法要をし、信長公百年忌も執り行ったというが、森家の改易後は御茶湯料の寄進はなくなったとする。
1917年(大正6年)に勅使が来訪し、当寺の信長の墓は「織田信長公本廟」として公認された。
延算寺
延算寺(えんさんじ)は、岐阜県岐阜市にある高野山真言宗準別格本山の寺院である。山号は岩井山。本坊と東院とは500m程離れている。ここでは本坊と東院の双方について記述する。
本坊の本尊は薬師如来。別名を「たらい薬師」という。東院の本尊は薬師如来。別名を瘡神薬師(かさかみやくし)という。美濃四国札所であり、延算寺東院は八十番札所。延算寺本坊は八十五番札所。皮膚病に利益があるといわれ、東院には皮膚病に効果があるという霊水がある。
伝承によれば、815年(弘仁6年)、空海がこの地で霊水を見つけ、薬師如来を祀ったのが起源であるという。
地元に伝わる昔話によると、805年(延暦24年)、唐から帰国した最澄が因幡国岩井郡岩井に滞在し、クスノキで3体の薬師如来像を彫り上げた。そのうち一体が空を飛び、美濃国岩井で座禅を組んでいた僧侶の前に現れたという。驚いた僧侶は像をお祀ろうとしたが粗末な仏堂しか造れず、地元の農民が用意した新しい盥の上に安置したという。このことから、「たらい薬師」と呼ばれるようになったという。空海がこの地を訪れた際、この薬師如来をお祀りする寺を建立し、薬師如来を盥の上に安置した僧侶は空海の弟子となったという。
864年(貞観6年)、定額寺となる。
昌泰年間頃、天然痘(皮膚病の説あり)を患った小野小町が、お告げにより疱疹、瘡を直すために延算寺に7日間こもる。夢で「東に霊水がある。その水を体にすり込むと良い。」とお告げを聞き、その水をすり込むと完治する。この際、その霊水に延算寺の薬師如来を模した石仏を祀ったという。これが東院の始まりであると伝えられている。
かつては大規模な伽藍であったというが、幾たびかの戦火で焼失する。現在の本堂は1643年(寛永20年)再建である。
【研究論文】岐阜和傘の歴史と技術のアーカイブ
〜岐阜市文化資源デジタルアーカイブの構築〜
研究概要
1,はじめに
卒業研究のテーマを決める中で、現在住んでいる岐阜市について関心を持ち、岐阜市を知っていく中で岐阜県の伝統工芸品である岐阜和傘を初めて知り、岐阜市にはまだあまり知られていない伝統工芸品があるかもしれないと考え、そこから若い世代や知らない方に岐阜和傘を知ってもらえる様にデジタルアーカイブを通して伝えたいと考えた。本研究では、岐阜和傘の技術と歴史を中心に、岐阜和傘以外の伝統工芸品と長良川の関係性をアーカイブし、より多くの人に伝える事が本研究の目的である。
2,研究の方法
研究対象である岐阜和傘とその他の伝統工芸品の歴史や技術などの資料を集め、文献調査を行う。次に、文献調査で分かった事をまとめ、分析しまとめていく。文献調査だけでなく岐阜和傘の資料や岐阜和傘に関連する施設などを実際に訪問し、撮影をさせてもらう。文献調査や撮影などを基にデジタルアーカイブを作成し、活用の方法とデジタルアーカイブをする事の意義を考察、提案する。
3,研究の結果(考察等)
本研究では、最初に岐阜和傘の歴史やその他の岐阜市の伝統工芸品の歴史・技術を知る為に文献調査を行った。そこから分かった岐阜市の伝統工芸品の共通点として長良川に沿って伝統工芸品が生まれている事が調査で分かった。
長良川は、岐阜県北部の大日ヶ岳から南へと岐阜県内を横断し、三重県桑名市で揖斐川に合流し、伊勢湾へと流れ込む。全長は166kmで、流域には、86万人が暮らしている。長良川は江戸時代では、物流の手段として使われていた。長良川は、伊勢までたどり着く事から関西から関東まで荷物を運ぶ事ができ、物流の要として使われていた。その為、出来た品物や材料などが手に入れやすい事から長良川の流域で数多くの伝統工芸品が生まれた。
その事から、岐阜和傘・岐阜うちわ・岐阜提灯の関係性が分かった。また、長良川の役割や歴史を知る事で、岐阜和傘の成り立ちと深く関係している事が分かった。
また、文献調査を進めるにあたって岐阜市和傘の現状の課題点が見えてきた。昨今は、和傘よりも洋傘が主流となっており、和傘の需要が減少しており、最近では舞台での小道具や結婚式の前撮りの小道具として使われる事が多くなった。そこで若い世代の方にも和傘をより身近に知ってもらう為にもデジタルアーカイブを通して岐阜和傘の歴史と技術を知ってもらう事が需要だと考える。その為に現在は、岐阜和傘に関連する場所や施設などを撮影し、ネットに上げる事を行っている。また、文献調査も並行して行う。
4.おわりに
岐阜和傘の普及の為に様々な取り組みが行われてきているが、現状はまだ若い世代に「岐阜和傘」の普及がないと考える。若い世代に「岐阜和傘」を知ってもらう為にもインターネットを通して、「岐阜和傘」の普及に努める。Mata,
関連の場所での撮影が出来ていないので、撮影を重点的に行いながら、岐阜和傘の歴史や技術、長良川の伝統工芸品の関連性と歴史の文献調査を行っていく。
参考文献
(1)岐阜傘に関する調査研究
(2)加納町史 下巻
(3)密柑水の文化センター 機関誌『水の文化』50号「江戸時代から続く岐阜・加納の和傘づくり」
https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no50/05.html
(4)和傘CASA
研究資料
岐阜和傘の歴史
・岐阜和傘の成り立ち
1756年(宝暦6)、加納藩主・永井直陳は下級武士の生計を助けるため和傘づくりを推奨した。岐阜で和傘を製造するにあたって、分業体制の確立に加え、美濃和紙の生産地に近く、周辺の山間地で良質の竹が採取できるなどに加えて、加納は位置的にも原材料に恵まれた事もあり、加納の和傘は栄え、最盛期の昭和20年代半ばには年産100万本を超えている。
・岐阜和傘と長良川
岐阜和傘を搬送するにあたって、長良川は大きな役割を果たした。搬送経路としては、長良川から伊勢湾の桑名に出て、廻船によって江戸・大阪などの大消費地へと搬送する事が可能となったため、広範囲に和傘を販売することができ、岐阜和傘が栄えた一因となった。
岐阜和傘とは?
・岐阜和傘の特徴
岐阜和傘は、畳むと細く収まる傘「細物」を特徴として、傘の製造に優れた技術を有し、豊富な装飾技法を継承している。
・和傘の種類
「蛇の目傘」→細みかつ色柄が豊富で女性が使用する事が多い
「番傘」→太めの骨や白の和紙で作られる男性用で、雨傘としても作られ、
わしには水除けの油が引かれる。
「舞踊傘」→日本舞踊や歌舞伎などで使われる
「野点傘(のだてかさ)」→野外のお茶会などで使われる
など様々な和傘が存在している。
・岐阜和傘が認められて…
2022年3月には、国の伝統的な工芸品に推定されている。
岐阜和傘の現状と課題
・岐阜和傘の今
現在、岐阜和傘を製造販売するのは加納地区に3件のみとなっている。最盛期だった頃と比べ、洋傘の普及に伴い、需要が減り、今の岐阜和傘の主な収入源としては、歌舞伎や日本舞踊などでの貸し出しや結婚式での貸し出しが主となっており、和傘を普段使いの傘として買う人は減少している。岐阜和傘は一つ一つが手作りで分業制で出来ているからこそ一本一本の値段が洋傘に比べると高く、中々手に届かないのも一つの原因となっていると考えられる。
⇓
その現状を打破しようと様々な事が取り組まれてきている。最近だと岐阜市に岐阜県で唯一の和傘専門店である「CASA和傘」というショップが出来た。このショップでは「岐阜和傘」をブランド化し、現代に合わせ、洋服に合うデザインの岐阜和傘を店頭やオンラインショップ等で販売している。また、公式のホームページでは買った方の写真や感想などが掲載されていたり、岐阜和傘の種類等も掲載されており、和傘をより身近に普段使いしやすいサービス等が提供されている。
研究内容(仮)
岐阜和傘の普及の為に様々な取り組みが行われてきているが、現状はまだ若い世代に「岐阜和傘」の普及がないと考える。若い世代に「岐阜和傘」を知ってもらう為にもインターネットを通して、「岐阜和傘」の普及に努める。
◎岐阜和傘の歴史と人をアーカイブする
⇒「岐阜和傘」はどういう物なのかどの様な歴史なのか、今現在どの様に作られているのか作っている人をアーカイブし、公開する事で岐阜和傘について知ってもらう。
(例)職人の方の作業風景やインタビューを行いアーカイブする
岐阜和傘や岐阜の伝統工芸品にまつわる資料などをアーカイブする
◎岐阜和傘を通して長良川周辺にある伝統工芸品についても調べ、マップにする
⇒長良川周辺で生まれた岐阜うちわや岐阜提灯などを調べ、紙のマップにしたり、ウェブでのマップを作成する
(例)そこにある伝統工芸品についての歴史や豆知識などをタップして見れるようにする。
資料
論 文
岐阜和傘の歴史と技術のアーカイブ
〜岐阜市文化資源デジタルアーカイブの構築〜
第1章 緒 言
1. はじめに
卒業研究のテーマを決めるにあたって、現在住んでいる岐阜市について関心を持ち、岐阜市を調べていく中で、岐阜県の伝統工芸品である岐阜和傘が岐阜市で作られてきたことを初めて知った。岐阜和傘の技術と歴史をもっとより多くの人に知ってもらいたいと考えた。また岐阜和傘以外にもまだあまり知られていない伝統工芸品があるかもしれないと考えた。そこから調べてく中で岐阜うちわ、岐阜提灯の2つがある事が分かった。この二つの伝統工芸品と岐阜和傘の成り立ちなどを調べていく際に、この3つとも長良川付近で作られている事が分かった。そこから若い世代の方や知らない方に岐阜和傘や岐阜和傘以外の伝統工芸品を知ってもらえる様にデジタルアーカイブを通して伝えたいと考えた。本研究では、岐阜和傘の技術と歴史を中心に、岐阜和傘以外の伝統工芸品と長良川の歴史的関係性を調査し、デジタルアーカイブを通じてより多くの人に伝える事が本研究の目的である。
2. 岐阜和傘の歴史的変遷
上記でも述べた通り、岐阜和傘をより多くの人に知ってもらう事が本研究の目的である。岐阜和傘は最盛期の1950年頃は600件以上の問屋があり、月に120万本から130万本まで生産されていた。しかし、現在は職人の高齢化や後継者が少なく、お店を畳む人が多く岐阜和傘を扱うお店も全盛期より大幅に減った。また、もう一つの原因として挙げられるのは、洋傘の普及だ。昭和20年頃日本は敗戦し、終戦を迎えた。それに伴い生活様式が大きく変わった。和傘の需要低下が本格的に進んだのは、終戦直後の昭和23年~25年をピークに急激に落ち込んだ。その背景としてあるのは、生活様式が変わった事に伴い、洋傘の普及が始まった事が和傘の需要低下に拍車をかけた一つだ。その他にも、服装の変化として、着物から洋服へと変わった事、交通機関の発達、なども挙げられる。また物資不足だったのも原因の一つと考えられる。そして、昭和30年には洋傘の生産と和傘の生産が逆転し、急激に低下した。現代においても、傘というと洋傘の方が日常使いのイメージが強い。一本一本人の手で作られており、単価が高く手に出しにくい。しかし、洋傘の場合は大量生産に適しており、単価も安いものから高いものまである。また、洋服に和傘は合わせづらいという事もある。これは和傘が洋傘よりもデザインの幅がない事が原因だと私は考えている。この様に和傘は現代の生活様式には合わなくなっている。また和傘を作っている会社のホームページはあるが、岐阜和傘について作られたサイトは少ない印象がある。この岐阜和傘での問題は他の岐阜市の伝統工芸品出も同じだと考えている。今回取り上げる岐阜うちわ、岐阜提灯でも現代の生活様式に合わず、生産量なども最盛期に比べると随分減った。岐阜和傘を中心に岐阜市の伝統工芸品をより多くの人に知ってもらえる様にするには、インターネットの活用が最適と考えた。そこで、デジタルアーカイブを用いて、岐阜市の伝統工芸品の和傘について歴史的変遷と共に周知する事が問題の解決だと考える。
3.目 的
本研究の目的は、「岐阜市の伝統工芸品をより多くの人にデジタルアーカイブを用いて知ってもらう」事だ。岐阜市には伝統工芸品が数多くある。本研究では、岐阜和傘の技術と歴史について、デジタルアーカイブを中心に岐阜うちわ、岐阜提灯と長良川の関係性をアーカイブしていく。
第2章 岐阜市の歴史
1.岐阜市について
岐阜市は、岐阜県の県庁所在地であり、人口は42万人で、岐阜県の市町村の中で一番多い人口だ。パーセンテージで表すと、岐阜県の20%が住んでいる。の主な産業としてはアパレルが挙げられる。市内中心部を清流長良川が流れており、金華山がそびえている。歴史も長く、岐阜市が歴史に登場したのは旧石器時代で、最初は岐阜市の北部から東部にかけた台地上に営みがあり、縄文、弥生、古墳時代にはほぼ全域に営みは広がっていった。その証拠として、紀元前1300年頃の石器や遺跡などが見つかっている。応仁・文明の頃には、斎藤道三が美濃国を手中にして、井口と呼ばれた稲葉山山麓に城下町を形成。永禄10年には、織田信長が美濃国を手中にし、「井口」から「岐阜」と改めた。その後、「楽市楽座」を行い城下町を発展させた。その後は合併が繰り返され、今の岐阜市が出来たのは1889年(明治22年)7月1日、その後2006年に柳津町と合併し、2019年に130周年を迎えた。本研究では、岐阜市の伝統工芸品を紹介してきたが、岐阜市には他にも様々な伝統文化や産業がある。その一つとして、岐阜市の伝統文化である長良川の鵜飼がある。長良川の鵜飼は、その歴史と伝統に培われた技術が評価され、国の重要無形民俗文化財に指定されている。また岐阜市を代表する産業として、アパレル産業が挙げられる。岐阜市のアパレル産業は満州から引き揚げられた人達が中心に軍服を売る店を立ち上げ、そこから発展していき、日本でも有数のアパレルの産地となった。また、岐阜市には様々な史跡が残されている。城の跡地が残っている所もあり、金華山の上にそびえる岐阜城跡は、岐阜城を含む金華山一帯が「岐阜城跡」として国史跡に指定されている。国史跡とは、日本の歴史を正しく判断する上で欠く事が出来ない遺跡の事であり、岐阜城跡地は岐阜市内の国史跡としては4件目に登録された。岐阜市は岐阜県の中心地として栄えながらも伝統と歴史のある町であり、自然にも恵まれている。
2.岐阜市の伝統工芸品について
岐阜県には、国の指定を受けた伝統的工芸品が6品目あり、その中の2つの伝統的工芸品は岐阜市にある。岐阜市には5つの伝統工芸品があり、内訳としては、国から指定された伝統的工芸品は、岐阜提灯、岐阜和傘の2つで、岐阜県から指定された郷土工芸品は、岐阜渋うちわ、のぼり鯉・花合羽、美濃筒引き本染め・手刷り捺染の3つが指定されている。本研究では、この5つのうち岐阜和傘、岐阜提灯、岐阜うちわについて取り上げていく。まず伝統工芸品とはどの様なものかを説明していく。一般には伝統工芸品と言われる事が多いが、それとは別に「伝統的工芸品」という呼称がある。伝統的工芸品は「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)」(以下から「伝産法」と略す)で定められている。この伝統的工芸品の「的」には、「工芸品の特長となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されていて、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品」の意味が含まれている。「伝統的工芸品」には、法律上で次の要件が必要になる。
・主として日常生活で使われるもの
冠婚葬祭や節句などのように、一生あるいは年に数回の行事でも、生活に密着し一般家庭で使われる場合は日常生活に含まれる。
・製造過程の主要部分が手作り
すべて手作りでなくてもよいが、製品の品質、形態、デザインなど製品の特長や持ち味を継承する工程は「手作り」が条件だ。持ち味が損なわれない様な補助的な工程には、機械を導入する事が可能だ。
・伝統的技術または技法によって製造
伝統的とはおよそ100年間以上の継続を意味する。工芸品の技術、技法は、100年間以上、多くの作り手の試行錯誤や改良を経て初めて確立すると考えられている。伝統的技術、技法は、昔からの方法そのままではなく、根本的な変化や製品の特長を変えることが無ければ、改善や発展は差支えない。
・伝統的に使用されてきた原材料
「伝統的技術または技法によって製造」と同様に、100年間以上の継続を意味し、長い間吟味された、人と自然にやさしい材料が使われているか。またすでに枯渇したものや入手が極めて困難な原材料もある場合は、持ち味を変えない範囲で同様の原材料に転換する事は、伝統的であるとされている。
・一定の地域で産地を形成
一定の地域で、ある程度の製造者があり、地域産業として成立していることが必要。ある程度の規模とは、10企業以上または30人以上が想定されている。
以下の要件を全て満たし、伝産法に基づいて経済産業大臣の指定を受けた工芸品の事を指す。今回取り上げる岐阜提灯、岐阜和傘は伝統的工芸品で、岐阜うちわは郷土工芸品に分類されているが、3つとも伝統工芸品である事には変わらないので、ここでは3つとも伝統工芸品と呼称していく。それでは、いつ伝統的工芸品と郷土工芸品について指定されたのかというと、岐阜提灯は平成7年4月5日、岐阜和傘は令和4年3月18日に伝統的工芸品として岐阜渋うちわは平成4年3月30日に指定されている。
3.岐阜市加納地域に地域性
加納の地名の由来は、荘園が誕生した時代に盛んぼる。荘園とは、功績のあった貴族やお寺に与えた土地が荘園である。今の茜部には茜部の荘という東大寺の荘園があり、その荘園の管理者は、荒地を開墾し、その土地を国に言わずに自分の土地にして、年貢を手に入れていた。しかし、隣の荘園との境にぶつかると、正式に権限が欲しいため、開墾した土地を正式に届出を出し、そこから国に年貢の一部を納めた。その様な経緯から、元の荘園に後で加えて納めたことから「加納」という地名が出来た。加納は岐阜県稲葉郡に存在した町で旧城下町でもあった。加納城が出来たのは、1600年11月出来ヶ原合戦後、家康は西方の脅威に備え、交通の要衝を理由に加納城の築城を命じられ、加納城が築城された。加納城初代城主には奥平信昌が任されたという。また、加納は加納城が築城する前は、中山道の宿場町としても栄えた。中山道は、1601年から7年間で他の4街道(東海道、日光街道、奥州街道、甲州街道)とともに整備された会堂であり、古くは都と東国を結ぶ東山道と称されていた。加納宿は守山宿から東海道の草津宿を経て京都三条に大橋に至ると69の宿があり、そこまでを「木曽路69次」とも言われている。美濃路には16宿が設けられていて、そのうちの最大の宿だと加納宿は言われていた。加納は加納城を中心に、侍屋敷と宿場町から成り立っていた。侍屋敷は加納城周辺(丸の内,東西の丸,長刀堀等)で、宿場町は本町一丁目~九丁目,天神町,広江,新町,柳町,安良町,八幡町等22町からなっていた。()そこから明治16年には、東加納町と西加納町が確立。その後、明治30年には、東加納町と西加納町、下加納町が合併し、加納町となった。その後、昭和に入り、加納町は岐阜市と合併した。加納の特産品としては、岐阜和傘があり、加納に数多くの国に指定された史跡が残っている。加納城だけでなく、加納宿、加納天満宮、加納八幡神社などがある。加納天満宮は、祭神は菅原道真公で加納城が築城される前から祀られていた古社で、慶長年間に現在の場所に移設された。加納天満宮は、学問の神様としても有名で、戦炎で焼け残った拝殿は、文化7年創建され、三十六歌仙,六歌仙,等の宝物や市文化財指定の山車(鞍馬車)があり、天神祭りやみそぎまつり、提灯まつりなどが開催されている。平成15年10月には、御鎮座400年と官公御神忌1100年の記念事業として本殿造営工事がされた。また、町政時代の名所として、1962年に竣工された旧加納町役場が存在しており、武田五一設計で、鉄骨鉄筋コンクリート造2階建ての近代建築で、国の登録有形文化財にも登録された。しかし、耐震性の問題などから2016年に取り壊され、その跡地は現在中山道加納宿まちづくり交流センターとなっている。この中山道加納宿まちづくり交流センターでは、加納宿を中心とした中山道の歴史の継承を図り、地域のまちづくりの活動の場という役割で令和2年10月14日に開館した。屋内には和傘や加納城のジオラマなどの展示が展開されており、街歩きなどで中山道を訪れる方へのトイレの提供や休憩スペースとしても利用が出来る様になっている。この様に加納を知る事ができる施設もある。また、旧加納町役場以外にも加納小学校の正門は、赤いレンガ造りが有名で「赤門」と呼ばれており、明治32年4月の開港同時に設置された。市内最古の門であり、平成7年10月には「岐阜の宝百選」にも選ばれた。加納は、1940年の1月23日に岐阜市への編入案が可決されたが、編入案が可決する条件として、岐阜駅、東海道本線下に地下道を設ける事、「加納」という地名を残すことを提示した。この条件を承諾した事で、岐阜市に編入した今も加納という地名は残っている。
4.長良川という自然環境
長良川は、岐阜県北部の大日ヶ岳から南へと岐阜県内を横断し、三重県桑名市揖斐川に合流、伊勢湾へ流れ込む。その全長は166kmで、流域には86万人が住んでいる。高知県の四万十川、静岡県の柿田川と並んで日本三大清流と言われており、名水百選にも選ばれている。また、長良川は上流約1㎞の水浴場があり、全国で唯一河川の水浴場として、「日本の水浴場88選」に選定されている。また、長良川にはダムや工場群が無く、水の美しい川として有名だ。長良川は水が美しい清流の為、鮎を中心に川の魚が良く捕れる。鮎は、澄んだ川の象徴と言われている。夏を告げる旬の魚だ。柳の葉のようなスリムな体をしていて、鮎の身からスイカの匂いが漂う為に「香魚」とも呼ばれる事もある。鮎は北海道から沖縄まで生息していて、澄んだ清流を好む。また、鮎は「年魚」とも呼ばれ、一年で命を閉じる。
おいしい鮎が育つためには、エサとなる上質なコケ(藻類)が必要となる。太陽光線 がコケ(藻類)の生える石まで届けばコケが豊富に育つが、泥や落ち葉などのゴミに遮られるとあまりコケは育ちにくい。しかし、長良川は、本流にダム(河川法で規定される高さ15m以上のモノ)が無く、大雨で自然に川の底が洗われやすいため、コケ(藻類)が育ちやすい環境にある。また、鮎は1日あたり自分の体重の半分の重さのエサを食べる。その為、鮎は縄張りを作るのは、他の鮎からエサ場を守る為だという。その為、たくさんの鮎が育つには、広範囲に美しい川が必要となる。また、鮎のエサとなるコケは、水中の二酸化炭素や窒素、リンなどを吸収し、水を綺麗にする役割がある。鮎がコケを食べる事で、次々に新しいコケが育ち、水を綺麗にし続ける。この循環がある事で、長良川の水の美しさを保ち続けることが出来る。鮎は水を綺麗に保つ役割を果たしている。長良川は、宮内庁の御魚場が定められていて、鵜飼の鵜匠が捕った鮎は皇室や伊勢神宮へ納められている。鮎の他にも、長良川の流域には、伝統工芸が多くある。
5.美濃和紙との関係性ついて
本研究でも取り上げている岐阜和傘や岐阜提灯、岐阜うちわ以外にも様々な伝統工芸がある。例えば、「美濃和紙」もその一つだ。美濃和紙の紀元はおよそ1300年前、天保9年(737年)ころで、奈良時代の「正倉院文書」の戸籍和紙が美濃和紙であったことが記されている。美濃和紙の原材料は、和紙の原料となる落葉低木楮、三椏、雁皮で、幹を使うのではなく、皮の部分の繊維を利用する。そして、良質の冷たい水が豊富にある事が、和紙を作る上で大事になってくる。美濃市は、その2つが揃っており、都からも近い場所だった為、和紙の産地として栄えた。
民間でも広く和紙が使われるようになったのは、室町・戦国時代の文明年間以後だった。美濃の守護職土岐氏は、製紙を保護推奨、紙市場を大矢田に開いた。紙市場は、月に六回開かれていたため、六斎市と呼ばれていて、現在も行われている。この紙市によって、近江の枝村商人の手で、京都、大阪、伊勢方面へ運ばれ、美濃の和紙が全国に知られるようになった。そして、慶長5年に徳川家康からこの地を拝領した金森長近は、長良川河畔に小倉山城を築城した。
慶長11年には、現在も残る町割りが完成した。こうして江戸時代には藩の保護や一般需要の増加もあり、美濃和紙は、幕府・尾張藩御用達となっていった。明治維新により、紙すき業に必要だった免許の制限がなくなり、製紙業が急増し、国内の需要や海外市場の進出などもあり、美濃は紙と原料の集積地として栄えた。しかし、濃尾震災と太平洋戦争の影響で、物資不足、人材不足などが生産に大きく影響し、陰りを落とすようになった。その影響は大正時代にも続いて行く。機械抄きが導入し、戦後には石油化学製品の進出が続いた。美濃では日用品を主とした素材を中心に生産していたため、打撃が大きく、昭和30年には、1200戸あった生産者が、昭和60年では40戸に減ってしまった。現在では、20戸程度になっている。美濃和紙は機械で漉く和紙を含め、美濃で作られた和紙全般を指す。
美濃和紙の中でも重要文化財指定の材料、道具を使い認められた職人が漉いた和紙のみ「本美濃和紙」と呼ぶことが出来る。上品な色合いや、薄くても布の様に丈夫で太陽の光に透かした時の美しさから。本美濃和紙は江戸時代以来最高級の障子紙として高く評価されてきた。美濃和紙の長い歴史の中で伝統の技が受け継がれてきたことなどが評価され、本美濃和紙は、昭和44年に国の重要文化財に指定され、平成26年には、ユネスコ無形文化遺産(人類の無形文化遺産の代表的な一覧表)に日本の手漉き和紙技術(石州和紙・本美濃和紙・細川紙)が登録された。
前述にも書いた通り、和紙の製法には「手漉き」と「機械抄き」がある。
〈手漉き〉
手漉きは、伝統的な「流し漉き」「溜め漉き」の技法を使用し、職人が一枚一枚丁寧に漉いている。仕上がった紙には四方に手漉きの特徴である「耳」がある。また、職人の手作りの為、一点として同じものはない。手漉きの技法には、前述でも述べた通りに2種類の技法がある。「流し漉き」は日本独特の技法で、靱皮繊維(雁皮・三椏・楮など)の紙料にネリ(植物性粘液)を混ぜ、簀桁ですくい上げ、全体を揺り動かしながら紙層をつくり、簀桁を傾けて余分な紙料を流しながら漉く。繊維が絡み合うため、横にも縦にも破れにくい紙が出来る。「溜め漉き」は、中国古来の紙漉きの技法。日本独自の流し漉きと違い、ネリを用いず一枚ごとに簀桁の中の水を簾の間から自然に落として漉き上げるので、「機械抄き」では製造できない厚さのある紙を造る事ができる。証券や賞状などに用いられる局紙は溜め漉きで漉かれている。
〈機械抄き〉
「機械抄き」は和紙の伝統的な技法である「流し漉き」の手法を機械に置き換えて製造する方法。比較的均一な紙を造ることができ、洋紙ほどではないが大量に生産をする事が可能である。しかし、伝統的な原料から製造するので、「手漉き」と同様に天然原料の持つ光沢や風合いを活かした美しく強靭な紙を造る事ができる。本来は「手漉き和紙」こそが「和紙」という存在であったとされている。しかし、日本古来の「手漉き」が色々な道具や手法を取り入れて進歩し、現在に至ったという事を考えると「機械抄き」も「和紙」の形の一種と考えられている。
第3章 和傘の歴史
1. 和傘について
世界で初めて傘が登場したのは、約4000年前の古代エジプトやペルシャで、当時の壁画にもその様子が残っている。
当時は、今の様に雨をしのぐ道具として使用しておらず、太陽の日差しを遮る事を目的とした日傘として使われだした。また、現在の様に開閉機能はなく、常時開きっぱなしだった。その後、傘はヨーロッパに渡り、富の象徴として多くの帰属が使用する事になった。13世紀頃(西暦1201~1300)のイタリアでは、傘の骨組となるフレームが考案され、18世紀頃になると現在のような傘の形状になった。そして、これまで日傘として使われてきた傘だったが、次第に雨避けとして傘をさす人が
増えていった。日本で最も古く傘についての記述があるのは、日本最古の歴史書である「日本書紀」に登場した。日本書紀で記述されている傘は、現代の傘の形状ではなく、「かぶりがさ」と知られる笠である。また、古墳時代には笠をかぶった埴輪なども残されている。
この当時の笠の材料は、イグサ、ヒノキ、竹などが使われている。この被り笠は現在も屋外の労働に、雨や日よけとして広く東南アジア各地でも使われている。一方、軸を中心に頭の上に広げる「傘」が日本に伝来した時期については詳しく分かっておらず、古墳時代の後期、鉄明天皇の時代には、百済から仏具の傘(天蓋)が日本に献上したと記憶されている。
和傘は平安時代前後に仏教やお茶・漢字等と同じく中国から伝来したと言われている。平安時代に登場する和傘は現在のような形ではなく、傘(蓋・笠)であり、天蓋のような覆う形のような物で、貴人に差し掛けて日除けや魔除け、権威の象徴として使用されていた。また、この時代では傘は開いたままで閉じる事は出来なかった。開閉が出来る様になったのは、安土桃山時代で、その頃には、製紙や竹細工の技術の進歩により、和紙に油を塗り防水性を持たせ、開閉できる「和傘」が作られるようになった。
和傘が広く一般に使われだしたのは分業制の発達した江戸時代中期のことで、江戸時代の浮世絵にも傘をさしている町人の姿が多く見受けられた。生活必需品として、広く普及していた事が伺える。普及するにつれ、和傘はただの日常品としてだけでなく、装いにアクセントを付けるファッションの小道具でもあったので、美しさも兼ね揃える様な様々な技巧やデザインを凝らした和傘が生まれた。和傘は、日常使いだけでなく、歌舞伎や日本舞踊、茶道の中でも取り入られてきた。また、傘に屋号をデザインしたものを客に貸与する事で、雨具としてだけでなく、宣伝の道具としても使われた。
和傘は、和紙、竹、木などの自然素材で作られている傘の総称となる。和傘は柿渋や油などを塗って防水加工した和紙などが用いられている。その和紙を数十本の骨組みで支える構造となっている。柄と骨部分には主に竹や木が使用されている。和傘の種類は、以下の種類がある。
・番傘(ばんがさ)
江戸時代に誕生した和傘。特徴としては、シンプルな構造と無骨な重厚感が挙げられる。持ち手は太い竹を使用し、傘布に使われる油紙は厚く、基本的に無地で、洋傘と比べると大振りで重量がある。番傘は、もともと商家が屋「〇〇の十三番」を入れて使用していた事から番傘と呼ばれるようになった。
・蛇の目傘(じゃのめがさ)
歌舞伎役者が舞台で使用することでおなじみの蛇の目傘。特徴は、骨組みの細さと装飾的な趣向である。江戸時代に軽量化されたことで、腰に差して使われていた。番傘に比べるとデザイン性があり、細身の骨を使用していて、女性でも使いやすい傘だ。中を白く、周辺を黒・紺・赤などで太く輪状に塗った模様が、蛇の目に見える事から、「蛇の目」と呼ばれている。
・日傘(ひがさ)
日傘は傘布に油による防水加工をしていないため、雨傘としては使用できないが、和傘独特の風合いや、程よく日光を遮り、透過する見た目が非常に美しいため、夏場に活躍する和傘だ。特徴としては、一般的に雲龍紙を使用したものが定番だが、一本ずつ表情の異なる手絞りの和紙を使ったものから、華やかな型染和紙を使ったものまで、多種多様だ。ろくろ部分には、飾り糸が付けられている。
・舞傘(まいがさ)
名前の通り主に舞台で使用される和傘で、和紙のものから絹を使った高価なものもある。デザインは、舞の邪魔にならないように基本的に無地の物が多いが、「助六」と呼ばれる紫地に白い輪状に色抜きしたものから渦巻き模様などもある。舞傘も防水加工はされていないが、日傘としても活用可能である。
この様に、和傘には雨傘としてではなく、日傘や舞傘、宣伝の為にも使われてきた。
次に、岐阜和傘の制作過程を述べていく。和傘の制作は大きく分けて、轆轤・柄作り、つなぎ、張り、仕上げの工程がある。一般的な轆轤作り以外の工程は現在も手作業で行われている。また、和傘は「分業制」で作る事が特徴で、この制度がある事で、大量生産と品質の向上が図られてきた。
傘張りは、以下の工程で作られた。
①親骨先端の軒と軒糸に、帯状に軒紙を張る。(軒付け)
②親骨と小骨を繫いだ中節と中糸の上に中置紙を張る。(中置紙張り)
③軒から中心にかけて、平紙を親骨に張る。(平張り)
④頭轆轤に紙を巻き、親骨とつないだ部分に、カナヘラやカナオサエヘラで天井紙を押し込み、ひだを作りながら張る。更に数度頭轆轤に紙を巻き張り、下部を天井紙と接着する。(天井張り)
⑤小骨の手元轆轤と繫いだ部分に、手元紙カナヘラやカナオサエヘラでひだを作りながら張る。(手元紙張り)
この工程で傘に和紙を張っていく。
2.岐阜和傘の成り立ち
岐阜和傘は、主に加納地区で作られてきた。岐阜和傘の起源として、今現在考えられているのは2説ある。
①寛永16年(1639年)藩州明石藩主戸田丹波守重(7万石)が加納城に移封された時、一所に明石から傘屋かね右衛門一家を連れ、傘張りを始めさせた。(文化 2 年〔 1805〕 6 月の久運寺留書の記事より )。金右衛門が加納にきたという事実はあるがそれが直接に傘産業を興したとはまだ傘が一般庶民には使用禁止されていたので家中の需要に応ずるのみで商品として製造販売されなく、あまり需要がなく発達したとは考えられにくい。
②宝暦 6 年(1756)永井伊賀守尚陳が加納に移封されたとき、わずか 3 万 2 千石と 10 万石の城下町にとって財政が苦しく、家臣たちは生きていくために、“武士は食わねど高楊子”といって生活は苦しいが武士は内職が許された時代ではなかったので、目立たない内職として傘骨削り、轆轤作りに従事し、また藩主の奨励が出たことにより地場産業として確立していった。また永井氏の時代、天保年間 (1781~ 88)には都会で傘の需要が高まってきた時代で産業として伸びた時期と思われる。
(引用元:岐阜大学地域課学部,地域学実習報告書,2004,3,第7章加納の和傘産業と現状とこれから,p.22)
この様に、岐阜和傘の起源は諸説ある。また①は、藩主の移封では、浄化の商工業者が従われるのは通例で、その中で金右衛門が一緒に来たのもあり得る事から、この金右衛門が加納で傘を広めたといえるかもしれない。加納にある久運寺の過去帳には、初代金右衛門から3代目まではっきりと傘屋長次郎と記されている。しかし、金右衛門が傘を加納で発達させたかは記されていないため不明である。また、戸田氏は7万石といえども領地はだいぶ輪中地帯にあり、災害が度々続き、財政が苦しかったと考えられる。その為、戸田氏が移封された頃は加納で岐阜和傘が産業として成立するほどではなかった。一方、宝暦5年に加納城の藩主となった永井直陳の頃は、傘の需要が増え、産業として成立する基礎が確立されてきたと考えられる。寛永の歴史的起源と宝暦の産業的起源の二つが岐阜和傘の起源であるといえる。
加納で和傘の産業が本格化したのは、永井直陳が加納城藩主をしていた時代である。石高の減少や度重なる水害による財政難のため、武士に和傘の内職を薦めた。本格化した頃には、武士は傘骨削り、埴輪作り、柄竹作りなどをし、加納町民・農閑期の農民は傘張り、仕上げをするなどといった分業制が生まれてきた。この分業制があったからこそ加納で和傘が栄えたともいえる。
文政9年になると宮田吉左衛門(江戸席酒造家で宿老)と森孫作(脇本陣の年寄)が加納藩より領分傘問屋を申し付けた。この狙いとしては財政難に苦しむ藩役人が城下の傘作りに専売制を実施し、江戸積産業を育成して、その利益を回収しようとした。この統制は全体で5万本を超えていったが長くは続かなかった。また、この江戸積については、従来仲買人制度の頃から行われており、統制の時期に始まったものではない。
加納傘の生産量はその後年々増えていき、安政6年の4月の「加納領傘銀桟留出来数取調帳によると、傘生産者が加納の町内に35人で、その中の上位の3業者の主な販路として、江戸、京都、など遠隔地で出荷し、それ以外の業者は岐阜・名古屋など近辺に出荷していた。その時の加納で作られた傘の生産量は、業者によってばらつきはあるが、全て合わせると加納町内だけで、49万1380本を生産していた。
明治維新の後、当時の加納藩主と重役は東京へ移住したが、一般武士はほとんど残り、傘生産に従事した武士も多く残った。明治5年頃には、上加納の中村源之助が絵日傘を神戸のイギリス商人と取引し、杉山新七は小型の絵日傘を製造して海外輸出を試み、この年は年間150万本の生産を記録した。明治12年には、オーストラリアのシドニーで万国博覧会が開催され、加納の赤塚源次郎が加納傘13種を出品した。この事が岐阜和傘の海外進出への基礎を築き上げた。その後、東海線開通により、郵送時間の短縮、包装堅固などの企業利益からほとんどの業者が製品郵送で往来使っていた水運から鉄道を使うようになり、東京が主な取引先だったが、他府県の直接販売に成功し、北は北海道、南は宮城県まで京阪地方にも直接販売を拡張していった。明治36年第五回国内勧業博覧会が大阪で開催されるとき、加納傘問屋から多数出品をし、加納傘の精美にして安価であるため飛ぶように売れ、それ以降も出店をし、加納傘は1日1万本から2万本へと著しく生産量が増加した。しかし、大正元年に入ると、大阪の松坂屋が原価を無視した宣伝がされ、傘は飛ぶように売れ、同様の事を松坂屋だけでなく、三越、大丸でも行われ、京都、東京にも波及した。しかし、この事態は都市の傘小売店に大影響を与え、問屋や製造元までに影響は広がった。その結果、安価に傘が大量に売られた事で粗製品であるように思われ、実際粗製品が市場に出回り、評判が悪くなった。昭和に入り、当時の岐阜和傘同業組合の会長だった赤塚源八は県当局から助力を得て、取引上の欠陥、製品、業界の改良、回復をし、以前あった組合を解散させ、昭和10年に新たに「岐阜県傘商業組合」を誕生させた。その後、昭和20年代半ばには、生産1000万本を超えている。その後は洋傘の普及、交通機関の発達、生活様式の変化により、和傘の需要は戦争直後で物資不足だった昭和23年~25年をピークに急激に落ち込み、洋傘の生産と和傘の生産が逆転した。
3.長良川と岐阜和傘の関係性について
長良川は岐阜和傘にとって欠かせない存在だ。長良川は、公共交通機関が発達する前、運送の手段として使われてきた。
各地で城下町や門前町、宿場町などの建設の為に大量の木材が運ばれたり、幕府・大名の御用物資・年貢米などの郵送、各地の商品生産との流通や荷船による船運の役割などにも長良川は活躍してきた。長良川流域には各地に川湊ができ、大小の船が頻繁に往来していた。
また、長良川が伊勢湾に繋がる事から東京や大阪にも出やすかった。その為、岐阜和傘の原材料である和紙や竹なども頻繁に運送されていた。また、加納町が長良川に近い事もあり、出来た和傘をすぐに東京や大阪に出荷出来る位置にあった。また、長良川は水運としての役割だけでなく、文化の発達の役割もしていた。長良川の流域には多くの伝統文化が生まれた。清流の水を使い染める郡上本染、長良川と津保川の水運や水を使う関市の刃物産業、長良川で捕れる鮎を取る漁法鵜飼などが挙げられる。その内の一つが岐阜和傘である。長良川流域には上述でも述べた通り様々な伝統文化が誕生してきた。その中には、岐阜和傘の原材料となる美濃和紙、周辺の産地で取れる良質な竹、エゴの木、柿渋・亜麻仁油・桐油などがあった事と運送の事も合わせると岐阜和傘を作る環境が整っていた。長良川があったからこそ岐阜和傘は発達してきたのである。
第4章 デジタルアーカイブと地域活性化
1.デジタルアーカイブについて
今回の研究では、デジタルアーカイブを活用している。デジタルアーカイブとは、「デジタル技術を用いて作成されたアーカイブという意味の造語」(特定非営利活動法人,“デジタルアーカイブとは”,https://jdaa.jp/ ,最終閲覧日:2023年12月26日 )だ。アーカイブは、古文書や公文書館というのが元来の意味である。デジタルアーカイブの対象は、公的な博物館、図書館、文書館の収蔵資料、自治体・企業等の文書・設計図・映像資料などを含め有形無形の文化・産業資源など多岐に渡る。また、完成されたものだけでなく、そのプロセスに関する資料も対象となる。
デジタルアーカイブはそれらを収集するだけでなく、デジタル形式で記録し、データベースの技術を用いて保存、蓄積をして、ネットワーク技術を用い検索を可能にすることで持続的に活用するまでがデジタルアーカイブである。この様に蓄積したデータは、研究や学習支援、地域の振興、防災、経済の発展、新たなコンテンツの創作などの活用が可能となる。この事からデジタルアーカイブは地域循環型社会の社会基盤として重要視されている。
デジタルアーカイブにする事で、文字、図表、画像、映像、音声などの様々な情報を統合して扱う事が出来、保存や複製をしても劣化しない事が特徴である。また、分野を横断した関連情報の連携・共有も可能となり、ネットワーク技術を使い、時間や場所にとらわれず情報やコンテンツへのアクセスも簡単に行える事からデジタルデータのメリットや特徴がデジタルアーカイブの役割を担っている。デジタルデータで記録する事で、長年の経験や研鑽により培われた個人の技術などは、言葉や文字にも表しにくいため継承が困難になる事も少なくない。しかし、デジタルデータを活用する事で、形式知可出来る可能性があり、技術の継承や知識の共有などに役立てる事が出来る。また、文化財や文化遺産がアーカイブされると考えがちだが、地域の文化や伝統芸能、生活の記録は、貴重な地域資産としての価値があり、産業技術や職人の技術などを中心とした伝統産業、日常の生活、テレビ、ファッションなども社会全体の財産を記録として残す事が求められている。また、過去だけでなく今も残す事も必要である。今を記録し、残していく事で、震災や自然災害の復興に役立つことも重要視されている。これらがデジタルアーカイブの役割である。デジタルアーカイブの活用事例として多いのは、博物館、図書館、公文書館などの公的な施設が多い。特に博物館は、デジタルアーカイブを利用したデジタルミュージアムを各地の博物館や大学で行っている。岐阜女子大学でもデジタルミュージアムが行われており、内容としては、全国各地の文化情報を取り扱っている。
また、デジタルアーカイブのメタデータを提供し、検索・閲覧・活用できるプラットフォーム「ジャパンサーチ」もある。日本国内で保有する様々な分野のコンテンツを提供している。利活用の例としては、検索機能を提供したり、インターネット上でギャラリーを作る事が出来る。
2.岐阜県とデジタルアーカイブの活用例について
ここでは、実際に岐阜市ではどの様なデジタルアーカイブが活用されているかを述べていく。
①岐阜市digitalarchive写真貸出システム
このサイトでは、岐阜市の「観光振興を目的とした広報活動に利用しても羅う事を目的としたデジタルアーカイブを活用したサイトである。デジタルアーカイブの対象は、岐阜市の伝統文化である鵜飼を始め、長良川や金華山、史跡・旧跡、町並み、博物館など岐阜市が対象である。写真貸出システムというサイト名の通りに写真を利用する際には、利用申し込みをする必要がある。
②岐阜県図書館
岐阜県図書館では、岐阜県関連資料や地図資料等を図書の検索と同じように「資料検索」のページからキーワードで検索できるようになっている。岐阜県図書館では、ウェブサイトで公開しているデジタルコレクションで、パブリックドメインを付している画像は、申込書等の手続きが条件を守った上で不要となっている。
③岐阜市歴史博物館
岐阜市歴史博物館では、ウェブサイトに館蔵品一覧を公開している。館蔵品一覧では、岐阜市歴史博物館が所蔵する資料をテーマごとに紹介している。テレビ放映や刊行物への掲載、インターネット公開、展示パネルでの刑事での目的で利用する場合は、申請を行う必要がある。
④岐阜県博物館 デジタル展示室
ここでは、岐阜県博物館の収蔵品がインターネット上で無料で見れるようになっている。カテゴリに分かれており、収蔵品の写真は、様々な角度から見れるようになっている。所蔵品の説明もされている。
岐阜県でデジタルアーカイブを行われているのは、公的な施設が多かった。今回だと博物館や図書館だとほとんどの所では、所蔵されている作品が家にいても見られる様になっていた、また、データでの貸し出しや画像を静止画だけではなく、様々な角度から見られるような工夫をしている事が分かった。
3.伝統工芸品のデジタルアーカイブの活用事例について
ここでは、実際に伝統工芸品のデジタルアーカイブ化をし、どの様な活用がされているのかを国立工芸館の一例を基に述べていく。
・国立工芸館
国立工芸館では、2020年10月に石川県金沢市に移転開館した国立工芸館が所蔵する一部の工芸作品を、3Dデジタルアーカイブ化をし、設置したタッチディスプレイで公開した。また、2Dでのデジタルアーカイブ化も行った。
上の写真の様に作品が展示された。実物展示では見られない展示品の器物の底などが見られるように様々な角度から見られる仕様となっている。展示品の写真だけでなく、キャプションも一緒に組み込まれている。
この様な画面になっており、タッチディスプレイの為、来館者好きな様に展示品を動かし、見る事が出来る。また、多言語にも対応している。2Dの方では、国立工芸館のコレクションの中で気になる作品画像からその作品の解説や技法を閲覧する事が出来る。検索機能が主となってくるため、年代選択から選ぶことが出来たり、分類選択など様々な角度から検索する事が出来る。
この様な画面から来館者が好きな作品を選ぶことが出来る様になっている。
作品を選択すると「解説」・「技法」・「拡大画像」を見る事が出来る。2Dなので、3Dの様に自分で様々な角度を見ようと動かす事は出来ないが、拡大したり、解説だけでなく、技法も合わせて見る事が出来る。
検索機能では、様々な方法から検索する事が出来る。年代からの検索では、選択された年代に該当する作品一覧が表示される。分類選択でも選択された分類に該当する作品の一覧が表示される。
国立工芸館では、デジタルアーカイブを展示する事によって、様々な方面から伝統工芸品について知る事ができる様になっていた。国立工芸館は当初、展示品を飾る際に鏡を使うという案もあったが、難しく物理的規約に縛られない仮想現実を用いて作品を紹介する取り組みを行った。デジタルアーカイブを用いる事で、今まで見れなかった部分を見る事ができるのは、デジタルアーカイブを活用したからこそ伝統工芸品に身近に触れて知ってもらうが出来るのである。
第5章 岐阜市文化遺産デジタルアーカイブ
1.岐阜市文化遺産とデジタルアーカイブの関係性について
ここでは、岐阜市文化遺産とデジタルアーカイブの関係性について詳しく述べていく。文化遺産とは、その国や地域またはコミュニティの歴史・伝統・文化を象徴した存在である。文化遺産は様々な種類があり、有形の物から無形の物まである。岐阜市にも様々な文化遺産がある。今回の研究のテーマである伝統工芸品から史跡や銅像、絵画など様々な文化遺産が岐阜市にある。様々な文化遺産が岐阜市にある中でその文化遺産がどこにあるのかどの様な物なのかを紹介するためにもデジタルアーカイブという方法は最適であると思う。実際に、岐阜市のホームページには岐阜市の文化遺産を紹介するページがある。
上の写真の様に、写真だけでなく、解説や史跡についての歴史もアーカイブをしている。その他にも文化財一覧では、国指定の文化財は、文化庁のホームぺージにリンクが飛ぶようになっている。
また、前述でも述べた通り岐阜市にある博物館や図書館に所蔵している作品もサイト上で公開されている。岐阜市立図書館でも所蔵している文化財をデジタルアーカイブとして誰でも見られるようになっている。
また、メディアコスモスでは、昔の地図や写真、伝統工芸品などをデジタルアーカイブをした物を今と比べたマップが一階のシビックプライドプレイスで展示されている。
この様に岐阜市では文化遺産をデジタルアーカイブをし、活用している。文化遺産をデジタルアーカイブする事で町おこしや後世に伝える役割をしている事が分かった。
2.岐阜和傘デジタルアーカイブのコンテンツ構成
ここでは、デジタルアーカイブを使って岐阜和傘のコンテンツを構成を述べていく。デジタルアーカイブを使ったコンテンツはたくさんあるが、今回は岐阜和傘の歴史・技術を知らない人、若い世代に向けたコンテンツを構成する。今回このコンテンツとして入れる要素で特に重要視して入れる要素は「歴史」と「技術」である。まず初めに「歴史」と「技術」をどの様な構成デジタルアーカイブにしていくかを述べていく。この後世でのデジタルアーカイブの撮影方法は、写真を中心に考えている。また、どの様な所を撮影するかは、岐阜和傘だけを撮影するのではなく、岐阜和傘に関わる場所や物、加納の歴史、岐阜和傘を作成している様子などをデジタルアーカイブをしていく。また、デジタルアーカイブをした物は、一つのウェブサイトにまとめたいと考えている。そこでは、「歴史」と「技術」をカテゴリに分ける。例えば、一つのウェブサイトで「歴史」と「技術」を分ける事で、検索をもっとしやすくなると考える。また、解説も詳しく書いていきたいと考える。
歴史と技術を中心にアーカイブをしていく予定だ。アーカイブで載せる写真や動画は、様々な方向から撮っていく。このウェブサイトでは、岐阜和傘の歴史と技術を知らない人や若い世代の人にも分かりやすく伝える事が目的のコンテンツにしてく。
3.岐阜市伝統工芸品と長良川の関係性のアーカイブのコンテンツ構成について
ここでは、岐阜市の伝統工芸品とアーカイブの関係性を分かりやすくまとめたコンテンツの構成にしていく。前述では、岐阜和傘を中心に取り上げてきたが、このコンテンツでは、岐阜市の伝統工芸品である岐阜和傘を始め、岐阜うちわ、岐阜提灯の共通点である長良川の関係性について写真や図、表などを用いて、若い世代の方にも分かりやすく伝えたいと考えている。まずは、岐阜和傘と岐阜うちわ、岐阜提灯の説明をするページを設ける。その後、長良川についてのページを設け、長良川と岐阜市の伝統工芸品をデジタルアーカイブでの資料を使いながら、図や表を用いて説明していきたいと考えている。
この様に図や写真を使って分かりやすく岐阜市の伝統工芸品と長良川の関係性のアーカイブをウェブサイトでまとめていく。長良川のアーカイブや図を用いながら、流域にある伝統工芸品も一緒に紹介していく事で関係性について詳しく理解してもらえる様にする。このウェブサイトで長良川と岐阜市の伝統工芸品の関係性について若い世代や知らない人にも興味を持ってもらえるサイトにする。
4.岐阜市文化遺産の活用について
ここでは、デジタルアーカイブ以外に現在岐阜市文化遺産を知ってもらえるまたは盛り上げているどの様な活用をしているかを述べていく。
・和傘CASA
和傘CASAは、岐阜県岐阜市港町にある岐阜県で唯一の和傘専門店である。長谷川てしごと町屋というお店の中に和傘CASAはある。和傘CASAでは、和傘の販売から貸出までやっている。和傘CASAは店舗からの販売もしているが、インターネット上での販売も行っている。店舗では、実際に和傘を触る事が出来たり、レンタルをしている。和傘CASAの建物には和傘以外にも提灯や活版印刷など様々な文化遺産も取り扱っている。
・岐阜灯り物語
岐阜市で行われる岐阜市の伝統工芸品とプロジェクションマッピングがコラボしたイベントが岐阜公園や正法寺等で行われる。このイベントは、毎年行われており、岐阜和傘と岐阜提灯を用いて行われる。また、連動イベントとして、岐阜駅前広場から金公園でも同様のライトアップが行われている。
ここでは、岐阜市の文化遺産をデジタルアーカイブ以外の方法で紹介しているイベントや店などについて紹介してきた。
第6章 結 言
本研究では、岐阜和傘の歴史と技術を中心に岐阜市の伝統工芸品と長良川の関係性をデジタルアーカイブを用いて、若い世代や岐阜市の伝統工芸品を知らない人に伝えていく事を目的にこれまで述べてきた。若い世代や岐阜市の伝統工芸品を知らない人に、技術と歴史を伝えるためには、紙媒体だけでなく、デジタルアーカイブを活用する事でより多くの人の目に留まるのではないかと私は考えた。
岐阜市の伝統工芸品を多くの人に知ってもらえる事で、現在問題視されている後継者不足が解消するのではないかと私は考える。岐阜和傘では、和傘を非日常の物として使うのではなく、昔の様に普段使いしてもらえる様に様々な取り組みが行われている事が本研究を進めていく中で分かった。岐阜和傘を販売している「和傘CASA」の方にお話を聞いて、岐阜和傘は普段使いをする事で和傘自体の劣化を防ぐ事が分かった。また、現在は岐阜和傘の柄を洋服にも合わせてもらえる様に様々なデザインがある。
また、岐阜市では、伝統工芸品とプロジェクションマッピングとのライトアップのイベントが毎年行われている事も分かった。岐阜和傘の技術と歴史をデジタルアーカイブをする事で、岐阜和傘を知ってもらい、現在行われている取り組みを知ってもらえるのではないかと考えた。
また、岐阜市の伝統工芸品と長良川の関係性をデジタルアーカイブにする事で、岐阜市の伝統工芸品がどの様にして誕生したのかを知ってもらい、岐阜市の伝統工芸品を知ってもらう事で現在ある問題の解決に繋がると考える。デジタルアーカイブを活用し、岐阜和傘を中心に岐阜市の伝統工芸品の普及が出来る事が本研究を通して分かった。
参考文献
1.和傘CASA (最終閲覧日:12月30日)
https://wagasa.shop/
2. 密柑水の文化センター 機関誌『水の文化』50号「江戸時代から続く岐阜・加納の和傘づくり」 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.mizu.gr.jp/kikanshi/no50/05.html
3.マルト藤沢商店 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.wagasa.co.jp/
4. 坂井田永吉商店 (最終閲覧日:12月30日)
http://kano-wagasa.jp/html/wagasa.html
5.世界農業遺産 清流長良川の鮎 (最終閲覧日:12月30日)
6.public relations office 和傘最大の生産地・岐阜市 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202306/202306_03_jp.html
7.日本洋傘振興協議会 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.jupa.gr.jp/pages/history
8.岐阜市 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.city.gifu.lg.jp/info/kidspage/1009717/1009718.html
9.加納町づくり会 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.city.gifu.lg.jp/info/kidspage/1009717/1009718.html
10.岐阜市漫遊 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.gifucvb.or.jp/outline/index.php
11.人力 (最終閲覧日:12月30日)
「人力」とは – 旧街道ウォーキング – 人力 (jinriki.info)
12.岐阜県 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/3156.html
13.環境省 (最終閲覧日:12月30日)
https://www.env.go.jp/water/meisui/H27senkyo/view/view_e10.html#:~:text=%E9%95%B7%E8%89%AF%E5%B7%9D%E3%81%AF%E5%B9%B9%E5%B7%9D%E6%B5%81,%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
14.全国鮎養殖漁業組合連合会 (最終閲覧日:12月30日)
http://www.zen-ayu.jp/ayu/#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E6%84%9B%E3%81%99%E3%82%8B%E5%84%AA%E7%BE%8E,%E3%81%A7%E5%91%BD%E3%82%92%E9%96%89%E3%81%98%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
15.Corsoyard (最終閲覧日:12月30日)
16.岐阜大学 (最終閲覧日:12月30日)
https://www1.gifu-u.ac.jp/~forest/rilc/senngonowasi.html
17.「ふるさとの岐阜の歴史をさぐる」No.27 (最終閲覧日:12月30日)
https://gifurekisi.web.fc2.com/rekisi/no27.htm
18.太田成和(1980),加納町史 下巻
19,岡村精次,神馬仁太郎(1929),岐阜傘に関する調査研究
20,岐阜和傘の技と美 パンフレット
論文資料
1.卒論要旨
建福寺
建福寺(けんぷくじ)は、長野県伊那市高遠町西高遠にある臨済宗妙心寺派の寺院である。
伝承によれば文覚上人(1139年~1203年)が独鈷池付近に開創。 康元元年(1256年)蘭渓道隆(大覚禅師)が立ち寄り、鉾持山乾福興国禅寺(ほこじさんけんぷくこうこくぜんじ)を興した。 のち、武田信玄の帰依により、静岡市の臨済寺から東谷宗杲禅師を招いて中興開山とし、妙心寺派となった。 貞享2年(1685年)、喝道和尚中興、明和3年(1765年)3月24日類焼、安永4年(1775年)少山和尚がさらに中興するも、嘉永4年(1851年)正月19日焼失、安政3年(1856年)に再建した。
武田勝頼が高遠城主の時、武田家菩提所とし、母諏訪御料人を埋葬して乾福院殿という。 さらに次の藩主、保科氏も菩提寺とし、大寶山建福寺と改名。 寛永13年(1636年)保科正之が会津若松藩主となり、移封する際に、鉄舟和尚が供奉して会津にも建福寺 (会津若松市)を創建した。
建福寺の石仏群
本堂への階段へ上る石段の両側および境内には、江戸時代の高遠石工によって作られた45体の石仏がある。45体の石仏のうち、西国三十三観音が33体、延命地蔵1体、願王地蔵1体、六地蔵6体、不動明王1体、楊柳観音1体、法陀羅山地蔵1体、仏足石などがある。
桂泉院
現在は田中の里にあるが、最初は法憧院曲輪にあった。開山は月哺禅師で、正平8年(1353)に時の城主であった高遠太郎家親が月哺禅師の高徳を聞き、城の鎮護の寺としたと言われる。その後、文禄元年(1592)に上野国松井田の補陀寺の住僧であった荊室広林が来て、どんな人でも出入りができる城外に移すよう勧め、清い泉の湧き出る桂の木の傍にうつして、龍澤山桂泉院と称するようになった。
梵鐘は県宝であり、勘助桜、仁科盛信の位牌堂、武田信虎の墓が伝えらえれ、守屋貞治の石仏などがある。
美篶刈る信濃の国上伊那の郡その名も高遠の里なる、龍澤山桂泉院の由緒をたづねまいらするに、今を去ること云々。
九七代後村上天皇の代丹波の国曹洞宗永澤寺の名僧月浦和尚、正平八年(1353)高遠の地に遍歴して来る。城主は木曽義仲六世の孫木曽又太郎家村の嫡子高遠太郎家親、和尚の高徳を聞き、城内に宝冠釈迦如来を安置し高遠城鎮護の寺とし、法瞳院と称す。開山月浦和尚、開基高遠太郎家親なり。
正親町天皇の天正元年(1573)甲斐の国主武田信玄の五男仁科五郎盛信公城主となり、板町村沖の平に存す諏訪大神を信仰し城内に遷宮、法腫院の僧に大神のお祭りも行わせる。
天正十年(1582)織田勢の攻勢により、仁科五郎盛信公の霊を弔い、霊牌を同院に納め。蒼龍院殿源晴清公成嶽建功大居士と血脈を誼号す。後陽成天皇の文禄元年(1592)二月二十九日群馬県松井田の大泉山補陀寺の十二世荊室廣琳大和尚高遠の地に来て法幡院に住す。その時の城主は内藤修理亮昌月で内藤修理信豊の子で和尚とは兄弟なり。これより大泉山補陀寺の末寺となる。
和尚の徳を仰ぎ、近隣の人々集まりしも城内にて誰でも白由に出入りできず、法化もできないので板町村龍ケ澤に庵を設けて住す。ある夜年たけたる翁ありて、戒法を授けてくださるように請い奉る、そこで「百丈野狐」の戒法を授けたところ、翁忽ち白龍となり桂ケ池のほとりに現れて、法施に清らかな泉を出しましょうと、高遠三泉の一「桂井の水」が湧きでて現在にいたる。和尚の高徳を聞き、城主昌月公村民とともに法腫院の堂宇を龍ケ澤に移し、その所の名をとりて、龍澤山桂泉院と命名す。
慶長五年(1600)三月二十九日である。中興開基内藤修理昌月。中興開山荊室廣琳大和尚。その後歴代の高遠城主に信仰され、十一月二十五日を開山忌とした。城主が参拝に来られるので、庫裡の書院の間を一段と高くし、高遠八ケ寺の一となり、高遠城鎮護の寺となる。内藤駿河守頼寧公より田地を与えられた。伊那市美篶洞泉寺・長谷村非持正随寺を末寺とす。