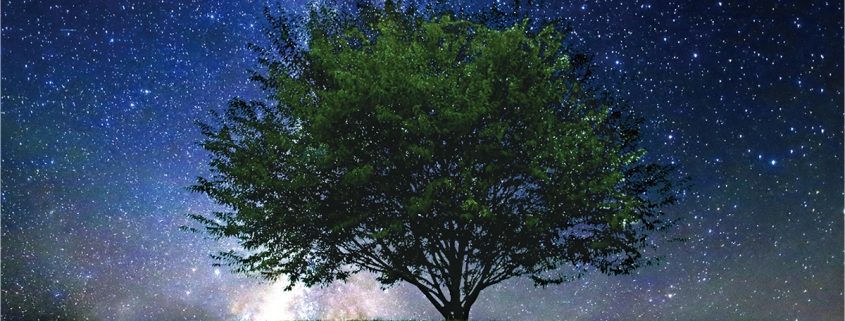【授業】調理科学
Ⅰ はじめに
調理をするうえで、各種調理操作(煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める)の特徴、調理操作による生じる食品の変化(温度、味、テクスチャー)を理解することは大切である。調理科学では、各調理操作の特徴、調理操作により生じる食品の組織や成分、物性変化を理解し、調理操作や食品の調理性について科学的な視点で理解する。
また、それらの知識を大量調理の基本と関連させ、応用できるようにする。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
調理科学では、基本的な調理操作(煮る、焼く、蒸す、揚げる、炒める)の特徴、調理操作により生じる食品の組織や成分、物性変化を科学的な視点で理解できる知識を修得することを目的とする。
Ⅲ 授業の教育目標
調理には、栄養面、衛生面だけでなくおいしさが求められる。そのため、食品の特性を知り、適切な調理操作を選択する必要が求められる。調理操作により生じる食品の組織や成分変化を科学的な視点で説明する。
第1講 米、小麦の調理特性
1.何を学ぶか
(1) 米の成分および構造
(2) 白飯、味付け飯、酢飯、炒め飯の調理
(3) 米粉の調理
(4) 小麦粉の成分および分類
(5) 小麦粉の膨化調理
2.学習到達目標
・米の成分および構造が説明できる。
・米の調理(白飯、味付け飯、酢飯、炒め飯)のポイント
(それぞれの違い)が説明できる。
・米粉の種類および調理(種類による違い)が説明できる。
・小麦粉の成分および品質特性による分類が説明できる。
・小麦粉の膨化調理について説明できる。
3.研究課題
(1) 白飯、味付け飯、酢飯、炒め飯のポイント(それぞれの違い)をまとめなさい。
(2) 米粉の種類および種類による調理特性の違いをまとめなさい。
(3) グルテン形成に及ぼす影響をまとめなさい。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 牛乳、鶏卵の調理特性
1.何を学ぶか
(1) 牛乳の成分
(2) 牛乳の加熱による皮膜形成
(3) 牛乳の酸による凝固
(4) 鶏卵の成分および構造
(5) 鶏卵の調理特性(希釈性、泡立ち性、熱凝固性、乳化性)
2.学習到達目標
・牛乳の加熱、酸添加による変化について説明できる。
・鶏卵の調理特性(希釈性、泡立ち性、熱凝固性、乳化性)について説明できる。
3.研究課題
(1) 牛乳の加熱による皮膜形成および酸による凝固に関与する成分、調理上の注意点をまとめなさい。
(2) 鶏卵の熱凝固性について、熱凝固に及ぼす添加物の影響も含めまとめなさい。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
Ⅶ テキスト
調理学 食べ物と健康④,木戸詔子,池田ひろ,化学同人
Ⅷ 参考文献
調理の科学,吉田恵子,綾部園子編著,理工図書
食品学Ⅱ,栢野新市,水品善之,小西洋太朗編,羊土社
【授業】管理栄養士 対策講座
Ⅰ はじめに
管理栄養士国家試験に合格するためには、これまで学修した授業内容の見直しと復習をし、自主的な学修姿勢を身に付けることが大切である。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
授業内容や勉強方法の見直しを行い、くり返し過去問等を解くことで、管理栄養士国家試験合格を目指す。
Ⅲ 授業の教育目標
15回の授業教育目標を示し、各講に学修到達目標を設定し、個々に学修の到達を確認することができる。
第1講 核酸の構造と機能
1.何を学ぶか
・核酸の種類と誘導体、およびその働き
・遺伝子の発現について
・臨床分野で利用される遺伝子解析技術について
2.学習到達目標
・核酸の構造とその名称がわかる。
・転写・翻訳の仕組みを説明できる。
・遺伝子解析技術の仕組みを説明できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 酵素の分類と機能
1.何を学ぶか
・代表的な消化酵素や代謝酵素について
・基質親和性、アロステリック酵素、酵素の活性調節について
・酵素の阻害様式と薬による酵素阻害について
2.学習到達目標
・酵素の名称と働きを説明できる。
・酵素の機能を説明できる。
・酵素阻害について説明できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:
Ⅶ テキスト
管理栄養士国家試験対策完全合格教本(上巻・下巻) 東京アカデミー編
Ⅷ 参考文献
【授業】基礎栄養学
Ⅰ はじめに
糖質の代謝は、栄養の代謝を学ぶ上で基礎かつ重要な分野であり、エネルギー代謝を理解する上で必須である。この分野をより理解するために、特に解糖系、TCAサイクル、電子伝達系について詳しく学び、生体内での代謝における位置づけについてより深く理解する。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
糖代謝の各経路について学び、エネルギー産生経路について学ぶ。またこれらの経路がどのように他の代謝にも作用をしているのか、理解を深める。
Ⅲ 授業の教育目標
糖が代謝される様子を、関連する経路を用いて説明できるように、各経路について理解する。
第1講
1.何を学ぶか
糖質が解糖系、TCAサイクル、電子伝達系で代謝される経路について学び、エネルギーがどのように産生されるのか、理解する。
2.学習到達目標
解糖系、TCAサイクル、電子伝達系の代謝について、生体の機能と関連付けて説明ができる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:
Ⅶ テキスト
オープンセサミシリーズ 管理栄養士 上巻 東京アカデミー編
Ⅷ 参考文献
・スタンダード人間栄養学 基礎栄養学 第3版 朝倉書店
・マッキー生化学 第6版 化学同人
【授業】化学・生物
Ⅰ はじめに
「化学」および「生物」は、管理栄養士のための土台となる科目である。「生物」では、人の細胞や組織、器官などの構造や働きについて、「化学」では栄養素の構造について学修する。人の体の仕組みや栄養素の構造の理解は、管理栄養士国家試験の「人体と構造及び疾病の成り立ち」に関わる知識となる。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
「生物」では、私たちが生きていくために必要な人の体の仕組みを理解し、「化学では、糖質・脂質・たんぱく質の構造の特徴を理解し、説明できるようになり、管理栄養士の国家試験に応用できるようなることを目的とする。
Ⅲ 授業の教育目標
2回の授業教育目標を示し、各講に学修到達目標を設定し、個々に学修の到達を確認することができる。
第1講 生物の細胞
1.何を学ぶか
・細胞小器官の役割
・細胞膜の構成成分と特徴
2.学習到達目標
細胞小器官と細胞膜の役割が説明できる。
3.研究課題
・管理栄養士国家試験の過去問で細胞に関わる問題の内容を正しく直しなさい。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 糖質・脂質・たんぱく質の構造
1.何を学ぶか
・糖質の構造の特徴
・脂質(主に脂肪酸)の構造の特徴
・たんぱく質の構造の特徴
2.学習到達目標
・糖質・脂質・たんぱく質の構造の特徴を説明できる。
3.研究課題
・管理栄養士国家試験の過去問で糖質・脂質・たんぱく質の構造に関わる問題の内容を正しく直しなさい。
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験
対面による筆記試験
Ⅶ テキスト
オープンセサミシリーズ 管理栄養士 上巻 東京アカデミー編
Ⅷ 参考文献
食と栄養を学ぶための生物学,堀田久子,池晶子,塚元葉子,化学同人
【授業】調理学実習Ⅰ
Ⅰ はじめに
調理の基本を身につけるため、調理の基本操作、食品の調理特性と扱い方、調理設備・器具の取り扱い方を学ぶ。また、衛生・安全管理や環境への配慮も踏まえ、おいしい料理を作ることができる能力を養う。さらに、後期の家庭料理技能検定2級または3級の受験を目指す。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
調理学の理論をもとに、食品特性をいかした調理の基本的技術を習得することを目的とする。
そのために、適切な調味のための計算や料理の栄養価計算ができる、料理ごとに適切な調理器具を選択し、使用法が理解できる、動物性、植物性食品各々の調理特性を理解した上で、適切な調理操作(茹でる、焼く、煮るなど)ができることをねらいとする。
Ⅲ 授業の教育目標
各講に学修到達目標を設定し、個々に学修の到達を確認することができる。
第1講 基礎調理①日本料理1
1.何を学ぶか
(1)主食:白飯
(2)主菜:厚焼き卵
(3)副菜:ほうれん草のお浸し
(4)汁物:油揚げと小ねぎのみそ汁
2.学習到達目標
・白飯の炊飯の要点について説明でき、白飯が調理できる。
・卵の調理特性が説明でき、卵料理が調理できる。
・青菜を色よく茹で仕上げるための調理法が説明でき、青菜を使った副菜が調理できる。
・煮干し昆布だしの取り方が説明でき、みそ汁が調理できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第2講 基礎調理②日本料理2
1.何を学ぶか
(1)主食:枝豆ご飯
(2)主菜:魚の煮つけ
(3)副菜:きゅうりとみょうがの酢の物
(4)汁物:かきたま汁
2.学習到達目標
・味付け飯の炊飯の要点について説明でき、味付け飯が調理できる。
・魚の調理特性が説明でき、煮魚が調理できる。
・乾物(わかめ)の扱い方について説明できる。
・きゅうりの輪切りができ、酢の物が調理できる。
・1番、2番だしのとり方が説明でき、かきたま汁が調理できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第3講 基礎調理③中国料理
1.何を学ぶか
(1)主食:チャーハン
(2)主菜:鶏肉のから揚げ
(3)副菜:胡瓜ともやしの中華風和え物
(4)デザート:牛乳のかんてん寄せ
2.学習到達目標
・炒め物について調理の要点が説明でき、炒飯が調理できる。
・揚げ物について調理の要点が説明でき、唐揚げが調理できる。
・胡瓜と人参のせん切りができ、和え物が調理できる。
・ゲル化剤としての寒天の扱い方が説明でき、寄せ物が調理できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第4講 基礎調理④西洋料理
1.何を学ぶか
(1)主食:ハムライス
(2)主菜:ポークソテー・ピーマン添え
(3)副菜:ポテトサラダ
(4)デザート:ぶどうゼリー
2.学習到達目標
・玉ねぎのみじん切りができる。
・肉の調理特性が説明でき、肉の焼き物が調理できる。
・芋の扱い方を説明でき、サラダが調理できる。
・ゲル化剤としてのゼラチンの扱い方が説明でき、ゼリーが調理できる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第5講 基礎調理⑤日本料理3
1.何を学ぶか
(1)主食+主菜:親子丼
(2)副菜:さといもの煮物
(3)汁物:けんちん汁
(4)デザート:りんご
2.学習到達目標
・鶏胸肉のそぎ切りができる。
・冷凍食品の扱い方が説明でき、冷凍食品を使った煮物が調理できる。
・野菜・果物の褐変について説明できる。
・ごぼうのささがきができ、具沢山の汁物が調理できる。
・りんごの皮の縦むきができる。
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
第6講 実技対策
1.何を学ぶか
(1)きゅうりの輪切り
(2)玉ねぎのみじん切り
(3)りんごの皮むき
(4)かきたま汁
2.学習到達目標
・きゅうり1/2本を4㎜以下の輪切りにできる(1分半以内)。
・玉ねぎ1/2個分を5㎜以下のみじん切りにできる(5分以内)。
・りんご1/4個を2等分にし、皮を縦むきできる(3分以内)
・かきたま汁を作ることができる(15分以内)
3.研究課題
4.映像資料
5.プレゼン資料
6.テキスト
Ⅳ レポート課題
課題1
(1)「基礎調理①日本料理1」実習の評価をレポートに記録する。
(2)家庭で応用として「卵または青菜を使った料理」を調理し評価を記録する。
課題2
(1)「基礎調理②日本料理2」実習の評価をレポートに記録する。
(2)家庭で応用として「味付け飯または魚の煮物」を調理し評価を記録する。
課題3
(1)「基礎調理③中国料理」実習の評価をレポートに記録する。
(2)家庭で応用として「炒め物または和え物」を調理し評価を記録する。
課題4
(1)「基礎調理④西洋料理」実習の評価をレポートに記録する。
(2)家庭で応用として「ゼラチンまたは寒天を使ったデザート」を調理し評価を記録する。
課題5
(1)「基礎調理③日本料理3」実習の評価をレポートに記録する。
(2)家庭で応用として「丼物または冷凍食品を使った煮物」を調理し評価を記録する。
Ⅴ アドバイス
課題1~5解説 各講の到達目標を達成するため、美味しく作る技術面のポイントや食材の特性を踏まえた科学的なポイントを踏まえ、記録すること。また、美味しく作るだけでなく、調味%や栄養価、衛生管理についてもまとめておくこと。
Ⅵ 科目修得試験:レポート試験
Ⅶ テキスト
(1)映像で学ぶ調理の基礎とサイエンス 学際企画株式会社
(2)「家庭料理技能検定公式ガイド 1級 準1級 2級 改訂版」女子栄養大学出版部
(3)日本食品成分表2024 栄養計算ソフト・電子版付 医歯薬出版株式会社 編
Ⅷ 参考文献
「調理のためのベーシックデータ第6版」松本仲子監修,女子栄養大学出版部,2022年
「流れと要点がわかる 調理学実習 ―豊富な献立と説明―第4版」香西みどり・綾部園子 編著,光生館、2024年
【授業】基礎生物
Ⅰ はじめに
「基礎生物」は、管理栄養士のための基礎科目となる授業である。「基礎生物」では、人の細胞や組織、器官などの構造や働きについて学修する。人の体の仕組みの理解は、管理栄養士として個々人に合わせた栄養指導や献立を考える上での根拠となる重要な知識である。また、学修した知識は、管理栄養士として必要な基礎栄養学や解剖生理学、生化学等を学ぶための基礎知識となる。
Ⅱ 授業の目的・ねらい
「基礎生物」では、私たちが生きていくために必要な人の体の仕組みを理解するとともに、今後管理栄養士として必要な基礎栄養学や解剖生理学、生化学等を学ぶための基礎知識を習得することを目的とする。
Ⅲ 授業の教育目標
15回の授業教育目標を示し、各講に学修到達目標を設定し、個々に学修の到達を確認することができる。
テーマ1 人体の構造、生物の構造
1.何を学ぶか
・人の体の成分・臓器
・人の細胞の特徴
・細胞小器官の役割
2.学習到達目標
・人の体の構造を踏まえて細胞の役割を説明できる。
・細胞小器官の役割を説明できる。
3.研究課題
・消化器系の器官を図示し、器官名をまとめなさい。
テーマ2 細胞の構造
1.何を学ぶか
・細胞膜の構成成分
・細胞膜を介した物資の移動
・受動輸送と能動輸送
・エンドサイトーシスとエキソサイトーシス
・浸透圧による濃度調節
2.学習到達目標
・細胞膜の成分・構造を理解し、細胞膜を介した物質の移動を説明できる。
3.研究課題
テーマ3 遺伝とDNA
1.何を学ぶか
・DNAの構成成分と構造
・染色体の構造
2.学習到達目標
・DNAの構造と役割を説明できる。
・染色体の構造と役割を説明できる。
3.研究課題
テーマ4 細胞分裂
1.何を学ぶか
・体細胞分裂の仕組み
・DNAの複製過程
・体細胞分裂と減数分裂の違い
2.学習到達目標
・体細胞分裂と減数分裂の違いを説明できる。
・体細胞分裂におけるDNAの複製の過程を説明できる。
3.研究課題
テーマ5 たんぱく質合成
1.何を学ぶか
・転写の過程
・翻訳の過程
・転写・翻訳によりできたたんぱく質の役割
2.学習到達目標
・転写・翻訳の過程からたんぱく質ができるまでを説明できる。
3.研究課題
テーマ6 酵素
1.何を学ぶか
・酵素の成分
・酵素の役割
・酵素の反応の調節(阻害反応・フィードバック調節)
2.学習到達目標
・酵素の役割を説明できる。
・酵素反応の調節について説明できる。
3.研究課題
テーマ7 栄養と代謝
1.何を学ぶか
・代謝の定義
・グルコースから解糖系・クエン酸回路・電子伝達系によりエネルギーができるまでの過程
2.学習到達目標
・グルコースからエネルギーができるまでの過程を説明できる。
3.研究課題
4.動画資料
5.プレゼン資料
テーマ8 栄養と代謝
1.何を学ぶか
・グルコースから解糖系・クエン酸回路・電子伝達系によりエネルギーができるまでの過程
2.学習到達目標
・グルコースからエネルギーができるまでの過程を説明できる。
3.研究課題
テーマ9 動物の組織
1.何を学ぶか
・上皮組織の構造の特徴と役割
・支持組織の構造の特徴と役割
・筋組織の構造の特徴と役割
・神経組織の構造の特徴と役割
2.学習到達目標
・人の体の組織について、構造・役割を説明できる。
3.研究課題
・血液の成分や役割についてまとめなさい。
テーマ10 動物の器官(消化系)
1.何を学ぶか
・消化器系の臓器の再確認と構造の特徴
・口腔・胃・小腸での栄養素の消化
・3大栄養素の消化過程の整理
2.学習到達目標
・人の体の消化器系の臓器を理解し、役割・構造を理解できる。
・消化酵素の役割を説明できる。
・3大栄養素が消化される過程を説明できる。
3.研究課題
4.動画資料
5.プレゼン資料
テーマ11 動物の器官(循環系)
1.何を学ぶか
・循環器系の定義
・心臓の構造
・体循環と肺循環による血液の流れ
2.学習到達目標
・人の体の循環器系の臓器を理解し、役割・構造を説明できる。
・体循環と肺循環を説明できる。
3.研究課題
テーマ12 動物の器官(腎・尿路系)
1.何を学ぶか
・腎・尿路系の定義
・腎臓の構造
・尿ができるまでの過程
2.学習到達目標
・人の体の腎・尿路系の臓器を理解し、役割・構造を説明できる。
・腎臓で尿ができるまでの過程を説明できる。
3.研究課題
テーマ13 動物の器官(神経系)
1.何を学ぶか
・神経系の定義
・中枢神経と末梢神経の違い、役割の違い
・自律神経による体内環境の調節
2.学習到達目標
・人の体の神経の種類・役割を説明できる。
・神経の働きによる体内環境の調節について説明できる。
3.研究課題
テーマ14 動物の器官(内分泌系)
1.何を学ぶか
・内分泌系の定義
・ホルモンの役割
・ホルモン分泌の流れ
・ホルモンによる体内環境の調節例(血糖値)
2.学習到達目標
・人の体の内分泌に関わる臓器やホルモンの役割を説明できる。
・ホルモンによる体内環境の調節について説明できる。
3.研究課題
テーマ15 動物の器官(免疫系)
1.何を学ぶか
・免疫の役割
・自然免疫と獲得免疫の違い
・獲得免疫に関わる細胞の役割、反応機構
2.学習到達目標
人の体の免疫反応の意味について説明できる。
自然免疫と獲得免疫の役割を説明できる。
獲得免疫における細胞の働きを説明できる。
3.研究課題
Ⅳ レポート課題
課題1
課題2
Ⅴ アドバイス
課題1解説
課題2解説
Ⅵ 科目修得試験:対面による筆記試験
Ⅶ テキスト
食と栄養を学ぶための生物学,堀田久子,池晶子,塚元葉子,化学同人
Ⅷ 参考文献
医療・看護系のための生物学,田村隆明,裳華房
第2版カラー図鑑 人体の正常構造と機能【全10巻縮刷版】,坂井「建雄,河原「克雅,日本医事新報社
資 料