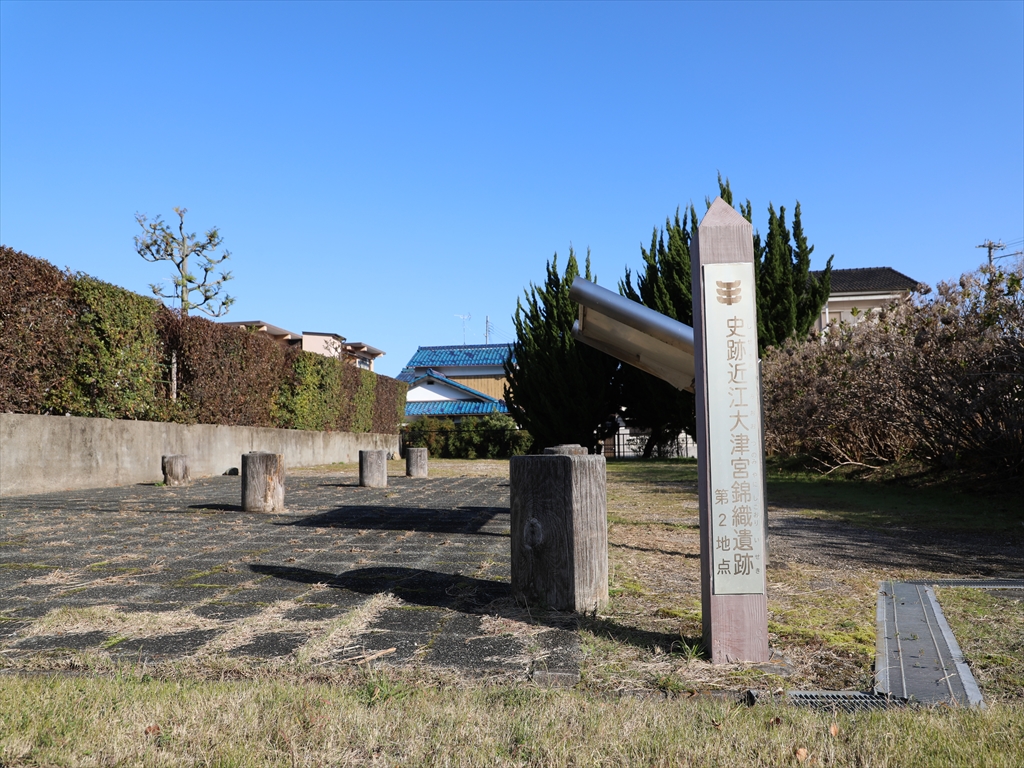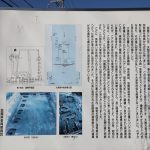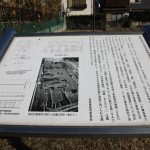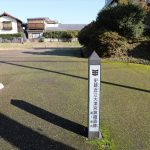【報告書】デジタルアーカイブinぎふ郡上 ~白山文化はいいもんだ~
日 時:平成31年2月23日(土)
時 間:13:00~16:30 受付12:30
場 所:郡上市総合文化センター(〒501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷207-1TEL:0575-67-1555 FAX:0575-65-2584)
参加費:無料
主 催:岐阜女子大学 共催:郡上市・郡上市教育委員会
後 援:デジタルアーカイブ学会・日本デジタルアーキビスト資格認定機構
郡上ケーブルテレビ放送センター
定 員::200名
内 容:(敬称略) 受付(12:30~13:00)
1.伝統文化芸能実演(13:00~13:30)
・「白鳥の拝殿踊」(国選択無形民俗文化財)
2.挨 拶(13:35~13:50)
松川 禮子氏(岐阜女子大学学長)
日置 敏明氏(郡上市長)
3.基調講演(13:55~14:45)
「文化遺産と記録」 佐々木正峰氏(国立科学博物館顧問・元文化庁長官・元文部科学省高等教育局長)
基調講演佐々木
文化遺産と記録
4.シンポジウム(15:00~16:30)
「デジタルアーカイブで地域の課題を解決できるか~白山文化を事例として~」
(パネリスト)
「白山芸能とデジタルアーカイブ」 曽我孝司氏(郡上市文化財保護審議会委員)
1パネリスト曽我
白山芸能とデジタルアーカイブ
「美濃馬場の文化財とその保存活用」 藤原 洋氏(郡上市教育委員会社会教育課)
2パネリスト藤原
「美濃馬場の文化財とその保存活用」
「加賀馬場と文化の再発見」 小阪 大氏(白山市教育委員会文化材保護課)
3パネリスト小阪
加賀馬場の文化の再発見
「越前馬場と文化財の保存活用」 宝珍伸一郎氏(勝山市教育委員会世界遺産推進室)
4パネリスト宝珍
プレゼン1
「地域資源デジタルアーカイブと地域活性化」 長丁 光則氏(東京大学大学院特任教授)
5パネリスト長丁
DAPCONパイロット事業
(コーディネータ)
久世 均氏(岐阜女子大学教授)
0シンポジウム











デジタルアーカイブinぎふ郡上報告書
関連資料