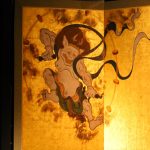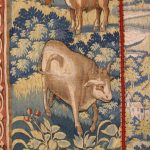祇園祭(八幡山)
町内に祀られている八幡宮を山の上に勧請したもので、常には町会所の庭にお宮を祀っている。山の上の小祠は総金箔の美麗なもので天明年間(1781~1788)の製作といわれる。水引は今までの金地花鳥仙園図唐繍にかわって昭和61年より十長生図の刺繍が用いられている。「十長生」とは不老長寿を意味する。前懸は慶寿群仙図で元禄3年(1690)に寄進されたものを昭和62年に復元新調したのである。見送は日輪双鳳人物文様の綴錦と藍地雲龍文様蝦夷錦がある。欄縁の彫金飛鶴は河原林秀興作と伝えられ、朱塗鳥居の上には左甚五郎作の木彫胡粉彩色の鳩が飾られる。その他に美術品として海北友雪(1598~1677)筆の祇園会還幸祭図屏風(京都市指定文化財)を所蔵している。
The object of worship of the small Shinto shrine which located on this float is Hachiman, one of the most famous Japanese gods.
The miniature shrine on the float is decorated with gold foil, and it is said to have been made in the Tenmei period, between 1781 and 1788.
(引用:http://www.gionmatsuri.or.jp/)
祇園祭(鯉山)
山の上に大きな鯉が跳躍しており、龍門の滝をのぼる鯉の奔放な勇姿をあらわしている。前面に朱塗鳥居をたて山の奥には朱塗の小祠を安置し素盞鳴尊を祀る。その脇から下がる白麻緒は滝に見立てられ、欄縁その他の金具はすべて波濤文様に統一されている。山を飾る前懸、胴懸(2枚)、水引(2枚)、見送は16世紀にベルギー・ブラッセルで製作された1枚の毛綴を裁断して用いたもので、重要文化財に指定されている。ベルギー王室美術歴史博物館の調査により、その図柄はホーマー作「イーリアス」物語の一場面で、トロイのプリアモス王とその后ヘカベーを描いたものといわれている。別に旧胴懸としてインド更紗のものがある。また、平成21年に前水引「金地果実文様」が、平成22年に後水引「金地花唐草文様錦」が新調された。
The theme of this float comes from a Chinese legend that if a carp (koi in Japanese) could swim up ryumon (a waterfall), it would become a dragon. The figure of the carp on this float is quite realistic, vivid and beautiful, as if a living carp is jumping up the waterfall. The shrine on this float is dedicated to Susano-o no Mikoto”, a powerful deity in Japanese mythology. The designs of most of the tapestries describe stories of the Trojan War in Greek literature. They were produced in the 16th century in Brussels, Belgium.
龍門の滝を登り切った鯉は、龍になるという中国の「登竜門」の故事を表現した山です。飛沫を上げながら滝を登る鯉の彫像は、左甚五郎の作と伝えられています。
また、前懸・胴懸・水引・見送はギリシャの英雄叙事詩『イーリアス』の名場面を描いた逸品です。欄縁を飾る金具は、激流を表現した波濤文様で立体感のある厚肉彫です。隅房掛金具も波を意匠しており、千鳥を一羽ずつ浮彫にしています。明治の名工・村田耕閑の作です。(引用:http://www.gionmatsuri.or.jp/)
祇園祭(後祭)
祭行事は八坂神社が主催するものと、山鉾町が主催するものに大別される。
一般的には山鉾町が主催する行事が「祇園祭」と認識されることが多く、その中の山鉾行事だけが重要無形民俗文化財に指定されている。山鉾町が主催する諸行事の中でもハイライトとなる山鉾行事は、山鉾が設置される時期により前祭(さきのまつり)と後祭(あとのまつり)[1]の2つに分けられる。山鉾行事は「宵山」(よいやま、前夜祭の意。前祭:7月14日 – 16日・後祭:7月21日 – 23日)、「山鉾巡行」(前祭:7月17日・後祭:7月24日)が著名である。八坂神社主催の神事は 「神輿渡御」(神幸:7月17日・還幸:7月24日)や「神輿洗」(7月10日・7月28日)などが著名で、「花傘連合会」が主催する花傘巡行(7月24日)も八坂神社側の行事といえる。
宵山、宵々山、宵々々山には旧家や老舗にて伝来の屏風などの宝物の披露も行われるため、屏風祭の異名がある。また、山鉾巡行ではさまざまな美術工芸品で装飾された重要有形民俗文化財の山鉾が公道を巡るため、「動く美術館」とも例えられる。
祇園祭は数々の三大祭の一つに挙げられる。京都三大祭(他は上賀茂神社・下鴨神社の葵祭、平安神宮の時代祭)、日本三大祭(他は大阪の天神祭、東京の山王祭、神田祭)、日本三大曳山祭(他は岐阜県高山市の高山祭、埼玉県秩父市の秩父夜祭)、日本三大美祭(他は前述の高山祭と秩父夜祭)のうちの一つであり、日本を代表する祭りである。
祇園祭という名称は、八坂神社が神仏習合の時代に、比叡山に属して祇園社と呼ばれていたことに由来する。祇園社の祭神の牛頭天王が仏教の聖地である祇園精舎の守護神であるとされていたので、祇園神とも呼ばれ、神社名や周辺の地名も祇園となり、祭礼の名も祇園御霊会となったのである。
その後明治維新による神仏分離令により神社名が八坂神社となった際に、祭礼名も仏教色を排除するため「祇園御霊会(ぎおんごりょうえ)」から「祇園祭」に変更された(ただし「祇園」という名称自体は前述の通り仏教由来である)。(引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%87%E5%9C%92%E7%A5%AD)
資料
公益財団法人祇園祭山鉾連合会