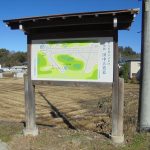山桜神社火の見櫓
所在地 高山市本町2丁目65番地
所有者の氏名又は名称 山桜神社
建築年代 昭和7年(1932)
施工 —-
員数 1棟
構造、形式及び大きさ
三層櫓、木造鉄板葺、
高さ(櫓のみ)6.95m
櫓下部3.36×3.36m
櫓上部1.52×1.52m
山桜神社社殿の南側建物の小屋梁上に柱を建て、棟上に櫓を組んでいる。櫓の袴底部は、3.4m四方、高さ7m規模、三層建で、東部に宝形造の見張小屋を置き、明治14年製造の半鐘を吊っている。神社の絵馬市とともに親しまれている。
〈特徴〉
当建物は、旧高山市内中心部に位置する商店街・本町通り内に立地し、山桜神社に付随する。
高山4代城主・金森頼直の愛馬「山桜」が、明暦年間の江戸大火で、主君をのせて江戸城の百間堀をこえ危急を救ったと伝えられている。馬の死後、厩(うまや)の跡に祠をたて、「山桜神社」「馬頭さま」として祀ったことが由来とされている。戦後になってから絵馬市が始まり、現在では8月1日から15日まで開催されている。地元民だけでなく観光客にも人気があり、夏の風物詩として本町通を賑わしている。
火の見櫓については、嘉永7(1854)年、馬頭組による「火消溜所屋根棟上げ・火之見櫓新設普請願書」が高山町会所文書にあり、当年に建てられたのが初源とされている。
明治5年の大火で類焼し被害を受けたが、明治14年に再建された。大正13年、歩広めにともなう神社敷地の拡張がなされ、昭和7年に現在の位置に移築され、現在の火の見櫓の建築年代は昭和7年になる。
木造平屋建、山桜神社拝殿南側の和室天井面上に基準階が設けられ、櫓の礎となっている。ここから受け梁に4つの柱をおき、周囲を4つの隅柱と桟で組み、外壁板で覆っている。櫓胴部は三層になっており、上下の梁間の筋違で補強している。構造は江戸時代からの櫓建築の技法を踏襲していると考えられる。
最上部の見張り台は、四方をガラス窓で囲い、見晴らしは良好である。また、半鐘が吊り下げられ、「飛騨国大野郡高山町 馬頭組 明治十四年辛巳六月」「東京 西村和泉守作」と銘があることから、再建時頃のものかと考えられる。
旧来の形態を踏襲した、木造の火の見櫓は非常に珍しく、関連する文書も多数残されており、歴史的価値は高い。商店街にありながら保存状態も良好であり、山桜神社の絵馬市とともに周辺住民に親しまれ、大切に保存されている。
関連資料